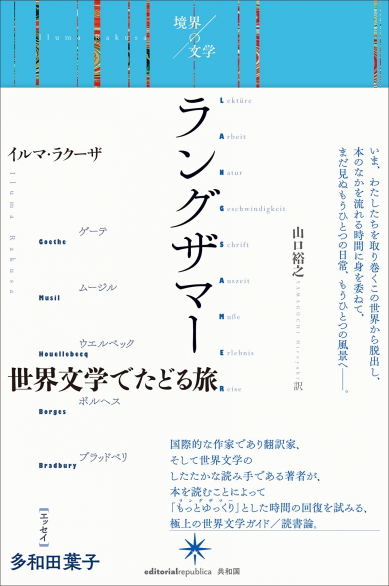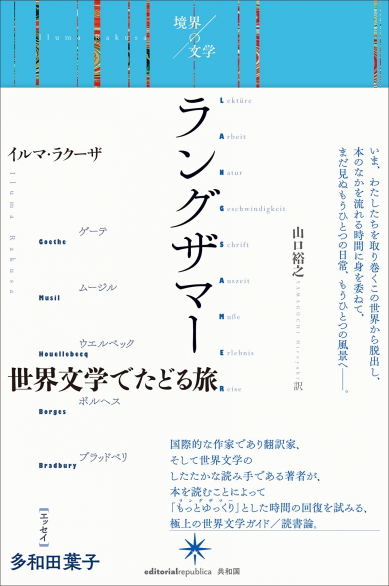速さはどうやら伝染するばかりではない。すでに自己目的的な性格をほ癒手中にしている。そしてさらなる加速を求めている。成長の限界、あるいはその他の限界について知りたいと思う人はいない。そういった限界は、現在のターボ経済の歯止めの効かない圧倒的膨張の要求とは相容れないものなのである。しかし、崩壊と内破の兆しが現われる前に、過剰な速度が蔓延していることへの警告に対して注意を向けるべきだろう。例えばそれは、暴走によって引き起こされた交通死亡事故(フランスの高速道路には「速さ? それとも命?」という簡潔明瞭な標語が掲げられている)であったり、大気圏内の排気ガスであったり、渋滞によって動かなくなった道路であったり、身体的・精神的なストレス症状(「急ぎ病」「加速症」「圧縮疲労」)であったり、生産の加速度的オートメーション化によって生み出された失業状態であったり、「情報爆弾」(ポール・ヴィリリオ)であったりする。ヴィリリオのいう「情報爆弾」が人間のうちに与えるヴァーチャル効果は、リアルなものに対する感覚,とりわけ苦しみや暴力の現実に対する感覚をも圧殺してしまう。
警告を発する声はすでに存在するし、ソフトなトレンドの変化を宣伝するものもいろいろある。『スロー・ダウン・ユア・ライフ』や『世界のテンポ』といったタイトルのアドバイス的実用書もあれば、ゆっくりすることの再発見のためのインターネット・サイト『時間遅滞協会』(www.zeitverein.com)や『ナマケモノ・クラブ』(www.slothclub.or.)、あるいは『スローライフ』(www.slow-life.net)といったものもある。『スローシテイーズ』(www.cittaslow.net)や『スローフード』(www.slowfood.de)のようなサイトももてはやされていて、巧妙なマーケティング戦略を追求している。交通に落ち着きがあり、環境に配慮した施策をおこなう(イタリァやその他の)小都市では、「急がば回れ」も一般的であるし、「ゆっくりとした」地方の食堂では健康的な、オーガニック生産物による料理を楽しむ雰囲気もある。それで結構。こういったコンセプトは、その商業主義的な観点を越えて、ヴィリリオが「知覚の新しい倫理」と言い表わしているものに相応する。 |