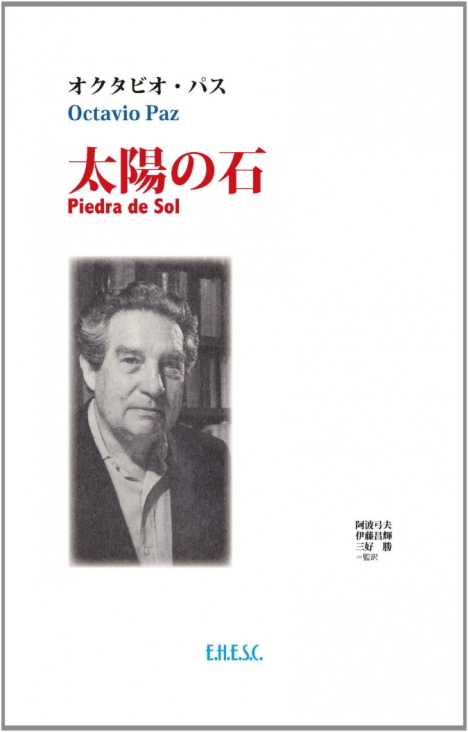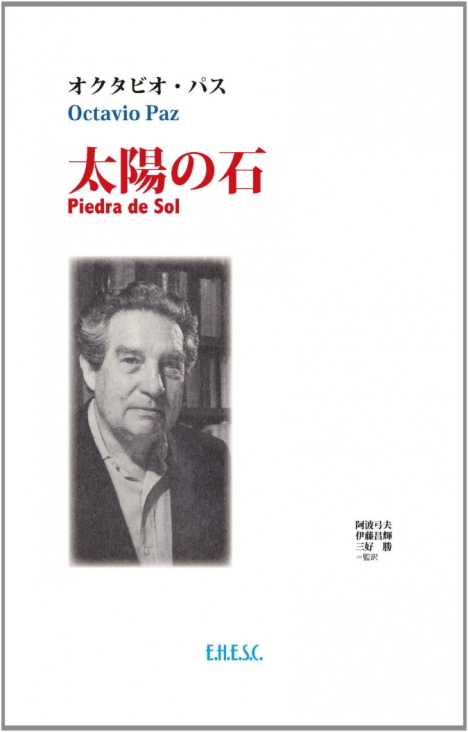「第二次世界大戦後、ラテンアメリカの人たちは再び日本文学に関心を寄せるようになった。その証拠にわれわれの『奥の細道』、それに雑誌『Sur』の日本近代文学特集号およびKazuya Sakaiの翻訳がある。彼は孤高の、しかし百人力の翻訳家である。」
その関心について、パスはこう語る。「日本は単なる芸術的、文化的好奇心の対象ではなくなっている。より良いとか悪いということではなく、われわれとは異なる世界観なのである(あった?)。つまり、鏡ではなく、人間について別なイメージ、別な存在の可能性を見せてくれる窓なのである」。
この短文以上に、日本文学を読む理由を教えてくれるものを私は知らない。日本文化は鏡ではなく、異なる世界への窓であり、その世界は我々の西洋世界より良いとも悪いともいうものではない、とパスは述べる。この別世界を知ることは喜びであり、心を豊かにする。個人的な話だが、満八十歳を迎え、日本文学に六十年の歳月を捧げたことを私は後悔していない。 |