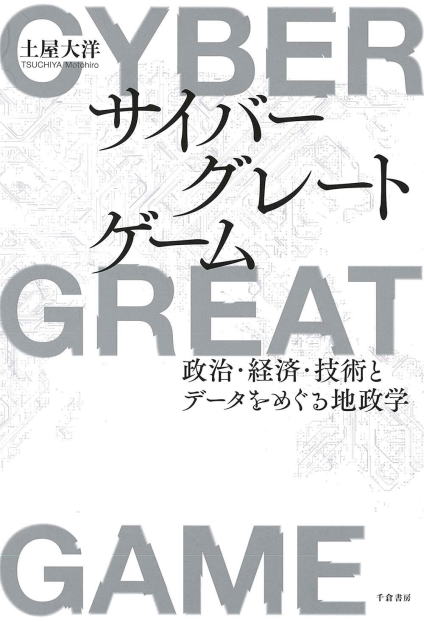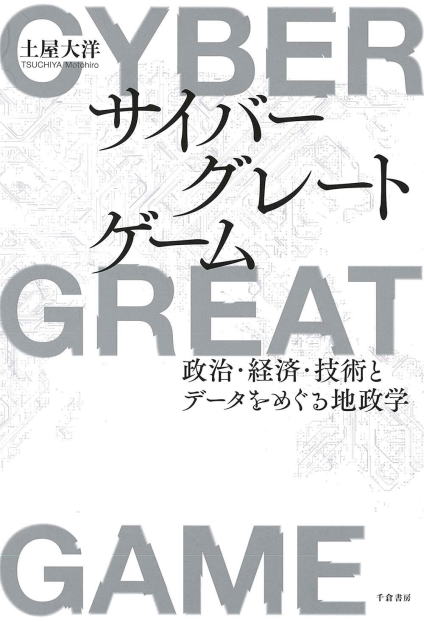インターネットはl960年代から開発が始められ、1990年代から一般に普及するようになったが、インターネットとサイバースペースは同じものとしてはとらえられない。インターネットは定義上、ネットワークのネットワークであり、各種のコンピュータ・ネットワークが相互に接続されたものである。しかし、インターネットには接続されていないものの、同様の技術を使ったサイバーシステムがその外に広がってきている。例えば、道路や航空路などの交通管制を担うシステムにも同様のコンピュータやネットワークが使われているが、通常はインターネットには接続されない閉鎖システムになっている。原子力発電所などの重要インフラストラクチャもそうである。社会機能の多くがそうしたサイバーシステムに依存するようになっていることから、サイバースペースの重要性は高まってきた。
サイバースペースのガバナンスは、1990年代までは民間の技術者たちによって担われていた。技術標準を検討するIETF(lnternet Enginee・ing TaskF・rce)、インターネットの住所機能を担うICANN(lnternet C・rp・rati・n石・・Assigned Names and Numbers)などの多くの非営利組織が自律・分散・協調的なガバナンスに参加していた。しかし、インターネットが社会的な重要性を高める2000年頃から、各国政府が介入してくるようになった。
特に、近年は、サイバースペースを介し、各種の犯罪、スパイ活動、攻撃が行われるようになり、そのガバナンスが重要性を増してきている。2007年のエストニアに対する分散型サービス拒否(DDoS)攻撃の発生は、国家間の争いにサイバー的な手法が使われることを示した先例になった。2010年にはイランの核施設に対しサイバー攻撃が行われ、サイバー的な手法が物理的な施設に影響を及ぼすことができることを示した。2014年のソニー・ピクチャーズ・エンターテインメント社に対するサイバー攻撃は北朝鮮が行ったと断定されており、一国家が一企業を狙い撃ちすることも示された。さらに、2016年の米国大統領選挙ではロシアがノ・ッキングやフェイク・ニュースで介入し、国際政治上の問題になった。
既存の研究では、グローバル・ガバナンスの視点からサイバースペースを捉えるものが多かった。しかし、本章では、サイバー攻撃に注目し、そのアンティシペーション(anticlpation:予期)とアトリビューション(attribution:特定)という視点から考えてみたい。その過程は、2010年をおおよその境目として、デジタル・デバイドが議論された時代と安全保障上の懸念が高まる時代としてとらえることができる。そして、近年のサイバーセキュリティ問題の悪化に対してアンティシペーションとアトリビューションが別の抑止の形につながる可能性について検討したい。 |