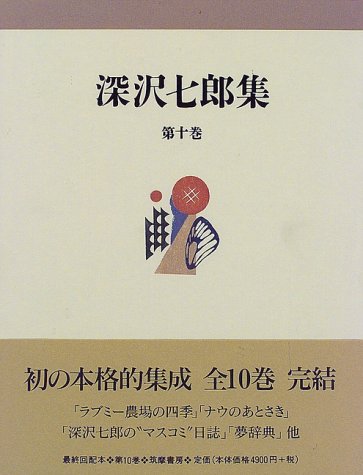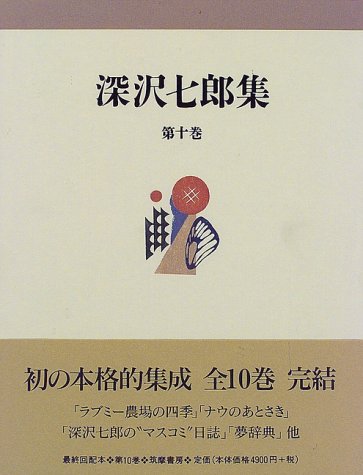|
わが友 羽仁協子
彼女は羽仁五郎氏の娘さんで、若い頃からハンガリーへ留学していた。その関係で、私の小説のハンガリー語訳をやってくれていた。いまは日本にいるが、その頃は、「ときどき日本へ帰ってきた」
という状態だった。私と彼女は気が合って、幼なじみというほど親しかった。彼女を、ほかの人に紹介するとき、私は「協子さまは、私の同級生です」と、口ぐせのように言っていた。勿論、私は彼女より三〇歳も年上なのだから、ユーモアを含んではいるが、それほど親しい仲だという紹介の意味だった。
いつだったか、そのとき、彼女と一緒にいた女性が「アナタ、それを言うのはヤメて、ヤメて、協子さまは、それを言われると背すじが寒くなって、ゾクゾク身ぶるいがするのよ」と、私は言われて「へーえ」と思った。女性は、年を余計に見られるのは冗談でも許されないという、わかりきったことさえ私はツイうっかりしてしまう。いつだったか銀座で食事をして地下鉄の階段をおりながら「こんやは、私の家に行きましょう。将来のことなど一緒に話しましょう」と言いながら私は彼女のソバに寄りそって「あなたの、お父うさんに、許可をうけて」と、彼女の肩に手をかけた。途端、彼女は犯される、犯される」と、身ぶるいをしながら逃げるように人ゴミの中に去ってしまった。
それから、彼女は十年くらい私とは音信不通になってしまった。彼女は作詞や作曲したりするから芸能人だと思っていたがカタギの女だった。半分ほんとで、半分ウソで、男と女は出来上る芸能人でなかったのが玉にキズだ。男と女は、フザけてキッスなどして、案外、それは、スバラシイ味のするものだが、私には、どーも、良家のヒトは扱いにくい。男性でも、良家のヒトはオフザケが通用しない。だから私の友だちは庶民という人だけなのだ。大学の先生、作家、とても、とても、私はその前にいるだけでも拷問されているようだ。
|