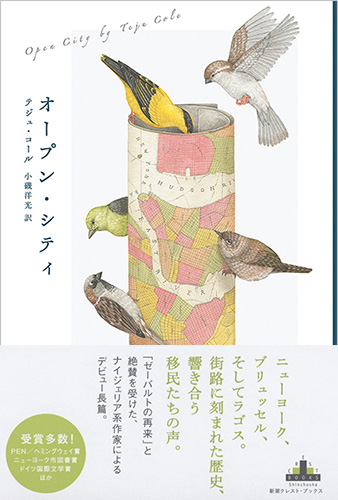
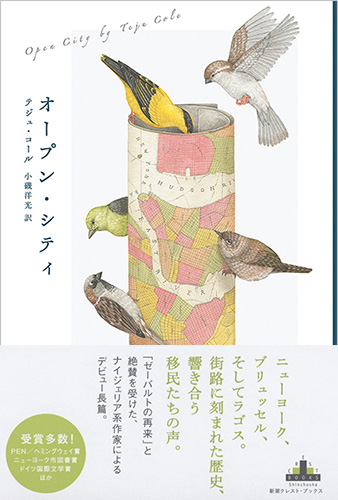
| 2021年6月2日(水) テジュ・コール『オープン・シティ』読了。 ブログ参照。 http://kohkaz.cocolog-nifty.com/monoyomi/2021/05/post-65506d.html オープン・シティ デジュ・コール マクスウェル大学 サイトウ教授 39p ウィキによれば、 マックスウェル行政大学院(Maxwell School of Citizenship and Public Affairs)は、アメリカ合衆国ニューヨーク州シラキューズにあるシラキューズ大学を構成する学校の一つ。1924年にGeorge Holmes Maxwellによって創立され、行政学、公共政策学、国際関係学を扱う。大学院は、行政学および公共政策学において高い評価を受けている。 コロンビア大学プレスビテリアン病院 23p https://ameblo.jp/onedaymanhattan/entry-10483725188.html https://sekaidr.com/clinic-list/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%A8%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%93%E3%83%86%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%B3%E7%97%85%E9%99%A2%EF%BC%88%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%83%93%E3%82%A2/ タワーレコード閉店 20p 瑕疵レコード屋のブロックバスター閉店 24p ジョン・ブルースター;画家 41p 盲目の芸術家;ミルトン、ブラインド・レモン・ジェファーソン、ボルヘス、レイ・チャールズ 42p ブラインド・レモン・ジェファーソン (Blind Lemon Jefferson 1893年9月24日 - 1929年12月19日) は、アメリカ合衆国で1920年代に演奏活動をしたブルース・シンガーである。いわゆる戦前ブルース、カントリー・ブルースの代表格のひとりとして知られる。ライトニン・ホプキンズ、T-ボーン・ウォーカーなど、のちのブルース・アーティストにも大きな影響を与えている。(ウィキ) ウォール街駅 51p ファラフェル 52p トリニティ教会 ブリュッセル旅行 98-99p 飛行機の中で引退した女性外科医に会う メイヨット博士 エジプトのアンパン一族 ヘリオポリス エドワール・ルイ・ジョゼフ・アンパン この建物は現地では「カスル・アル・バロン」 と呼ばれていて、英語では BARON’S PALACE と訳されています。バロンとは人の名ではなく男爵のことなので、本来はその男爵の名をとって「アンパン宮殿」と呼ぶべきなのでしょうが、カイロの人々は「バロン」を特定の人物をさす固有名詞のように扱ったようです。したがって ここでも「バロン宮殿」と呼ぶことにします。 その特定の人物とは、ベルギーの実業家の エドワール・ルイ・ジョゼフ・アンパン (1852-1929) で、一代にして銀行、電気、電話、鉄道、都市開発の事業で 国際的に大成功をおさめた人物です(今ならグローバル・マルチ・ベンチャー企業というところ)。パリの地下鉄建設に果たした業績のゆえに、フランス政府から男爵の爵位を贈られたのです。そのアンパン男爵が 1900年頃にエジプトの鉄道や電話網建設のためにカイロを訪れると すっかりこの地域に魅せられ、ナポレオンのあとを継ぐ エジプト愛好家となりました。 1904年にカイロ北東部の砂漠に 6,000エーカー(2,400ヘクタール)の土地を買うと、ここに新しいカイロとしての近代的な田園都市を計画し、1907年に建設を開始しました。ちょうど インドの デリーに対する ニューデリー(この6年後に建設開始)に相当する地域です。 混沌とした旧市街と対照的に、広い道路を整然と通し、建物をゆったりと配して、「ヘリオポリス」(太陽の都)と名づけました。現在はカイロの一部ですが、20世紀のカイロの都市発展にとって、ヘリオポリス地区は大きな役割を果たしました。 後にその東北端に カイロ国際空港がつくられために、外国からの訪問者は必ずこの地区を通り抜けていくので、ヘリオポリスはカイロの顔となっています。 http://www.kamit.jp/11_information/baron/baron.htm ゴルダ・メイア( Golda Meir, 1898年5月3日 - 1978年12月8日)は、イスラエルの政治家、第5代首相(在任期間1969年-1974年)であり同国初の女性首相。 サイード 112p ゴルダ・メイアは、より排外主義的な文章、特にパレスチナに関連する文章も頻繁に使用しています。「パレスチナ人のようなものはない」と彼女は言った。 「パレスチナ国家を持つ独立したパレスチナ人はいついるのか?パレスチナ人は自分をパレスチナ人と考えているパレスチナ人ではないのですか?私たちは来て、彼らを追い出し、彼らから彼らの国を取りました。彼らは存在しない」と、ゴルダ・メイアは、彼女のために存在しないパレスチナの存在について言いました。 https://voi.id/ja/memory/39359/read ベネディクト・アンダーソン 136p シャリーア ポール・ド・マン 137p マーティン・ムンカッチ 163p MUNKACSI, Martin (1898-1991) マーティン・ムンカッチは当時のハンガリー、コーロズヴァル(現在ルーマニア領)生まれ。16歳のときに家を出てブタペストで暮らすようになります。ぺンキ職人の弟子を経て地元の新聞社に就職した青年ムンカッチは詩人を夢見ていたとのこと。1921年頃からスポーツ誌「アズ・エシュト」のためにスポーツ写真を撮り始めます。その後ベルリンに移り、有力グラフ誌「ベルリナー・イルストリヒテ・ツアィトゥンク」 などの仕事を行い、ドラマチックかつ大胆なアングル、構図の写真で名声をかちえます。この時期に、欧州、アフリカ、南米を旅行し、1930年頃にはリベリアで、有名な海に駆け込む地元少年たちを撮影しています。アンリ・カルチェ=ブレッソンはこの作品に感銘を受け、「この写真を見たときに、写真は瞬間を通して永遠に到達できるかもしれないと直感した」と、ムンカッチの娘ジョーンに寄せた手紙で述べています。 1933年ムンカッチはウルシュタイン社の仕事でアメリカに渡ります。ちょうどヴォーグからハーパース・バザーに移籍し雑誌改革に取り組んでいた 編集長カーメル・スノウに起用され、はじめてファッション写真を撮影します。1933年12月号に発表された、アメリカ娘(モデルはルシール・ブロコウ)が服をなびかせながら浜を走るイメージは新時代のファッション写真の第1号となります。 彼はそれまでスタジオで制作されていたファッション写真に、動きのある自然なイメージや野外撮影を取り入れ変革をもたらしたのです。 1934年にはナチス・ドイツの抑圧から逃れてアメリカに移民。 ハーパース・バザー誌と専属契約を結び、同時期に雇われたアート・ディレクターのアレクセイ・ブロドヴィッチとともに斬新なファッション写真を次々と発表していきます。 その後、「レディース・ホーム・ジャーナル」誌などの仕事も行い、30年代、40年代のアメリカで最も高額のギャラを得る写真家といわれるようになります。1943年に心臓発作を起こし、療養期間には著作に専念する生活を送ります。戦後はファッションの移り変わりが速くなり、彼の写真は次第に時代遅れになっていきます。時代はカラー写真が全盛となりますが彼はその変化にも対応できませんでした。その後はフリーで主にコマーシャル関係の仕事を続けますが、1963年に心臓発作で亡くなりました。 彼の写真は上記のアンリ・カルチェ=ブレッソンとともに、幼少時代のリチャード・アベドンにも多大な影響を与えたことで知られています。 写真集は1951年にブロドヴィッチがデザインした写真集"Nude"が、また死後の1979年に"STYLE IN MOTION, Munkacsi Photographs of 20s,30s, And 40s"などが刊行されています。 ヨルバ人(Yoruba)は、アフリカの民族。主にナイジェリア南西部に居住し、西アフリカ最大の民族集団のひとつである。ナイジェリアにおいては、ハウサ人・イボ人とともにナイジェリアの三大民族のひとつとなっている。 168p 農夫ピアズの幻想 190p W・ラングランド作 《原題The Vision of Piers the Plowman》中世イギリスの宗教詩。ラングランドの作品とされる。50以上の写本が現存し、1370年頃、1380年頃、1385年頃の3種の稿本に大別することができる。 【抜き書き】国王は言った、「[…]しかしながら、〈道理〉よ、お前はここからすぐに立ち去ってしまってはならない。予の生きている限り、お前を手放したくないのだから。」/〈道理〉は答えて、「私はいつまでも陛下のおそばに居るつもりでおります。そこで、〈良心〉をどうぞ陛下の助言者として加えていただきたく、これだけを伏してお願い申し上げます。」/国王は言った、「よろしい、認めよう。彼がしくじることは、神かけて断じてありえない。予がこの世に生きている限り、われわれは協力して生きて行こうではないか。」(第四歌p63-4) 【抜き書き】「彼らみんなを守る城の司令官(城代)は、とりわけ賢明な騎士で、〈良心〉卿と呼ばれ、彼は最初の妻との間に五人の美しい息子をもうけた。??〈よく見よ〉卿、〈よく言え〉卿、上品な〈よく聞け〉卿、非常に力の強い男である〈お前の手でよく働け〉卿、そして〈ゴッドフレイ・よく歩け〉卿で、いずれも有力な貴族である。これらの六名がこの城を守るために配置されている。かの女性を保護するよう、これらの賢い人たちは命令を受けている、〈自然〉が出てくるか、人をやって自らが彼女を守るまでは。」(第十歌p116-7) 【抜き書き】「そのとき、〈善行〉は悪徳を攻め滅ぼす公爵となり、魂を救い出すので、罪はお前の心臓の中に腰をすえ、休息し、根づく力がない。それがつまり神を畏怖することであり、〈善行〉がそうさせるのだ。神を畏れることが善良のはじまりである。ソロモンは真実の物語としてそう言っている。『主を畏れることは知恵の初め。』(詩編 111の10)畏れのために人はより善いことをする。畏れは偉大な主人であるので、そのため人を柔和にし、しゃべり方も穏やかにし、あらゆる種類の学生を学校で勉強するように仕向ける。」(第十歌p119) ディストピア 215p ナッツ 216p nut 変わり者 ラスカー賞 221p らすかーしょう Lasker Awards ラスカー財団の創始者であり慈善家でもあったラスカー夫妻(アルバートAlbert Davis Lasker(1880―1952)とメアリーMary Woodard Lasker(1901―1994))によって1945年に創設された医学賞。基礎医学および臨床医学に貢献した研究者らに与えられるアメリカの権威ある医学賞である。この賞の受賞者のなかからノーベル医学生理学賞の受賞者が出ることも多く「アメリカのノーベル医学生理学賞」ともよばれる。基礎医学研究賞、臨床医学研究賞、公益事業賞および医学特別業績賞の種類がある。 基礎医学研究賞Albert Lasker Basic Medical Research Awardは、障害や死の原因に関する基礎的な発見をした研究者らを対象とする。日本人では、細胞の遺伝子変異によって癌(がん)が発生することを明らかにした花房秀三郎(はなふさひでさぶろう)(1982)、生体組織を攻撃する抗原に対する抗体発現の仕組みを遺伝子構成段階で解明した利根川進(とねがわすすむ)(1987)、生体内のあらゆる細胞へ分化できるiPS細胞を樹立させた山中伸弥(やまなかしんや)(2009)、生体内の細胞異常の修復機構を解明した森和俊(1958― )(2014)らの受賞者がいる。 臨床医学研究賞Lasker-DeBakey Clinical Medical Research Awardは、治療法の改善など臨床医学研究に貢献した研究者を対象に与えられる。日本人の受賞者には、心筋梗塞(こうそく)などの予防にかかわる脂質異常症の治療薬として有用なスタチンを発見した遠藤章(1933― )(2008)がいる。 公益事業賞Lasker-Bloomberg Public Service Awardは、医療や保健にかかわる公益事業に社会的貢献をした者に与えられる。2000年からラスカーの妻メアリーの名を冠していたが、2011年に現名称に改称された。医学特別業績賞Lasker-Koshland Special Achievement Award in Medical Scienceには、生化学研究にとくに業績のあったコシュランドDaniel E. Koshland Jr.(1920―2007)の名が加えられている。 ツィクロンB(独: Zyklon B, 英: Cyclon B)とは、ドイツのシアン化合物系の殺虫剤の商標である。しかし第二次世界大戦中にナチス・ドイツによるホロコーストで、強制収容所のガス室で毒ガスとして用いられたと言われている。現在は農薬としては用いられておらず、その他の使用(シラミ除去など)に対してもユダヤ人団体からの抗議で商用に至っていない。 片仮名転記の際には「チクロンB」と表記される場合もあり、英語読みで「サイクロンB」とも言うが、全て同じ薬剤である。 245p クロイターズ美術館 252p パラケルスス(スイスドイツ語:Paracelsus)こと本名:テオフラストゥス・(フォン)・ホーエンハイム(Theophrastus (von) Hohenheim[4][5], 1493年11月10日または12月17日 - 1541年9月24日)は、スイスアインジーデルン(英語版)出身の医師、化学者、錬金術師、神秘思想家。悪魔使いであったという伝承もあるが、根拠はない。後世ではフィリップス・アウレオールス・テオフラストゥス・ボンバストゥス・フォン・ホーエンハイム[6][7](Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim)という長大な名が本名として広まったが、存命中一度も使われていない[4]。バーゼル大学で医学を講じた1年間を例外に、生涯のほとんどを放浪して過ごした[8]。 253p ガイウス・ムキウス・スカエウォラ(ラテン語: Gaius Mucius Scaevola)は、共和政ローマ初期の伝説的な人物。一説によると元々のコグノーメンはコルドゥス(Cordus)であった[1]。若者らしい勇気を示し、追放されたタルクィニウス・スペルブスの王政復古を目論むエトルリア王ラルス・ポルセンナを退けた。 ローマが王政から共和政に移行したばかりの時代、追放された王タルクィニウスはいまだ健在で、エトルリアの王たちと手を組んでローマへの復帰を企んでいた。タルクィニウスの盟友ポルセンナは軍を率いる事に優れ、ローマ軍はたびたび苦難に陥る。そしてポルセンナはローマを包囲するにまで至った(ローマ包囲戦 (紀元前508年))[2]。 そして、その時に一人のローマ市民ガイウス・ムキウスは闇夜に隠れて城外のポルセンナを暗殺しようと企み、元老院の許可を得た。しかしポルセンナの顔を知らないムキウスは王の隣にいた秘書を殺害してしまい、囚われの身となったムキウスがポルセンナに詰問される。この時のムキウスの台詞は後のローマでは語り草となった。曰く: 私はガイウス・ムキウス、ローマ市民だ。私は敵を殺しにやってきたあなた方の敵である。また敵を殺す覚悟と同様、私には死ぬ覚悟もできている。我々ローマ人は行動を起こすときには勇気をもって攻撃し、傷を受けるのも勇気を持って甘んじるであろう。同じ覚悟を持った若者の列が私の後に続いている。その者たちがいつでもお前の首を狙っているぞ。これはそうした者たちとお前一人の戦いだ。 これを聞いたポルセンナは恐れかつ怒り、ムキウスの身体を火であぶって拷問することとした。ムキウスは従容としてこれを受け入れるどころか、ポルセンナよりも先に松明をつかみ右手に押し当てて、痛みの表情を出さずに炎が右手を焦がすままに耐えたという[3]。 この勇気を目にしてポルセンナは彼を解放し、またこのようなローマ人の勇猛さを前にポルセンナはローマと和議を結んだ。そして焼けただれた右手が使えなくなったため、彼はのちにスカエウォラ(Scaevola、「左手の」という意)と呼ばれるようになったという。 262p
|