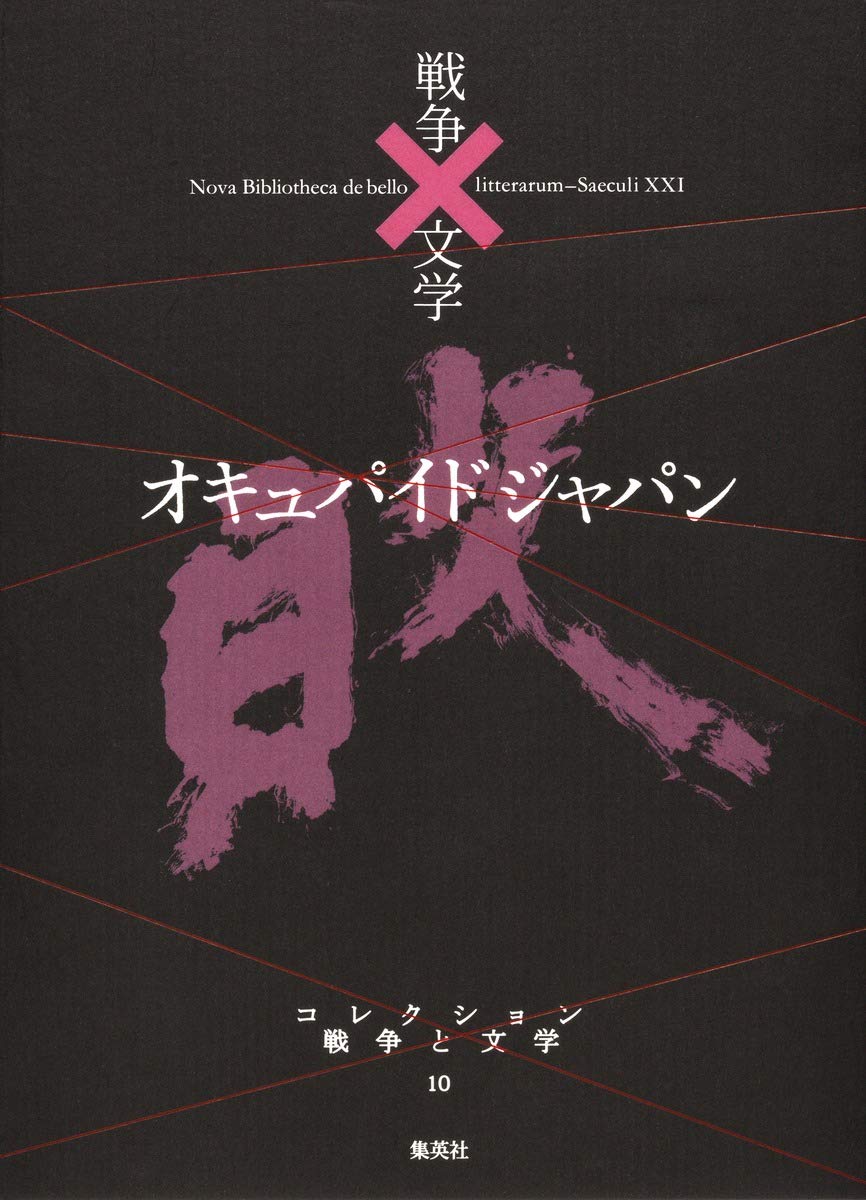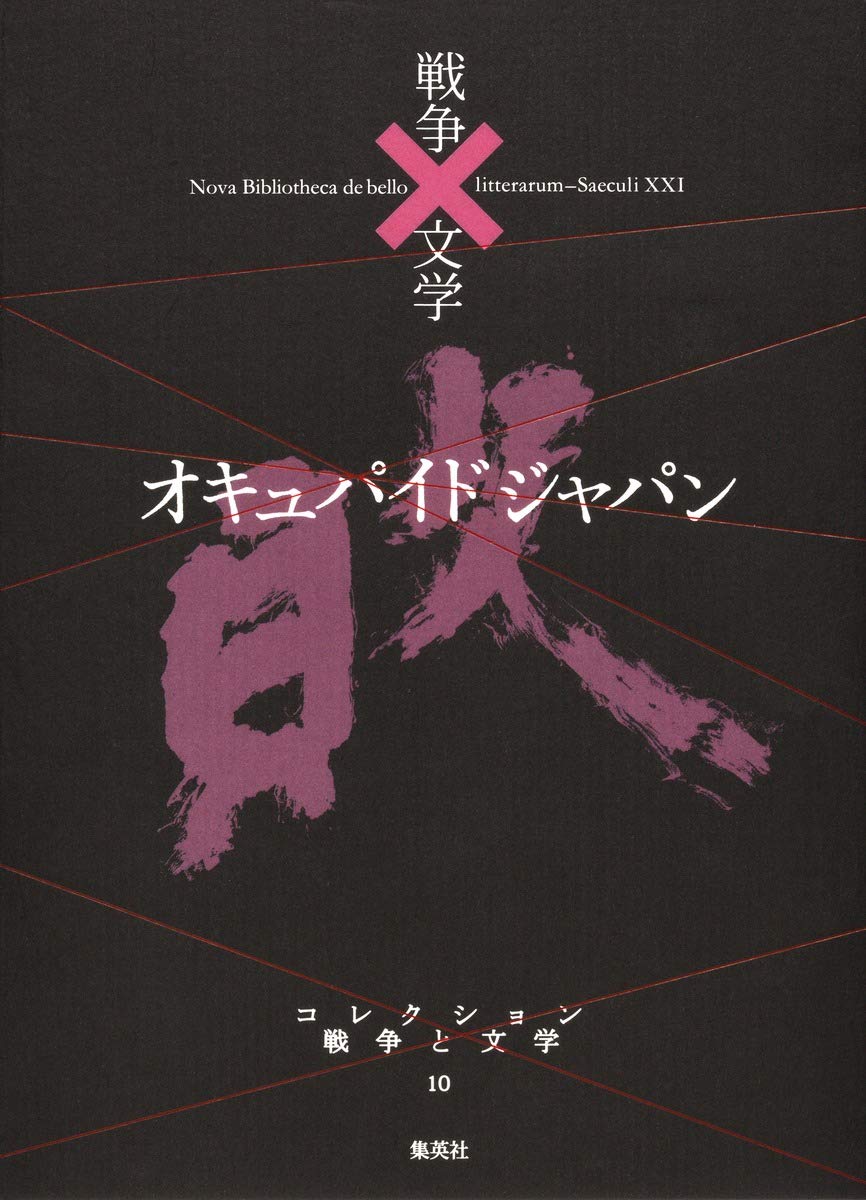2021年5月3日(月)
『コレクション 戦争×文学 10 オキュパイド ジャパン』読了。
ブログ参照
http://kohkaz.cocolog-nifty.com/monoyomi/2021/04/post-1edca9.html
http://kohkaz.cocolog-nifty.com/monoyomi/2021/04/post-4885ef.html
http://kohkaz.cocolog-nifty.com/monoyomi/2021/05/post-fdfff7.html
解説 成田隆一
占領は、戦争の延長に位置している。アジア太平洋戦争において、日本はポツダム宣言を受諾し降伏したため、アメリカを中心とした連合国軍による占領統治がおこなわれた。マッカーサーを最高司令官とするGHQ(連合国軍最高司令官総司令部)が設置され、日本本土では日本政府に指令を出す間接統治がなされた。また、沖縄など南西諸島、千島・南樺太など北方領域、さらに小笠原諸島では直接軍政が敷かれた。
占領下の「日本人」にとっては、戦時(大日本帝国)の整理と、戦後(占領)の受容という二重の事態が出現することになった。戦争が終結する一方、これまで信じていた価値観が崩壊するとともに、「敵」であった勢力が権力を持ち統治するという事態が出現し、力関係が変わり、解体と創出が目の前で進行していく。占領期は、人びとにとって屈曲し、単純ではない意識がもたらされる時代となる。他方、占領軍にとっても、 ダワーは、占領期を「めったにない」「重みのある」瞬間としたが、その占領は長いあいだ、なかなか正面から捉えられなかった。文学作品においても、占領を素材とするより、あらためてアジア太平洋戦争をたどり直し、描き直すものが多かった。背後には占領軍による検閲があり、占領軍とその政策への批判が許されていなかったことがある。戦後には、戦後の不自由さがあった。しかし、同時に、(「日本人」にとっては)占領という事態を見たくないという意識もあったろう。
本巻では、占領下における目の前の現状-焼け跡や闇市の状況や、占領という事態に向き合った作品を収録している。敗戦を契機にした衝撃は本全集第9巻「さまざまな8・15」に譲り、本巻では日常としての戦後とその意味を重視した。ひとつの柱は、占領時代の光景である。焼け跡・闇市の光景といってもよい。〈Ⅰ〉にはそうした作品群を収めた。
ふたつ目の柱は、占領そのものである。〈n>には、占領軍に対する屈折した思いを描く作品を配し、 ふたつ目には、占領下で戦争責任を追及した作品を収録した。さらに、三つ目の柱として、戦争の記憶をたて、〈Ⅳ〉には、戦争がどのように人びとの深層に記憶として存在しているかを扱かった作品群を収めている。
2
〈1〉に収録した作品のうち、三編までもが、物語内の時間を書き留めている。「昭和二十年十月十六日の事である」と記した、志賀直哉「灰色の月」(一九四六年)では、「私」は電車内の乗客を観察しコト頃とは人の気持も大分変って来た」と「気持よく」思うが、一転して「暗澹たる気持」ともなる。「私」はよりかかって来た、一七、八歳くらいの「少年工」の身体を肩で突き返す。「私の気持を全く裏切った動作」だったが、少年工の体重が軽く、「抵抗」が余りに少なかったという。その少年工は、「どうでも、かまわねえや」と投げやりであり、志賀は敗戦ー占領のなかの無気力を暗示していく。
石川淳「焼跡のイエス」(一九四六年)と、椎名麟三「深夜の酒宴」(一九四七年)は、生存ぎりぎりのところに追い詰められた状況での意識や行為を描き、人間存在の意味を追求する作品となっている。
石川淳「焼跡のイエス」は「昭和二十一年七月の晦日」 上野のガード下の、ざわめかしい光景を発端とする。「ポロとデキモノとウミとおそらくシラミとのかたまり」の「少年」が、いきなり女の足に抱きつく。「わたし」は、この少年がイエスで、行為には「神学的意味」がふくまれていると思う。
しかし、別の日に広い場所で見ると、ただの存在にも見えたが、少年は「わたし」をも襲う。それを押さえつけたときに、「わたし」は「苦患にみちたナザレのイエスの、生きた顔」を見る。少年がイエスであり、キリストであったとあらためて思う。
また、椎名麟三「深夜の酒宴」は、かつて共産党員で、「刑務所の病棟」にいた経歴を持つ「僕」の手記とされている。「倉庫」を改造したアパートの隣人たちの来歴が記されるが、それぞれ貧困や「深い絶望的な気分」を抱え込んでいる。
客商売をしている「深尾加代」もまた、「未来への漠然とした不安」があり、その不安に「漠然」と堪えるが、「現実に押し流されているだけ」とも記される。なによりも、「露店の売子」をしている「僕」が、「自分自身が重かった。そして人間が重かった」とされる。関係性を意味づけながら生きているが、アパートを出ていくように言われた「僕」と加代が別れに酒を飲む。ここでも受身の姿勢であり、理不尽さや飢えにも堪える……。
石川も、椎名も、慢性的な飢えのなかで、人間存在の意味を考えさせるが、山田風太郎「黒衣の聖母」
(一九五一年)も、読み物仕立てながら、同様の読後感をもたらす作品である。発端は「昭和二十一年五月十一日の夜」。(死ぬはずであったが「南の島」から戻った)「私」が、(空襲で死んだ)恋人との思い出にふけるとき、「三田鏡子」と出会う。鏡子は、医学生であり子を持つ母親で、娼婦をしていた。性的関係を重ねるなか、「私」は「官能の涙にむせぶ淫売婦に堕した聖母の顔」を見ようとして、かえって「恐ろしい、欄れたような醜怪な顔」を見てしまう。そして、彼女の首を絞めてしまうのだが……。男の身勝手さの論理に見える点が、最後のどんでん返しの伏線になっている。
石川、椎名、山田らの作品は、「人間の生理」としての「肉体」に焦点を当てるとともに、「すでに昨日がなくまた明日もない」(石川淳)精神風景を描き、〈いま〉が何にもまして優先される焼け跡の風景と、それゆえの実存の探求が重ね合わされている。
これに対し、占領解除後の一九五二年に書かれた、田宮虎彦「異端の子」は、占領という経験によっても変わらない戦後に対する批判が見られる。舞台となるのは、ある地域の村。ここに一家で疎開している「良一」少年がいじめに遭う。「土着の百姓や漁師たちが、他処のものを毛嫌いする」という「封建遺習」であった。良一は、「他処もの」であることに加え、腰椎カリエスで「両脚が不自由」であるため、「仲間はずれ」にされていた。
加えて、「宮様」が来たときに、一家は「日の丸」をたてず、「道普請」にも出なかったという理由で、さらにひどい仕打ちを受ける 「日本人の家に、日の丸の旗がなくて、それでも、われたちゃ日本人か」。
姉の「美津子」も、性的な仕打ちを含め、これまたひどいいじめに遭う。村における旧態依然とした様相を、告発的に描く作品である。
他方、吉行淳之介「廃墟の眺め」(一九六七年)は、新しいビルや家屋が建ちはじめるころを物語の発端とするが、戦後そのものに批判的な視線が向けられる。ある日、「私」は「花野美枝子」と出会い、酒を飲み接吻をする。一六年ののち、「私」は彼女が「満州からの引揚者」であり、その地で「無数の集団暴行」
がおこなわれたことを思い出す。そして、「その背景に、廃嘘が重なる」。敗戦が一六年のかなたにあること、また、戦争への思いをかかえた人びとがいたこと(いること)が、象徴としての「廃墟」を介して描き出される。
また、野坂昭如「あ・日本大疹癬」(一九六八年)も、敗戦直後の飢餓と貧困を持ち出し、作品発表時は高度経済成長のただなかにあった戦後の日本を批判する。「空腹」で「うまいもん食うたいう記憶」も「満腹感」も味わったことがない「昭和二十二年初夏の頃」の話である。「野荒し」に出かけた際、ひとりの仲間(朝鮮人の「チビ」)が溺死してしまう。悔みに行ったとき、チビが疥癬であったことを知る。「俺」もまた、疥癬持ちだったが、その後一気に症状が広がる。風呂屋で出会った、手がなかったり、足が悪かったり、ケロイドがあったりする「傷疲軍人」たち!これまた戦後の光景であるがーに、肉を食べるとよくなると言われ、むく犬を貰ってきて殺して食べ、疥癬が無くなったという話である。飽食の時代への異議申し立てが、焼け跡の物語を持ち出しながらなされていく。
吉行も野坂も、戦後の〈いま〉と敗戦後とを切り離さずにいる。この点は、田中小実昌も同様である。
田中小実昌「ミミのこと」(一九七一年)は、個人の次元で、野坂の問題意識を受けとめた小説を提供した。一二歳の「ぼく」(-ー「ハッピイさん」)は、BCOF(英連邦軍)の「食堂ボーイ」であったが、聾唖者の「ミミ」と知りあう。「ぼく」は、病院船で「復員」しており、「ハッピイである理由なんか、なんにもありゃしない」という気持ちを抱いている。年長の仲間に、
「こうやって、アメリカやイギリスやオーストラリアの兵隊がきて、われわれがコキつかわれていて、戦争に負けたのがわからないというのかね。あんたは日本の国が戦争に負けてもかなしくないのか?」
と問われ、「あんた、祖国ってものを考えたことがあるのかい?」とさらに尋ねられる。占領期の記憶に対する批評がなされる個所だが、話はさらに展開する。「ぼく」は、食堂をクビになるが、自分を「軽べつ」
はしなかった。しかし、奇蹟のようにして再会したミミを失ってしまう。「もう、ミミにはあえまい。だいいち、ぼくはもうハッピイさんではない」。
だが、一〇年くらい前から、「女房ができ、家ができ、子供ができて」「ぼくは、デカダンなくらしをしているのではないか」と思うー「自分を軽べつするというのが、デカダンのはじまりなのではないか」。
田中小実昌「ミミのこと」は、回想としてこれらのことが語られるのだが、〈いま〉のデカダンが強く描かれる作品となっている。ちなみに、GHQでの労働を描く小説は少なくないが、BCOFにかかわる作品はまれである。
こうして吉行・野坂・田中の作品は、占領-敗戦後の光景を描きながら、戦後の「繁栄」を問う作品群となった。
今回収録した川柳は、ある断面を切り取り世相を浮き彫りにするが、占領と占領下の「日本人」への批判的な姿勢をはっきりとうかがいうる。
3
占領は、「異民族」による統治として、人びとに屈折した感情をもたらした。非軍国化・民主化には同意しながらも、「異民族」が実施することへの割り切れなさである。しかも、時間が経つにつれ、占領軍は非軍国化・民主化を放棄し、権力としてのみ存在するようになる。そのことを占領下には、直裁に語ることができなかった。
そのなかで、前衛党としての日本共産党に関与していた中野重治や西野辰吉は、きっばりとした批判をする。中野重治「おどる男」(一九四九年)は、「だれもかれも不服そうな不機嫌な顔」をするが、それを「外」へ出したり、「爆発」させられない「屈辱感のようなもの」がつきまとうことをいう。「心が快活に、外へ外へと、本質的なものへ本質的なものへとはたらいて行かぬときの顔つき」を指摘する。
また、西野辰吉「C町でのノート」(一九五四年)は、占領中の事件を通して、なおも続くアメリカ軍駐留の問題性を描き出す。ひとりの青年がC町のアメリカ空軍基地で、日本人警備員(「岡田和政」)に、カービン銃で射殺された事件をめぐる小説である。警備員は威嚇射撃のつもりだったが、実際には基地外であったため、アメリカ軍の治外法権は及ばない。日米が事件をどう処理するか、「私」による調査報告の体裁をとって述べられていく。
基地で雇われた日本人たちには、「日本の警察や、日本の法律による裁判」はまったく意識になかったことや、逆に警察の内部ではアメリカ軍に対する批判があったことなどが明らかにされると同時に、C町ではこの事件に「おそろしく無関心」だったことも記される 「ひとびとはしだいに恐怖や不安に無感覚になり、殺されてもしようがないのだと思いこむ」。そして、その「意識」は、「いっぽうに殺してもいいという考え」をなりたたせていた、とするのである。
反米意識を前面に出した小説であるとともに、「日本人」たちの「隷属の意識」を抉り出す小説でもあったi「農村の平凡な一人の青年を、同胞をうち殺す任務でカービン銃をもたせて立たせておいたものに、検事は一言もふれることができなかった」。
また、内田百聞「爆撃調査団」(一九五四年)は、占領軍に呼び出しを受ける主人公の話である 一九四五年秋のことで、「その時分の事だから、亜米利加がそう云って来たなら止むを得ないと観念した」。「向うの云う事」は解るが、「私の答える事」は「よく通じないらしい」。また、彼らは「私」を出口まで送ってくるが、「礼」をつくしたのではなく、館内にいるあいだ「目を離さない」ためと解釈し、占領という事態が被占領者の「日本人」にとって、非対称的な関係にほかならないことをいう。
さらに、(〈W〉の最後においたが)吉本隆明二九四九年冬」は、「一九四五年冬ころの/ひとつのへいわ」と対比し、占領のもとでの「荒涼と過誤」を語る。吉本は、戦時下と通ずる「暗さ」を見据えているが、こうしたかたちで占領下の出来事が語り出された。
他方、占領下に青春を送った安岡章太郎、大江健三郎、豊川善一の作品世界もまた、屈曲している。彼らは、政治そのものではなく、性的なことを介しながら占領を描いて見せる。
安岡章太郎「ガラスの靴」(一九五一年)は、学生で「N猟銃店の夜番」の「僕」が主人公である。アメリカ軍軍医「クレイゴー中佐」の家で、メイドの「悦子」と知りあう。中佐夫妻の留守に、ふたりでその家を使用するが、豊富な食料(ジェロ・パイ、クラッカー、ミルク……)がある。
突然帰って来た中佐に対し、「僕」は「躊躇しそうになる自分の心を、強いてふみにじりながら」「グウド・モオニング」と呼びかけるが、中佐は返辞もしない 「ジロリと僕を見た。それだけで、僕の敗北だった」。「僕」は恥じ、「恐ろしさ」に襲われ、駆け出し逃げるが、その「云いようのない屈辱感と自己嫌悪」が書き留められる。
この被占領者の屈辱感は、喪失感を伴う現実にも直面する。悦子との関係がうまくいかず、
「放っておけば手のとどかぬ距離にまで、はなれてしまうのかもしれない。と云って、いま僕が声をかけるとすれば、それは自分の手で彼女とのつながりを断ち切ることにしかならないではないか」
と寓意的に記される。
豊川善一「サーチライト」(一九五六年)は、「与那嶺信吉」が三年前の夏、一六歳のときに遭った「実にくやしい屈辱の思い」を綴り、さらに占領下の心性の暗部へと入り込む。信吉はアメリカ軍人宅のハウスボーイであったが、ある日、「黒人」に犯されたのである。「男どうしのことながら死んでしまいたいほど恥かしく」、「性の倒錯のなかで非力に踏みにじられた〈少年〉」と、豊川は書きつける。
占領者・アメリカ/被占領者・沖縄の関係がセクシュアリティを介して提示され、権力の非対称性が抉り出される。男性による男性への強姦によって、傷つけられた男性性を表すのだが、占領下の人びとの心性がこのようなかたちで露わにされる。
さらに豊川は「それが奇妙にも信吉の欲望の対象ともなってしまっている」とも書きくわえる。信吉が性を売ることが暗示され、実に衝撃的に占領の事態を描いた小説である。「サーチライト」は、占領のアメリ力軍によって発禁処分をうけ、掲載誌「琉大文学」は回収された。豊川は、地名をカタカナで表記し、ひらがなを多用した文体や、英語を交えたはなしことばも使用している。
大江健三郎「人間の羊」(一九五八年)もまた、同様に占領下の屈辱の心持ちを描く小説である。「僕」が、「郊外のキャンプへ帰る酔った外国兵」とバスで乗り合わせる。「外国兵」の連れである「酔っている女」が彼らから離れて「僕」に寄ってくるが、「僕」が女の腕を振り払ったときにバスが傾き、女は床に投げ出されてしまう。怒った外国兵は、「僕」の尻をむき出しにして手のひらでたたくー「羊撃ち、羊撃ち、パン パン」。他の日本人乗客もつれてこられて同様の目に遭い、「焼けつく羞恥」を感じる。
とともに、日本人のなかで、「羊」にされたものたちと、されなかったものたちの差異が生ずる。「羊」にされなかった「教員」が、「人間に対してすることじゃない」と正論をいう(のちには、「僕らが黙って見ていたことも非常にいけなかった。無気力にうけいれてしまう態度は棄てるべきです」ともいいたてる)。
そして、交々いまさらのように「怒りにみちた声」をあげる。「羊たち」は、といえば「柔順にうなだれ」
黙って彼らの言葉を浴びていた。ここでも羞恥と屈辱を受け、二度目の「羊」となるが、教員は、誰かが「犠牲になる必要」があるとたたみかける 「犠牲の羊になってくれ」。「僕」は「苛だちと怒り」を感じるなか、教員も告発の姿勢を崩さない……。
「少国民」として過してきた戦時が反転しての占領下の心象が、このように記された。
このとき年長の斎藤茂吉は、戦意高揚を歌ってきており、占領はやり過したい事態であった。「進駐兵」
という言い方はそのことを示している。この用語はマスコミなどでも用いられていた。
占領下での出来事として、戦争責任の追及がある。木下順二「神と人とのあいだ」(一九七〇年)は、東京裁判を描く「第-部 審判」と、BC級戦犯を扱った「第Ⅱ部 夏・南方のローマンス」の二部構成で発表されたが、本巻では第Ⅰ部を採録した。ちなみに、第Ⅱ部は、雑誌の初出以降、単行本、著作集と収録のたびごとに、大幅に修正が加えられたが、第Ⅰ部はそのような修正はなされていない。
第Ⅰ部は三幕の法廷劇で、東京裁判が内包する三つの問題点が提起される。冒頭、裁判官の忌避が議論される場面で始まるが、法廷の管轄権をめぐる議論で、この法廷で可能なのは「通例の戦争犯罪のみ」を裁くことだけだと申し立てる「首席弁護人」を登場させる。実際の東京裁判の法廷記録に沿いながら、人道に対する罪、平和に対する罪は、この法廷では裁けないとの応酬があったことを取り上げ、論点を浮き彫りにする. これを第一とすると、第二は、仏印における日本軍の「残虐行為」をめぐってである。対象とされた事件には、フランス人とともに、ヴィエトナム人の「虐殺死体」があったー殺されたフランス人は、ヴィエトナム人と行動をともにしていたドゥ・ゴール派ゲリラではないかという可能性から、ドゥ・ゴール派とヴィシー派の対抗、およびホー・チ・ミンによる独立運動という構図を提示し、ナチスが負けた戦後は身を隠してしまったヴィシー派の存在を認識させる。
第三は、ケロッグ・ブリアン条約、今日いうところのパリ不戦条約をめぐる論点である。同条約が、戦勝国も含む多くの国々によって無視-侵犯されてきた点は、東京裁判で「泥棒が泥棒を裁く」ことを意味するとした。同様に違反しながら、一方は訴追され、一方が訴追する矛盾を突くのである。
さらに、大国の検察官の認識が、自国の立場の弁証となっている点への批判もなされる。占領下に、戦勝国によってなされた東京裁判のはらむ問題点に、木下は接近していく。東京裁判批判が、ともすれば単純な日本無罪論となり、戦争責任の追及をうやむやにしかねないなか、木下は日本を裁く連合国の立場を問うことを通じ、第二次世界大戦の総体を問題化する姿勢を表明している。
大原富枝「こだまとの対話」(一九五七年)は、BC級戦犯にかかわる作品である。「宇ど」(「秋山宇之助」)は、戦犯であった「須山」(上官だった海軍中尉)の仮釈放を迎えに行く。宇どは「小さい砲弾の破片」を身体にとどめるとともに、「A島で自分が殺した男」への順罪感がある。須山と一緒に、死体を海に沈めたのである。他方、須山は、二人のB29の乗員を斬り殺したことで戦犯となっていた。
宇どは「羞恥」と「やましさ」のため、「異常さ」を示すが、仮釈放された須山の側も「屈辱的」な感情からまぬがれえない。「本質的なおかしさの原因」は「日本の基盤にある」と、大原は戦後批判の視点を見せた。
占領と戦争責任追及という次元の異なることが、重ね合わされ実施されたことによる矛盾と問題点が、それぞれ記された。
4
占領が終わり、戦後が進行するなかで、戦争は次第に記憶の領域に入っていく。戦後の日常のなかでの戦争の記憶を描く作品が、一九六〇年代頃から提供されてくる。いずれも、戦後の現状との緊張関係から、戦争の記憶が想起されてくる状況が記される。
遠藤周作「松葉杖の男」(一九五八年)は、神経科の医者「菅」が、中学事務員の「加藤昌吉」(一九二四年生まれの三四歳。「人生の若さをあの戦争ですりへらした世代」)を診察するなかで明らかになった戦争の記憶である。加藤は、脱力感や足の硬直で松葉杖をついているー「なにかに怯え、なにかを怖れている」。
「中支の小さな部落」でスパイ嫌疑がかけられた「若い男」を刺殺し、その母に「怖ろしい目」で睨まれたことが原因であった。
遠藤が、記憶を扱うに際し、精神分析医を設定したところが興味深い。そして、その菅もまた、「悪」にたいする苦い諦め1無力感と敗北感を持つ。「だが諦めはせん」との決意を、遠藤は菅に述べさせている。
城山三郎「爆音」(一九五九年)は、理髪店主「峰岸光三」が、飛行基地の誘致をめぐる町会議員選挙のあと、戦前の航空法規を唱えながら自殺した話である。光三は爆音がすると、手が震え出すー「爆音の聞えぬところへ行きたい」。が、その実、光三の自殺には「村井中尉の幻」がかかわっていた。戦争中、横暴な村井に対し、事故を装った計画を実行し、墜落死させたのである。光三を脅かすものは「大編隊の爆音」
ではなく、「光三自身の手を下して殺した村井中尉機の爆音」であった。
当事者の内面に接近しようという点では、阿部昭「大いなる日」(一九六九年)も同様である。ガンにかかった「おやじ」の死に際し、あらためて「最も凡庸な軍人の一人」だった「おやじ」の軌跡を探る。級友の追悼文、戦史などでその行動を調べ、「敗戦の年の冬」警察に連れて行かれたこともふくめ、戦争と結びついた生涯であることを記す。
もっとも、「おやじ」は自ら語らず、すべては類推である。そして、その死によって「長い孤独な戦争」
が終わったとする。「場末の病院の裏口」から運び出されることは、「敗戦国の一軍人に似つかわしい光景」とした。しかし、「おやじ」が大佐という階級を有していたことを、阿部は問題化していかない。
戦時の自分と、戦後のいまを重ね合わせ描くのが、李恢成「証人のいない光景」(一九七〇年)である。
戦時中ともに「勤労奉仕」に明け暮れた樺太M国民学校時代の同級生(「矢田修」)が、敗戦直後に「帝国軍人の死骸」を見たということをめぐっての話である。
「金文浩」は、「戦時中の友人達」をあえて「ファシスト少年」といい、自らは「同化少年」であったとする。「あの頃はへんだったと思うのだ。何かにたえず凝視められているようだった」といい、自身に「卑屈さ」があったという。
いまひとり、図書館の受付係である矢田修は、兵士の死体にこだわる 「死んだ兵士の惨めな姿」は「崇高な散華」からは程遠く、「信じていたものを激しく裏切られた悲しさ」があり、「なにものかへの不信感」となっていった。自分の「無力感」や対人関係の不適応は、「兵士の記憶」と関係があるとする。
こうした矢田と金が、二四年目のいま、会う。金にしてみれば「二人だけで経験したその光景」を自分は忘れ果て、矢田が忘れかねていることに衝撃を受けるが、「同化少年が朝鮮人になるということ」も決して容易でなかったことと重ね合わせる。
「二人ともまだどこかで昔の影を動いているのだった。矢田はファシスト少年の影を、自分は同化少年の影を」
金は、矢田は「被害者意識」で生きているが、なぜ「加害者」をはっきりさせないのかと積極的である。
しかし、それぞれ戦争は過去のものとなっておらず、「心の闇」をかこつ。
李の描き出す世界は、戦後に、戦時をきちんと総括してこなかったことに起因するが、「加害者」は大日本帝国にのみし収斂してはいかないであろう。すなわち冒頭のダワーが指摘するように、占領ー戦後は「日米合作」によって進行していく。さらに加えて、占領という事態があらたな矛盾を創り出してもいった。戦時ー占領は複雑に絡み合いながら、戦後の〈いま〉を規定し続けてきたのである。
占領は、「日本人」にとっては、見たくない事態であり、忘却したい自己の姿であった。そのため、占領をめぐっての考察は、同時代的には、なかなか書き留められていない。占領という経験の探究は、これからの課題に属している。本巻収録の作品は、そのときに有益な手がかりとなるであろう。 |
|