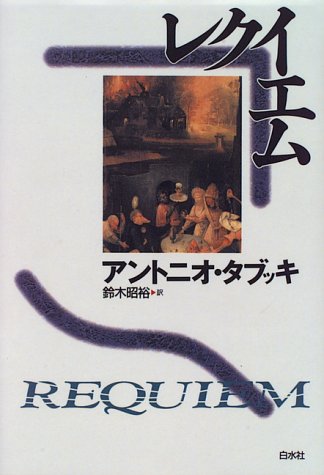
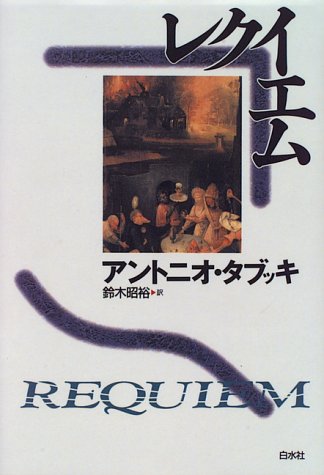
| 2021年4月14日(水) ブログ参照 http://kohkaz.cocolog-nifty.com/monoyomi/2021/04/post-1dbc2f.html ペソア 11 ポルトガルの国民的作家 お札にも フェイジョアーダ 32 豆と肉の煮込み料理 サラブーリョ 40 豚の血のスープ ポレンタ 48 トウモロコシの粉で作る付け合わせ レゲンゴス 45 赤ワイン スモル http://blog.livedoor.jp/sekainonomimono/archives/65875876.html パリのハリーズ・バー 81 バガッソ 82 https://hiroshiumezaki.yoka-yoka.jp/e540227.html https://lisboeta.exblog.jp/6974736/ ヒエロニムス・ボス 聖アントニウスの誘惑の祭壇画 https://www.musey.net/16740 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/Jeroen_Bosch_%28ca._1450-1516%29_-_De_verzoeking_van_de_heilige_Antonius_%28ca.1500%29_-_Lissabon_Museu_Nacional_de_Arte_Antiga_19-10-2010_16-21-31.jpg https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:The_Temptation_of_Saint_Anthony_by_Hieronymus_Bosch_(Lisbon) https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:The_Temptation_of_Saint_Anthony_by_Hieronymus_Bosch_(Lisbon)#/media/File:Jeroen_Bosch_(ca._1450-1516)_-_De_verzoeking_van_de_heilige_Antonius_(ca.1500)_-_Lissabon_Museu_Nacional_de_Arte_Antiga_19-10-2010_16-21-31.jpg グリロス アレンテージョ(Alentejo、発音: [?l??t??u]、アレンテージュ)は、ポルトガル中南部に位置する地方。名前は"alem do Tejo"(テージョ川の下)に由来する。 ポエジャーダ 127 スープ
|