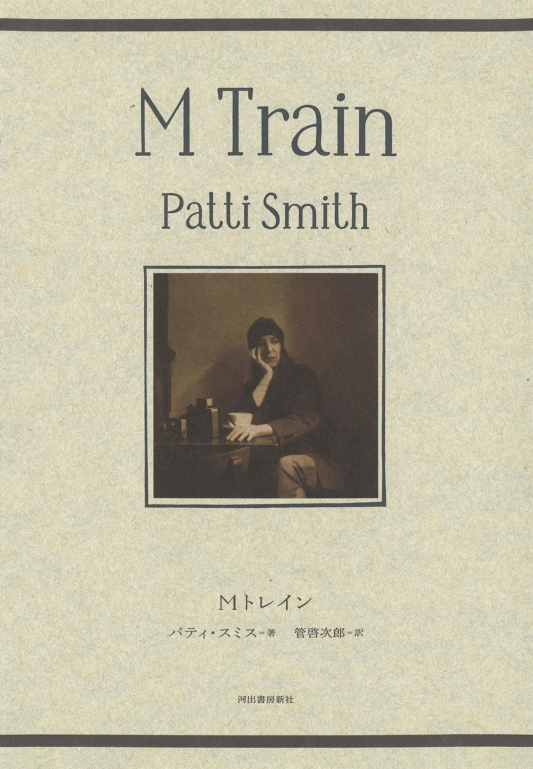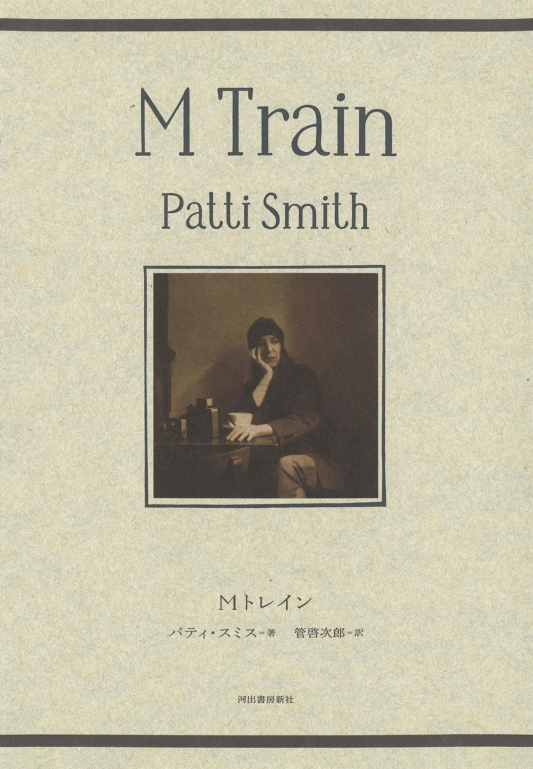2021年4月7日(水)
ブログ参照。
http://kohkaz.cocolog-nifty.com/monoyomi/2021/03/post-153f26.html
カフェ・イーノ cafe 'ino
閉店したらしい
https://www.yelp.com/biz/ino-caf%C3%A9-and-wine-bar-new-york-3
21 Bedford St
New York, NY 10014
b/t Downing St & Houston St
West Village
Ino Cafe & Wine Bar - CLOSED
21 Bedford St, New York, NY 10014
ゼーバルト『自然の後』
85p.
アルベール・カミュの肖像
ハンフリー・ボガートばりの写真
90p.
『上海から来た女』(シャンハイからきたおんな、The Lady from Shanghai)は、1947年のアメリカ合衆国のサスペンス映画。 シャーウッド・キングの小説を基にオーソン・ウェルズが製作・監督し、ウェルズの妻であったリタ・ヘイワースがウェルズと揃って主演した。92p.
フラットアイアンビルディング (Flatiron Building) は、アメリカ合衆国ニューヨーク市マンハッタン区5番街にある、高層ビルである。96p。
ビルディングは、三角形の珍しい形で建築様式も古く、人気が高い。最も細いところでは1メートル弱しかない。設計はダニエル・バーナムによる。ニューヨークで最も古い摩天楼と呼ばれることもある。96p
バーナムは、20世紀のアメリカにおける卓越した建築家として、多大な影響力を持った。彼はその生涯の中でアメリカ建築家協会(AIA)の会長を二度務めるなど、数々の役職を歴任した。1912年、ドイツのハイデルベルクで死去したときには、バーナムの事務所は世界最大の設計事務所となっていた。偉大な建築家、フランク・ロイド・ライトは、「(バーナムは、)巨大な建設計画の推進者として、その方法、人の使い方を熟知していた。彼のパワフルな人間性は、驚嘆に値する。(抄訳)」と賛辞を贈っている。バーナムの事務所は今日も継続しており、1917年以降は、「Graham, Anderson, Probst & White」の名で活動している。
カフェ・ダンテ ニューヨーク
https://shingosakata.com/entry/dante-newyorkcity/
デイビッド・クロケット物語
メイクロフト 103p
アメリカの国民的英雄の一人であるクロケットは1786年、東テネシーのグリーン郡で生まれ、1836年3月6日、テキサス独立戦争中のアラモの戦いで戦死した。50才だった。
クロケットは、伝説上の「デビー・クロケット」と史実に基づく「デービッド・クロケット」の二つのイメージを後世に残した人物だった。
「The Little Lame Prince」 Dinah Maria Mulock Craik 114p
ボラーニョ「2666」116p
『ヴィトゲンシュタインのポーカー』125p
コンティネンタル・ドリフト・クラブContinental Drift Club CDC解散 256p
ポール・ボウルズ
ピーター・アントン・オルロフスキー 268p
ジェイン・ボウルズ
はっきりしないかたちの天使たちが渦巻きながら湧き出してくるようなグラス一杯のお茶、開いたままの雑誌隅円い金属製のテーブルの上に使い終えた紙マヅチが投げ出されている。カフェたち。
パリのル・ルーケ、ウィーンのカフェ・ヨゼフィーヌム、アムステルダムのブルーバード・コーヒーショヅプ、シドニーのアイス・カブェ、トゥーソンのカフェ。アキ、ポイント・ローマのワオ・カブェ、ノースビーチのカプェ・トリエステ、ナポリのカブェ・デル・プロフェヅソーレ、ウプサラのカブェ・ウロクセソ、ローガン・スクエアのルラ・カフェ、渋谷の喫茶ライオン、そしてベルリンの鉄道駅構内のカフェ・ツォー。 |
(31p.)
|
訳者あとがき
パティ・スミス(1946ー)のことを改めて紹介する必要はないでしょう。多くの人の心の中で一九七〇年代ニュ!ヨークとのきわめて強い連想によってむすばれた、歌手、パフォーマー、写真家、ヴィジュアルアーティスト。一九七五年発表のアルバム『ホーセス』(Horses)によってニューヨーク・パンクの歴史に一時代を画し、まさにある世代を代表する「顔」となったアーティストだといっていいと思います。けれどもきらびやかで多彩な彼女の活動の核にあるもの、それは何よりも詩人の魂でした。
本書『Mトレイン』(ミぎミ』OU)は、『ジャスト・キヅズ』(Just Kids,2010)につづく彼女の二冊めの回想録です。前作『ジャスト・キッズ』(にむらじゅんこ/小林薫訳、アップリンク、二〇一二年)では、二十歳そこそこでニューヨークで暮らしはじめた彼女が、同い年の美術家(のちに写真家)ロバート・メイプルソープ(1946-89)と出会い、恋人どうしとなり、まったくの無名からはじまってそれぞれの分野で成功をおさめるまでが、なまなましく、いきいきと、記されていました。波乱に富んだふたりの人生は驚くべき人々との遭遇の連続で、まさにあの時代のニューヨークの文化シーンが当事者によって記された、貴重なドキュメントとなっています。この著作で彼女は全米図書賞という重要な文学賞を受賞し(ノンフィクション部門)、名実ともに第一線の作家の仲間入りをしました。
歴史の証言であろうとした意識がはっきり感じられる『ジャスト・キッズ』に対し、『Mトレイン』でははるかに自由な、そして彼女の内面に深く降りてゆく、語りを読むことができます。ニューヨークの地下鉄になじみのある人なら、このタイトルを聞くとすぐに「ああ、M線てあったね」と思い出すかもしれません。クイーンズを出てマンハッタンにわたり、大きなループを描くようにしてまたクイーンズに戻る路線です。この線はたしかにパティ・スミスの生活圏を走っていますが、ここでMという文字にこめられた意味は、じつはもっとずっと個人的で、しかも長い射程をもつもののようです。Memoryでしょうか。Musicでしょうか。当然、そのどちらも含まれているでしょう。しかし著者自身が、本書の刊行時に、それはMindの列車なのだと答えを明かしていました。
心の列車。自分が経験してきたさまざまな場所をたどり直すように、彼女は「目次」の代わりに「駅」Stationと記します。駅は彼女の生活と旅の記憶の、数多くの局面から選ばれています。具体的な土地、そこで会った人々。経験したできごと。大切な死者たち、かれらとの思い出。心は目的地を知らないままに、自由に連想をつむいでゆきます。冒頭で彼女の夢の中に出てきて、何度も戻ってくる謎めいたカウボーイの台詞が気になります。
「無について書くのは簡単なことじゃないよ。」パティ・スミスと深い関係にあったカゥボーイ的な男、しかも書くことそのものについての意見をもっている人物といえば、ただちに劇作家サム・シェパード(1943-2017)が思い浮かびます。本書が捧げられている「サム」は、まちがいなく彼でしょう。ともあれここで男がいう「無」が、そのまま「人生」
を意味するのだとすれば、自分の生涯を探究的に語ることのむずかしさが、最初から表明されていたのだといえそうです。実際、『Mトレイン』の「駅」のひとつは「無」(寓`)と呼ばれ、それは彼女がお参りにゆく小津安二郎の墓に刻まれた、たったひとつの文字でもありました。
死者たちとの対話という性格を、この本はもっています。中心にいるのは彼女の夫にして二児の父親でもあった、ミュージシャンのフレッド・ソニック・スミス(1948-94)。工場勤めで好奇心旺盛だった父親、ウェイトレスで大変な読書家だった母親。フレッドの死後ほとんど連続して亡くなった、弟のトッド。もちろん家族だけではなく、詩人としてのパティの精神の風景を育んだ多くの文学者やアーティストたちもいます。ここに生前の姿で登場するのは、たとえば彼女がモロッコまで会いにいったポール・ボウルズと、レイキャビクで一晩中一緒に歌をうたったボビー・フィッシャー(チェスプレーヤーを一種のアーティストと考えるなら)ですが、ボウルズのむこうには敬愛するジャン・ジュネの影があり、彼女がお墓を訪ねてゆく相手としてはシルヴィア・プラス、芥川龍之介、太宰治がいます。フリーダ・カーロとディエゴ・リベラは、若いころから特別な位置を占めていました。愛読する死んだ同時代作家たちとしては、たとえばW・G・ゼーバルトとロベルト・ボラーニョ。そして言葉という平面においては、生者も死者も、実際に肉声を知る相手も文字でしか知らない相手も関係なく、あらゆる存在がおなじ場に並ぶ以上、かれらのすべてがパティのMトレインの乗客なのです。
そんな乗客には、フィクションの中の人物も含まれます。コーヒー好きな彼女が、かつてミハイル.ブルガーコフの『巨匠とマルガリータ』を熱心に読んだようにここで夢中になって読みふける長編小説が、村上春樹『ねじまき鳥クロニクル』だというのはちょっとうれしい話ですが、ぼくに意外だったのは、書物のフィクションと同様に彼女が愛しているのがテレビの刑事もの連続ドラマだということでした。好きなシリーズの全エピソード・マラゾン放映を見るためだけに、ホテルにチェックインしたりするのですから! とりわけ愛するのが『ザ・キリング』の主役、殺人事件担当の刑事サラ・リンデンです。しかし思えば、死者たちのことを考え、かれらの生の意味を探究し、失われた命に何かを取り戻してあげようとする女性刑事の姿は、みごとにパティにとってのロールモデルとなるものなのかもしれません。
昨年出版された『猿の年』(Year of the Monkey,2019)は、『Mトレイン』の直接の続編といっていいでしょう。二〇一六年の申年に七十歳を迎えた彼女による、この一年の自己と世界の探究が、ノンフィクションとフィクションの区別を超えた自由闊達な文体で記されます。『ジャスト・キッズ』にはじまる三部作と考えてもいいのかもしれません。それに加えてスティーヴン・セブリング監督による、十一年間にわたって彼女を追った傑作ドキュメンタリー映画『パティ・スミス/ドリーム・オブ・ライフ』(Patti Smith:Dream of Life,欝2008)を見るなら、この傑出したアーティストの生涯と人柄が、よく窺えるのではないかと思います。その上で彼女の歌声に帰ってゆくとき、すべての歌がまったく新しく聞こえるはずです。
文筆家としてのパティ・スミスを支えるのは、その勤勉さと真剣さです。『Mトレイン』刊行時のインタビューで、彼女は創作の秘密を語っていました。自分は文章を書かずにはいられないこと、そして習慣を大切にすること。書くことの習慣が養われたのは、デトロイトでの子育ての時代だったといいます。音楽活動から半ば引退し、家庭に専念していた彼女は、毎朝五時に起き、子供たちが起きてくる八時までを、自分の創作のための時間に充てました。十数年におよぶこの時期が、作家としての彼女の準備期間となったのでしょう。彼女にはまた、ある種のオブセッションがあります。たとえば人の誕生日。きょうはランボーの誕生日だ、きょうはウィリアム・ブレイクの誕生日だ、などと考えて、かれらのこの地上への生誕と滞在をよろこぶのも、いわば「墓守」という役目をみずから引き受けた彼女の、もうひとつの面だと思います。
そこにあるのは、生きることへの関心と感謝。過激なようでいて驚くほどまっとうな彼女の生に向かう態度は、これからも、いつまでも、私たち自身の生の試みを励ましてくれるに違いありません。それはまた「詩人」という存在の社会的役割の、もっとも大きなものなのです。
二〇二〇年九月二十七日、東京
|
(331〜336頁)
|