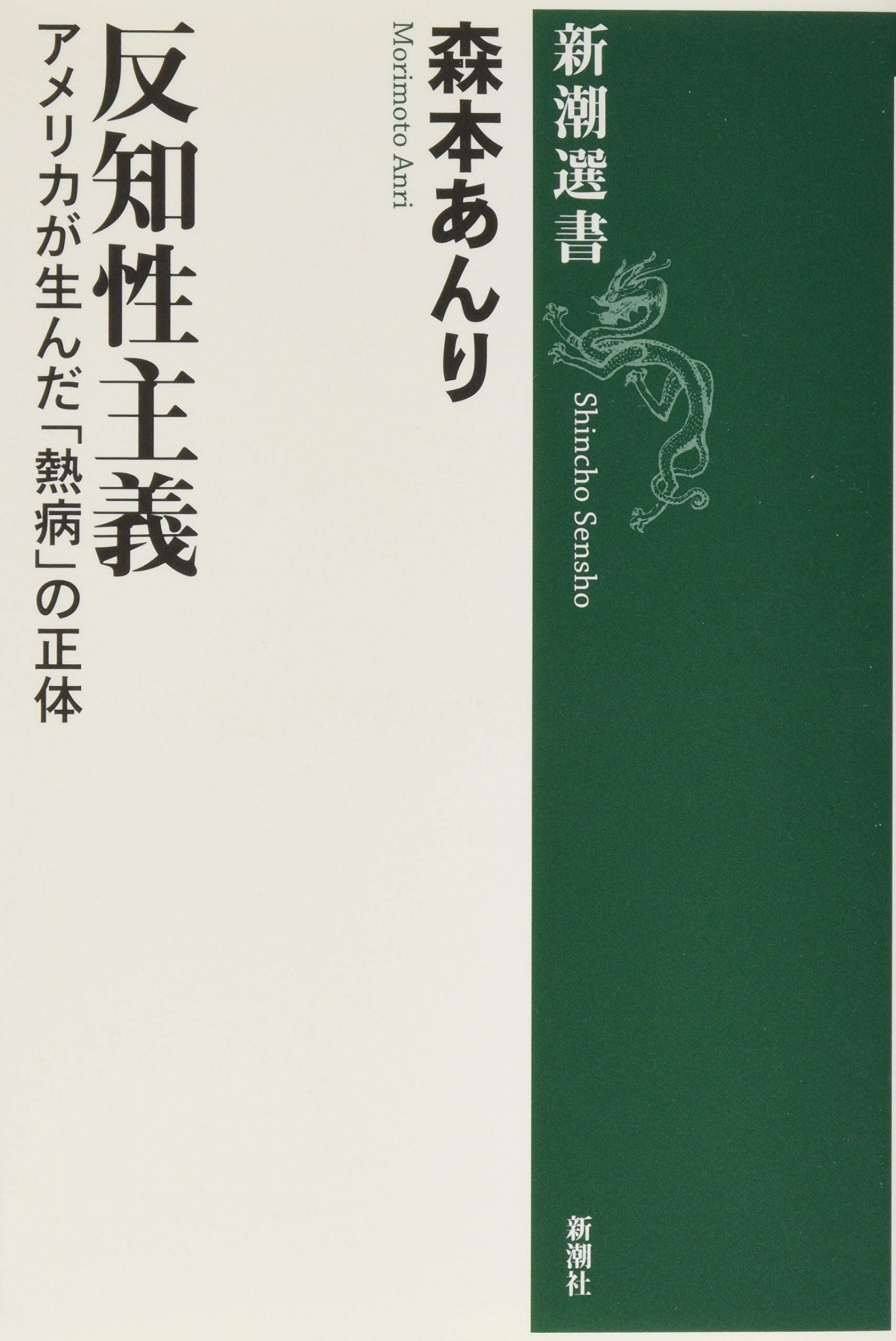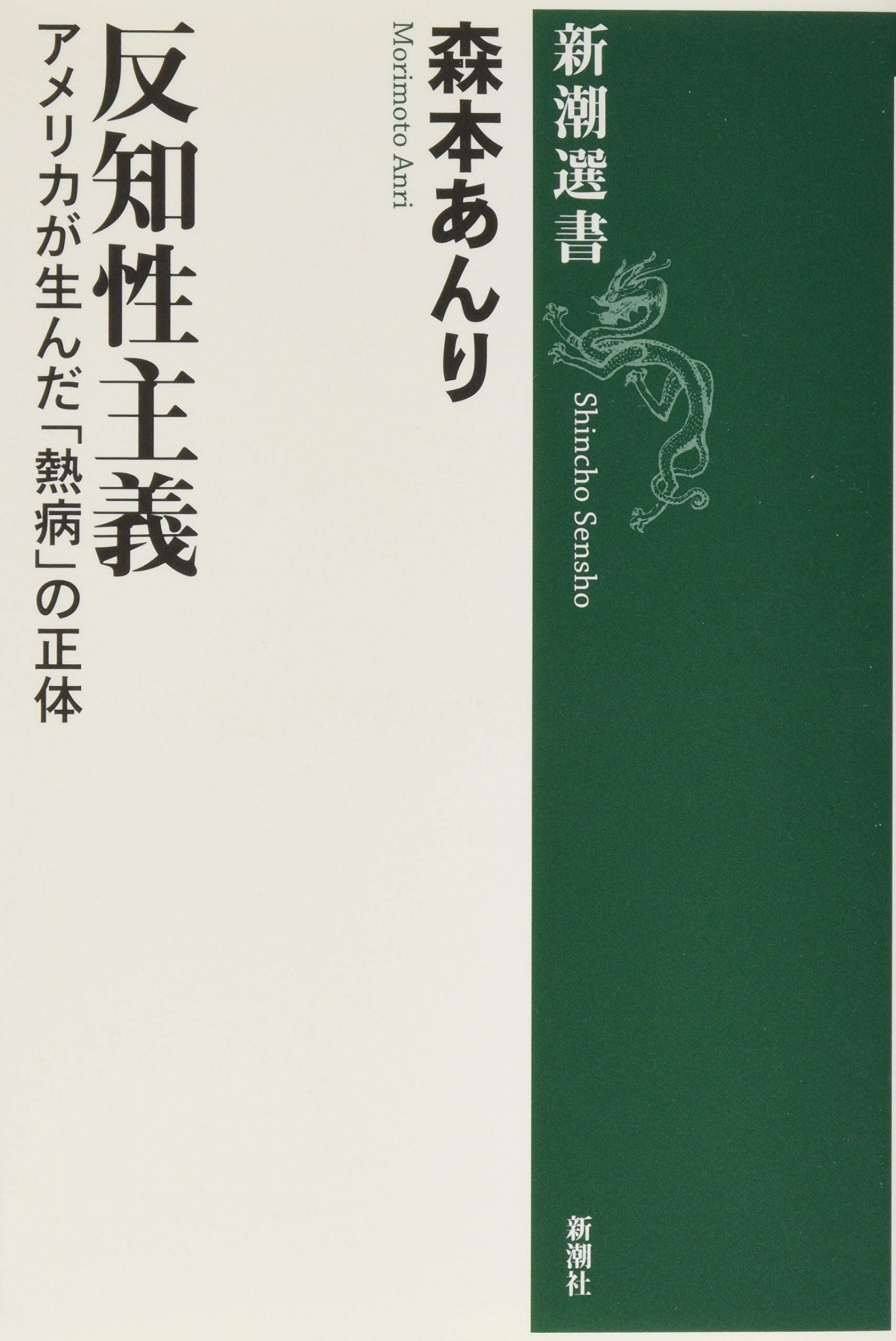|
はじめに
「反知性主義」という言葉が日本でも聞かれるようになったのは、ごく最近のことである。それまでは、アメリカ史を研究する一部の専門家たちの間で、特に二〇世紀以降の現代アメリカ社会を分析するために使われてきた用語だったが、近年では日本の時評や論壇にも頻繁に登場するようになった。
ただ、その使われ方には微妙な違いがあるように見える。日本では、「反知性主義が日本社会を覆い尽くしている」と言うように、どちらかと言うと社会の病理をあらわすネガティヴな意味に使われることが多い。たとえば、最近の若者は本を読まなくなったとか、テレビの低俗な娯楽番組で国民の頭脳が毒されているとか、大学はレジャーランド化して単なる就職予備校に成り下がったとか、あるいはそれもこれもみな、国民を無知蒙昧の状態にとどめておく「愚民政策」の陰謀だ、などという人まである。これらの文脈では、「反知性主義」とは「反・知性」、つまりおよそ知性的なことに何でも反対する、という意味だろう。たしかに、そういう局面で「反知性主」が感知されることも大いにある。
もう少しきな臭いところでは、隣国との領土問題や歴史認識をめぐって再燃するようになった日本の声高なナショナリズムなどを指して、「反知性主義」という言葉が用いられることがある。
元外務省主任分析官で作家の佐藤優は、反知性主義のことを「実証性や客観性を軽んじ、自分が理解したいように世界を理解する態度」と定義している。政権中枢にいる日本の政治家が、ナチズムを肯定するかのような発言をし、その深刻さを自覚できないでいる、というのはその典型的な症状だろう。ここには、知性による客観的な検証や公共の場における対話を拒否する独りよがりな態度が見える。他方、教育社会学者の竹内洋は、社会の大衆化が進み、人びとの感情を煽るような言動で票を集めるような政治家があらわれたことに、反知性主義の高まりを見ている。こうした政治家は、メディアに登場して「本ばかり読んでいるような学者」の学問や知性を軽蔑した発言をすると、一部の有権者が喝采を送ってくれるのを知っているのである。民主主義社会では、政治が扇動家やポピュリズムに乗っ取られる危険性は常に伏在している。
反知性主義には、以上のような要素ももちろん含まれている。しかしこの言葉は、単なる知性への反対というだけでなく、もう少し積極的な意味を含んでいる。というより、ここまでその使用法が広がってしまった今ではとても信じられないことかもしれないが、本来「反知性主義」は、知性そのものでなくそれに付随する「何か」への反対で、社会の不健全さよりもむしろ健全さを示す指標だったのである。時代によりそれぞれの論者が自分なりの意味づけで一つの言葉を用いることは当然あってよいのだが、その言葉の歴史的な由来や系譜を訪ねて意味の広がりと深まりを知るならば、もっと有意義で愉しい議論が期待できるだろう。本書はそのような探訪の旅を読者に味わっていただきたいと願っている。
「反知性主義」(anti-intellectualism)という言葉には、特定の名付け親がある。それは、『アメリカの反知性主義』を著したリチャード・ホフスタッターである。一九六三年に出版されたこの本は、マッカーシズムの嵐が吹き荒れたアメリカの知的伝統を表と裏の両面から辿ったもので、ただちに大好評を博して翌年のピュリッツァー賞を受賞した。日本語訳がみすず書房から出たのは四〇年後の二〇〇三年であるが、今日でもその面白さは失われていない。訳者の田村哲夫が「あとがき」に記しているとおり、「説得的な歴史観の下で、正確な叙述で表わされた歴史書は、どんな時代にも古くささを感じさせるものではないし、どんな時代にも有益なヒントをあたえてくれる」ものである( )。
だが、もしそんなに名著であるのなら、これが四〇年も訳出されずに放っておかれたのはなぜだろう、という問いも湧いてくる。理由の一端は、この本の内容が日本人には理解しにくいアメリカのキリスト教史を背景としているところにある。この本に言及する人もあるにはあるが、よく見てみると、引用されているのは冒頭の数頁だけで、内容的な議論の深みへと足を踏み入れる人は少ない。けっして難しい本ではないが、日本人になじみの薄い予備知識が必要なため、本筋のところが敬遠されてしまうのである。その先に続く議論の面白さを考えると、これは実にもったいない話である。アメリカの反知性主義の歴史を辿ることは、すなわちアメリカのキリスト教史を辿ることに他ならない。
|