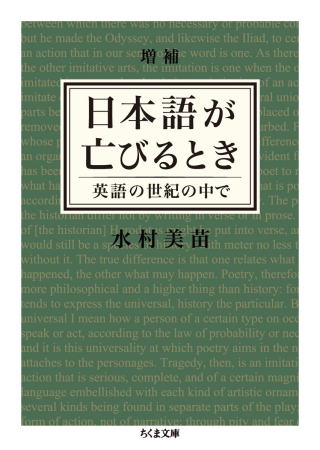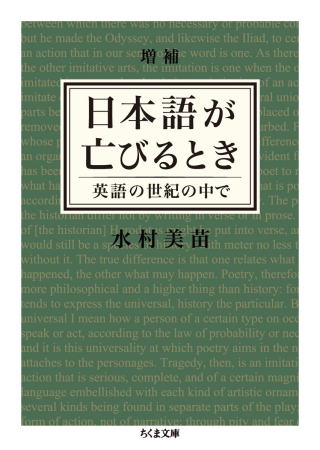2020�N2��3���i���j
�@�������c�w���� ���{�ꂪ�S�т�Ƃ�: �p��̐��I�̒��Łx�Ǘ��B
�@�u���O�Q�ƁB
����ۂB
���V�A��ł������A�w���̂����w�ŏ�f���Ă����\�r�ۃg�f��4,�ꂢ�����ϗ͂́A�����ɂ킩�����B�f��ŕ������̂Ɠ��������ȃ��V�A��ŁA���g�A�j�A�̎Ⴂ,���l�ɉ������₵�Ă���B���[���V�A�嗤�ɂ́A���{�l�Ƃ�������Ȋ�A�����āA���V�A��𗬒��ɘb���l����������̂͒m���Ă����B�����A���{�l�Ƃ�������Ȋ�����āA���V�A��𗬒��ɘb���l�����ۂɌ����̂͏��߂Ăł������B�����S���̋ߑ�j��m���Ă�����������قǂ̂��Ƃ͂Ȃ������̂����A���̂Ƃ��̎��͂Ђ�����������B�~�̘͂b�͓����琁�����ł��܂����B
�u���V�A���b�����̂ł���?�v
�u�͂��A���X�N���ŕ����܂����v
���g�A�j�A�̎��l����ɓ������B
�u����̃��V�A��͎��̃��V�A�����قǏ��ł��v
�����S���̎��l�͂�����đ�g�ɏ��Ă���B
���̂Ƃ����͏��߂ė��������B���̓�l�́A����ɋ��R�ɒʘH���u�ĂĂ�����Ă����̂ł͂Ȃ������B���A�W�A�l�̘Z�\�߂��j�Ɣ��l�̎Ⴂ�j�́A�͂�����݂�Ί�ȑg�ݍ��킹�ł͂��������A���V�A�����ėF�B�ƂȂ��Ă����̂ł���B�������A�l�̓����S���ɐ��܂�āA���X�N���ɗ��w���A���V�A����w�肷��̂��B�����āA�l�����㔼�ɂȂ��č��x�̓A�������̑�w�ɏ�����A�����ł��ă��X�N���Ŋw���V�A��ŁA���Ƀs�A�X�������Ⴂ���g�A�j�A�l�ƗF�B�ɂȂ����肷��̂��B��㔪��N�A�x�������̕ǂ����ꗎ����Ɠ����ɗ��\�����I�����ނ����A�A�����J����l�������āA�n�����ǂ��܂ł����������{��`�ɕ�����悤�ɂȂ����[�Ƃ́A������\�N�߂��A����ƂȂ�����Ԃ��ꂽ���t�ł���B���ꂪ�����Ƃ��Ă��̂܂ܖڂ̂܂��ɂ������B���̂܂ɂ���l�̓��V�A��ʼn�b�����n�߂Ă����B���炭����ƁA���g�A�j�A�l�̎߂�����ɂ�����Ă������l�̒��N�̏��̐l�����̃��V�A��̉�b�ɉ�������B���Ƃł킩�������A�C�t�Q�[�j�A�Ƃ����A�M���V���_�b�ɏo�Ă��邨�P�l�̖��������A�E�N���C�i����̏����Ƃł������B
������̕�����͒�����Ɗ؍��ꂪ�������Ă���B |
�i�P6�`17�Łj
�A�����J�̒������A���ƂɃA�C�I���B�́A�c�ɂ̑㖼���ŁA�܂��ɁA�ǂ��܂ł��Ƃ����낱�������������ƂŒm���Ă���B�A�C�I���E�V�e�B�́A���̏B�̂��܂ɂ���A�B���̃A�C�I����w�𒆐S�Ƃ�����w���ł���B�l���Z���l�̂���̔������w�����Ƃ����B�����A�Z�ނ����ɂ킩���Ă����̂́A�A�C�I���E�V�e�ł�������T�^�I�ȁu��ɂ̑�w���v�ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃł���B�����Ȓ��Ȃ̂ɁA��w�̓�����O�ɂ����A�}���فA���p�فA����A�f��فA���X�A�e���̃��X�g�����ȂǁA���\�Ȃ��̂��Ƃ��낹�܂��ƕ���ł���B�Ƃ�킯�������̂́A�A�����J�A���������������Ƃ����̂ɁA�}���n�b�^���̃O���j�b�`�E���B���b�W�ɂł����肻���ȁA�l���o�c���邱����܂�Ƃ����i���X�����������邱�Ƃł���B���̗��R�͈�B�A�C�I����w�͂֏�Ăŏ��߂Đݗ����ꂽ�n��w��(IWW=Iowa Writer's Workshop)���L���ŁA���̑n��w�Ȃ̑��݂��A���̒�������Ȃ�c�ɂ̑�w���Ƃ͂������A����߂ĕ��w�I�Ȓ��ɂ��Ă���̂ł���B(������Z�Z���N�ɃA�C�I���E�V�e�B�̓��l�X�R����u���w�̓s�s�v�Ƃ��đS�ĂŗB��w�肳�ꂽ�s�s�ƂȂ����B)
�S�Ăŏ��߂đn�����ꂽ�Ƃ����A�C�I����w�̑n��w�Ȃ́A���A�S�Ăň�ԗD�ꂽ�n��w�Ȃ��Ƃ������Ƃɂ��Ȃ��Ă���B�����ŋ�����̂���ƂƂ��Ė��_�Ȃ̂͂������A�������������Ŋw�Ԃ̂��w���Ƃ��Ė��_�ł���炵���B���N�A�����Ǝu�]�A���l�u�]�A����ɐ��l�̖|��Ǝu�]�������A�ȏ�l�]��̐��k���l�w���邪�A�����Ǝu�]�ƂȂ�Ɩ�O�\�{�̓�ւ�������˂Ȃ�Ȃ��B���{�̑�w�̑n��w�ȂƂ������A���łɑ�w�𑲋Ƃ������k�����ł���B�n��w�ȂȂǂŕ��w�̏��������w�ԂƂ����̂́A���{�ł͕]���������A�����g�A��Ƃ������ĐH�ׂ���Ƃ����ȏ�̈Ӗ��͂��܂茩�o���Ă��Ȃ��������A����A���̓�ւ��������Ă����w���������܂̂�����ɂ��āA�����Ԏv�������߂��B��w���o�����Ɣ�r�I�Ⴂ�����ɓ�N�Ԃ����ł��������̂����������𑗂�B���̂��ƁA�^���Ȃ�����̂������d���ɂ͂��Ȃ����A�Ⴂ��������̌P�����A�ꐶ�̂����A�����͖��ɗ��Ă����Ƃ��̋@��_���ď���������B�����������S�ȐS�����̊w���������S�Ă���W�܂��Ă����̂ł���B
�@�n��w�Ȃ��ݗ����ꂽ�̂����O�Z�N�B���ꂩ��O�\�N��A�����ɂ킽���Ă��̑n��w�Ȃ̃f�B���N�^�[�߂Ă����|�[���E�G���Q���Ƃ������l�����E�����Ƃ��ł���B
�j�G���t�A�����ނ̏����̍ȂƂȂ钆���l�̏����ƁA�j�G�ؗ肪�A�S���E�����Ƃ��W�߂Ă���Ƃ����v���O�����𗧂��グ��̂�����B���ꂪ�A�����Q������IWP�ł������B
���Z���N�Ɏn�܂��Ĉȗ���l�ȏ�̍�Ƃ�S�͍��ȏ�̍�����}�����Ƃ���(����]���N�O�A��������Ɋׂ�A�v���O������ł��낤�Ƃ������f�������ꂽ���������A�\�z�����Ȃ������w���Ǝs���̔��f��������L�����A�����Ȃ������Ƃ����B�����Q�������Ƃ��͐V�����f�B���N�^�[���}���đ��𐁂��Ԃ����Ƃ���ł������B�A�����J�� |
�i28�`29�Łj
��l�����^���Ă���鐔�X���ґ�[�㎿�ȋ�ԁA�������ߕ��A���������H���Ȃǂ��y���ނ��Ƃ��ł����ł��낤�Ǝv�킹�鏗�̐l����������ł���B
�ʂꂪ�߂��Ȃ�������ޏ��͗�����,���������B�Â����������Ɩڂ̉���������ō����B
�u�|�[�����h�ɁA�߂�����܂���w�ŋ����Ȃ���Ȃ�Ȃ�.�����̈������ƂƂ�������c�c�v
�ޏ��̓����V�����̃A�p�[�g�ŔL�ƏZ��ł���ƌ����Ă����B
���Ƃ͂Ȃ��ɁA��Ԑe�����Ȃ����̂́A�u���b�g�Ƃ������́A�m���E�[���炫�����̍�Ƃł������B�������͒m�荇���Ă��炭���邤���ɁA�Ă̗z�˂���ɂ���ŕ����ɌJ��o�������X�g�����ŁA���ɂ��搁����Ȃ���A�ꏏ�Ƀr�[����ۂ�H���������肷��悤�ɂȂ����B�ꏏ�Ɍ���ɑ����^�肷��悤�ɂ��Ȃ����B�Ԗтł��������炯�̃u���b�g�́A������łĐ��i�����������ɁA�������������펯�l�ł��������B�|�������̂ʼnp����g��ł���B�����A�ޏ��Ɛe�����Ȃ����̂́A���̂悤�ȗ��R�����ł͂Ȃ��B�݂��ɋ����̍����炫���̂ŁA�Ȃ��ƈꏏ�ɍs�����Ƃ�₷�������Ƃ�������A�����ɉ�������̂ł���B��Ƃ̑����͊O�Ńr�[�����̂ނƂ������ׂ��ґ�����Ɏ����ɋ������Ƃ͂��Ȃ��������A�Ԗт̃u���b�g�Ƃ́A���Ԃ���r�[����ۂ݃p���p���ƃ^�R�X��������Ȃ���A�܂�ʚ��ʌ����������߂�����
����ɂ́A���܂��܂Ȑ����Ƃ������̂��������B
�l�͋����ȍ���n�R�ȍ��ŏ��������łȂ��A���܂��܂Ȑ����̂��Ƃŏ����Ă���Ƃ����̂��A�A�C�I���ɍs���ď��߂Đg�������Ċ��������Ƃł���BIWP�̂悤�ȃv���O�����ɎQ���ł��邱�Ǝ��́A�Œ���͋@�\���Ă��鍑���炫���̂��Ӗ������B�����܂������@�\���Ă��Ȃ���A��ƂƂ����E�Ƃ����藧���Ȃ��B�����A���{���炫�����̂悤�ɁA�ו��̐���搉̂��Ă����l�Ԃ���łȂ������̂͂����܂ł��Ȃ��B
���\�r�G�g������̍�ƂɂƂ��ẮA�܂��́A.���_�̎��ȂƂ������̂��A������܂��̂��̂ł͂Ȃ������B���Ƃ���!�}�j�A����̎��l�̃f�j�[�T�B���t���������t�����X�ɋ߂������ł��낤�A�u���B�B�����Ƃ����������n���ɂ��������A�O��˂��o�������������߂��肷�鏊����A�ǂ����t�����X�l�Ɏ��Ă���A�����������ŁA�ƂĂ��A���Ɓu�����̐l�ԁv�ɂ͌����Ȃ������B�Ƃ��낪�A����ȃf�j�[�T�̓��̒��́A�u���ƌ��͂Ƃǂ��������Ă������v�Ƃ����悤�ȓ�����Ƃł����ς��ł������B�\�r�G�g�̎x�z���ł͍��Ƃ̌��{�͓��e�����łȂ��`���ɂ��y��..��\���I���I���̂���ɂȂ��āA�C�܂Ȃ����R���͌��ɂ͔��\�ł��Ȃ��Ƃ������m�Ȃ��Ƃ��܂���ʂ��Ă����̂ł���B |
�i�T�Q�`�T�R�Łj
�H�ׂ邽�߂ɍ��ƂƑË����ĕ��w��(�����Đl��)�Ƃ��Ă̑������������A�H�ׂ��Ȃ��Ƃ����ƂƑË������ɂ��邩�B�f�j�[�T�ɂƂ��Ă��̂悤�ȑI���͂�����̂��Ƃ̂悤�Ɏv����炵���A���ɔ��\����Ƃ����l�I�ɘb���Ƃ����A���̗������߂����Ă̘b���K���łĂ����B
�@�������A�����݁A���_�̎��R�̗}�����o�����Ă����Ƃ���������B
�@�������̂悤�ɁA�����͌��_�̎��R���ۏ��ꂽ���ł͂Ȃ��B���X�ɂ킩���Ă������̂́A�����X�[�c���������u�s��̂����v���A���͌��_�̎��R�̓��m���Ƃ��������ł���B�j���[���[�N�ɋ����ڂ��A�{�y�����ł͔��\�ł��Ȃ���i���W�߂ĕҏW���A���E���ɎU����������l�Ɍ����ďo�ł��Ă���Ƃ����B�j���[���[�N�ɏZ��ł���Ƃ������ɂ͕s�v�c�Ƒ債�ĉp���b�����A�L���ň��A��������x�̂������ɗ��܂������A�����݂Ȃ��ꑫ��ɋA��Ƃ킩��ƁA�o���̂܂��̔ӁA�����̃h�A�̉��ɉp�ꂽ����̒Z�҂��E���Ă������B
�@�����{�y�ł͔��\���Ȃ��������̂ł���B
�@��l���̑c���͋ɂ߂ĕn�����炿�Ȃ̂ɂ�������炸�A���Y�}�v���̂��ƁA��c���y�n�������Ă������Ƃ��������A�u�n��̌��v�������Ƃ������b�e����\���ē�������A�����߂ʂ���A�c��̐l�����C����(��)�ꂽ�܂ܑ���B�₪�ĔN�V���Ĕs���ǂɂ�����A�x�d�Ȃ�A�����邱�ƂɂȂ�B����̐g�̂Ɂu�S���̌��v�������Ă����̂ł���B
����͊��Ă���ꂻ���āA�������B����Ȃɕ֗��ȕ��@���������̂Ȃ�A�Ȃ��A����Ȃɂ����߂ʂ����܂��ɁA�����́u�n��̌��v���u�S���̌��v�ɓ���ւ��Ȃ������̂��낤�B�����̖��m���������́A���q�⑷�ɁA�ꍏ�����������̌����u�S���̌��v�ɓ���ւ���悤�����c���B�����čŌ�́A����Ŏ����̌��͂��ׂāu�S���̌��v�ɓ���ւ�����A�������̐��ɍs���Ă�����|�����Ƃ͂Ȃ��A�悩�����悩�����A�悤�₭���S���Ď��˂�A�ƌ����Ď��ۂɈ��S���Ď���ł����[�Ƃ����ߊ쌀�I�ȋł���B
�@�����̌㔼�͎�l���̑����j���[���[�N�ɂ��ǂ蒅���Ă���𒆐S�ɓW�J����A���{��`�̔g�ɂǂ����Ă����Ȃ������̂��A������A�R�J�R�[����r�ɂ�������ƗA������ƓˑR���ׂĂ����܂������悤�ɂȂ�Ƃ����t�@���^�W�[�E�m�x���ƂȂ�B���Y��`�Ǝ��{��`�Ƃǂ�����ᔻ��������ł��邪�A�O���́u�S���̌��v�̕��������|�I�Ƀ��A���e�B���������B
�@�����āA�R���������ɂ���A�r���}(�~�����}�[)����̏��V�̍�ƁB���̍�Ƃ͂Ȃ��IWP�ɎQ�����Ă���Œ��ɁA�A�����J�ɖS�����Ă��܂����̂ł���B�f���ɃT���_�����͂��A���ɐF�����₩�Ȗ����ߑ����܂Ƃ��A���M�т����̂܂ܓ����Ă���悤�Ȃӂ���������ɎT���U�炵�Ȃ���A�u�����ɏƂ炳�ꂽ�z�e���̘L���������X�^�X�^�ƕ����Ă����B�e���h�ŁA�w�r���}�̒G�Ձx��f���炵���{���Ƃ����A���ɂ͖��� |
�i54�`55�Łj
| ���̐��ɂ͌���ꂽ�����������Ȃ��B�P�l�͕��ꂸ�A�D�ꂽ���w�����̖ڂ������ɏI���B���{�ߑ㕶�w�����݂����Ƃ������������E�̓Ǐ��l�̂������Œm���Ă��邱�ƁB����́A���{�ߑ㕶�w���D��Ă������Ƃ��A�K�������Ӗ�������̂ł͂Ȃ��B�����������{�ߑ㕶�w�̑��݂����E�ɒm��ꂽ�̂́A���{�̐^��p�U�����_�@�ɁA�A�����J�R���G����m�邽�߁A���{�ꂪ�ł���l�ނ�Z���Ԃŗ{������K�v�ɂ���ꂽ�̂���ԑ傫�ȗv���ł���B�A�����J�̏��ǂɌق�ꂽ���ł��ɂ߂ē��]�D�G�Ȑl�������I��ēO��I�ɓ��{����w����A����炪�̂��ɓ��{���w�̌����ҁA�����Ė|��҂ƂȂ����̂ł������B�G�h���[�h�E�T�C�f���X�e�B�b�J�[�A�h�i���h�E�L�[���A�A�C���@���E�����X�͊C�R�ŁA�n���[�h�E�q�x�b�g�͗��R�ŁB�قړ�����ŁA��O�̓��{�Ɉ�����X�R�b�g�����h�l�̃G�h�E�B���E�}�b�N���������A���V���g���̏��ǂœ��������Ɩ|��҂ƂȂ����B |
129p.
| ���Z���N�ɐ�[�N�����m�[�x�����w�܂���܂����̂��A���̂悤�ɉp�������������ł���B�m�[�x�����w�܂�m�l���ŏ��Ɏ�܂����̂̓C���h�l�̃^�S�[���ň���O�N�B�����^�S�[���̓x���K����ŏ��������������ʼnp�Ă̎�܂ł���B�m��̍�Ƃ���܂����̂́A�Ȃ�Ƃ��ꂩ�甼���I�ȏソ�������Z�Z�N�B�I�[�X�g���A�E�n���K���[�鍑�ɐ��܂ꂽ���A�w�u���C��ŏ����悤�ɂȂ����C�X���G���l�̍�Ƃł���B�����āA���̓�N��̈��Z���N�ɁA��[�N���������B�m��̎�҂͂��̂��Ɠ�\�N�ԂȂ��������Ƃ��l����A�����ɉp�o�ł��ꂽ���Ƃ����{���w�ɂƂ��ďd�v�ł����������킩��B�m�[�x�����w�܂̈ł̕����́A���̐�������ʂɂ��Ă��A�|��Ƃ����A���w�ɂƂ��Ă����Ƃ����{�I�Ȗ���^���ɍl���Ă��Ȃ����Ƃɂ���B�����A���{�l�̍�Ƃ���܂���A���{�ߑ㕶�w�̑��݂���萢�E�ɒm����悤�ɂȂ�̂͂������ł���B�₪�āA�Ⴂ����̖|��҂��炿�A���{�ߑ㕶�w�̌ÓT�Ƃ�����i�����łȂ��A�O���R�I�v�A�����Ă̂��ɓ��{�l��l�ڂ̃m�[�x�����w��҂ƂȂ��]���O�Y�Ȃǂ̍�i���A������I�ɉp��ɖ|���悤�ɂȂ�B�����̖|���ʂ��A���{���w�͂���ɐ��E�Œm����悤�ɂȂ����̂ł������B |
130p
�@���̖{�́A���̏͂���A����܂łɂ������G��Ă����O�̊T�O�𒆐S�ɓW�J������B
�@�܂��́q���Ռ�r�B���{��Ƃ��ẮA�q���E��r�Ƃ����\���̕����܂��������������������邪�A�p��́uuniversao langauge�v�ɊY������\���Ƃ��Ă����Ŏg���B
�@��ڂ́A�q���n��r�B����͓��{��Ƃ��Ē蒅���Ă���A�p��̃R�ulocal language�v�ɊY������B
�@�O�ڂ́A�q����r�B����͉p��́unational language�v�ɊY������B�p��́unational language�v�́uofficial language�v=�u���p��v�قǂ͂�����ƋK�肳�ꂽ�\���ł͂Ȃ��B���Ƃ��@�I�ɂ����K�肵�����t���w�����Ƃ��A����n��ŁA������A���ʌ�Ƃ��ė��ʂ��Ă��錾�t���w�����Ƃ�����B�����ł́A�q����r���A�u�������Ƃ̍��������������̌��t���Ǝv���Ă��錾�t�v���w�����̂Ƃ���B�q�������Ɓr�Ƃ����T�O���ߑ�I�ȊT�O�ł���悤�ɁA�q����r�Ƃ����T�O���ߑ�I�ȊT�O�ł���B�������A�q�������Ɓr�Ƃ��ēƗ������������A����ɂ͎����n��ɂȂ肽���̂ɁA�����I�ȗ��R�ł����Ȃ邱�Ƃ��ł��Ȃ��������A�q���������̌��t�r���Ǝv���Ă��錾�t���A�����ł́q����r�Ƃ�ԁB
�@�������A���鍑�����g���q����r�͕K�����������ƈ�v���Ȃ��B�����q����r�����܂��܂Ȓn��Ŏg���Ă��邱�Ƃ����邵�A�q����r�͑��݂����A��̒n��ŕ����́u���p��v���g���Ă��邱�Ƃ�����B����ɂ́A�q����r�Ɓu���p��v�Ƃ𗼕�����������B�܂��q����r�������₯�ɂ͑��݂��Ȃ�����A���ۂɂ͍L�����ʂ��Ă��Ȃ���������B���������ł́A���̂悤�ȍׂ������Ƃɂ͓��݂��܂Ȃ��B
�@����Ԃ����A���S�ƂȂ�T�O�́q���Ռ�r�Ɓq���n��r�Ɓq����r�̎O�B�����܂ł��Ȃ��A�l�ނ̌��t�̗��j�́A���ۂ́A�Ђǂ����ׂƂ��č����������̂ł���B���̎O�̊T�O�́A���̍��ׂƂ��č��������l�ނ̌��t�̗��j���A�ł��邾���������čl���Ă������߂Ɏg�����̂ł����Ȃ��B |
134-135p
�܂��A���ꂩ�炵�炭�́A��̌��t�𑀂邱�Ƃ��ł���l�������A�u�o�C�����K���v�Ƃ���ɁA�u��d����ҁv�Ƃ���������Ȃ��\���ł�ԁB�u�o�C�����K���v�Ƃ����\���������̂́A�u�o�C�����K���v�Ƃ́A���{��ł́A�j�J�����b����Ƃ����Ӗ���������������ł���B�����ł����u��d����ҁv�Ƃ́A�����́q�b�����t�r�Ƃ͂������O�����ǂ߂�l���w���B�ǂނƂ����s�ׂ𒆐S�ɁA�l�Ԃ̏������t�ɂ��čl���Ă�����������ł���B�����́q�b�����t�r�����ǂ߂Ȃ��l�́u�P�ꌾ��ҁv�ł���B
�܂��A�u�m���v�A���邢�́u�m��v��u�m�l�v�Ƃ����\���B�A���{��ł͂��܂�g��Ȃ����A�ߑ�𗝉������ŁA�d�v�ȊT�O�ł���B���̊T�O������킷�̂ɁA����A�u���m�ł͂Ȃ��v�Ƃ��A�u���m�ɂ��炴��v�Ȃǂƒ����\�����g���̂�����邽�߁A�����̂����ۗ͂ɗ��邱�Ƃɂ����B�p��ł����unon-Western�v��unon-European�v�Ɠ����ł���B(�p��ł́uthe West�v�ɑ��āu������֓�A���Ȃ킿�u���̑��v���邢�́u�c�蕨�v�Ƃ����A���C�\�����A���m���S��`��ᔻ����Ӗ����܂߂Ďg�����Ƃ�����B)�������A�u���m�v�Ɓu�m�v�Ƃ����Η����́A�����܂��ȕ������c���B�I�[�X�g�����A��j���[�W�[�����h�͎�Ƀ��[���b�p����̈ڏZ�҂��p����q���r�Ƃ��Ďg���Ă������X�������A�n��(�����Đ�Z��)�����āu���m�v�ɓ����Ƃ��Ă��A������l�������ɂ�������炸�A�����̐l�X�̉ߔ����͔��l�ƃC���f�B�I�̍����ň��V����ɂ́A���́q���r�Ƃ����\���B���{��ł͍��͂܂��u�ꍑ��v�̂ق����q���r��������ݐ[�����A�Ԃ�V�̂���Ɏ��R�Ɋw�Ԍ��t���A���Ƃ̌��t�ƈ�v���Ă���Ƃ͌���Ȃ��̂ŁA���̖{�ł́q���r�Ƃ����\�����g�����Ƃɂ����B�u�{�S�v�Ƃ������͎��ɉ����Ȃ����A��萳�m�ł���B�p��́umother tongue�v�ɊY������B
����ł́A�܂��A�q���Ռ�r�Ƃ͉���?
�q���Ռ�r�Ƃ͉������l����̂ɁA���傤�ǂ悢��������^���Ă����A����̖{
�[�������A�ߋ��l�����I�ɂ킽���Đ��E���ő傫�ȉe��������������̖{������B��
���Ɂq���Ռ�r�ɂ��Đ[���l�@�������ł͂Ȃ��B����ǂ��납�A�����ɂ́q���Ռ�r�ɂ��Ă̍l�@�������قǂȂ��B�����A�܂��ɂ����Ɂq���Ռ�r�ɂ��Ă̍l�@�������قǂȂ��Ƃ������̎�������A�q���Ռ�r�Ƃ͉��ł��邩�Ƃ������Ƃ��A�ނ���A����������̂悤�ɋt�Ɍ����Ă���̂ł���B
���̖{�Ƃ́A�ق��ł��Ȃ��A���łɌÓT�ƂȂ����A�x�l�f�B�N�g�E�A���_�[�\������
�w�z���̋����́x�ł���B�ߑ㍑�Ƃ̐��藧���ɂ��ĕ��͂����{�ŁA�Ȃ��ł��q����r�ƁA�q�������w�r�ƁA�i�V���i���Y���Ƃ̌��т��𖾂炩�ɂ����������L���ł���B |
136-137p
�o�ł��ꂽ�͈̂�㔪�O�N�A����ł��o�ł��ꂽ�͈̂����N�B�|�ꂽ���Ɠ��{�ł��傫�Ȕ������ĂсA���Ƃɕ��w�����҂̂������ŁA�q�������Ɓr�Ɓq�������w�r�ɂ��čl����ۂ̕K�Ǐ��ƂȂ���(����)�B
�w�z���̋����́x�̊j�S���ꌾ�ŗv��A���̂悤�ɂȂ�B
�@���Ƃ͎��R�Ȃ��̂ł͂Ȃ��B
�@���A�l�ނ̑����[���Ƃɓ��{��[���b�p�Ȃǐ�i���̍����́A���Ƃ̑��݂������Ȃ��̂��Ƃ��Ă���B�����A�A���_�[�\�����킭�A���ƂƂ́A���܂��܂ȗ��j�I�ȗ͂��������邤���ɑ����Ă������A�u�����I�l�����v�ł����Ȃ��B�����A����������ƁA�������������قǂ́u�[������(�A�^�c�`�����g)�v��l�X�Ɉ����N�����A�����A�l�́A�����̂��߂ɐ��S���̒P�ʂŎ���ł������̂ł���B
�q����r�̐����ɘb�����ڂ肽���̂ŁA�����ŏЉ��̂́A�u���v���܂ށA�w�z���̋����́x�̍ŏ��̎O�͂ł���B
�@�E�̗v��ɕ���Ă��̍ŏ��̎O�͂��A�ꌾ�ŗv��A���̂悤�ɂȂ�ł��낤�B
�q����r�͎��R�Ȃ��̂ł͂Ȃ��B
�@���A�l�ނ̑����́A���������́q����r���A���̂��������A���Â̐̂���g�Ă������t���Ǝv�����ނɂ������Ă���B�Ƃ��낪�A�w�z���̋����́x�ɂ��A�q����r�Ƃ́A�������̗��j�I�������d�Ȃ��Đ��܂ꂽ���̂ł����Ȃ��B����ł��āA��������q����r�����܂��ƁA���̗��j�I�Ȑ����ߒ��͖Y�ꋎ���A�Y����邤���ɁA�l�X�ɂƂ��āA�����������ꂪ�����Ƃ��[�����������̍������[�[�������̕\�ꂾ�ƐM�����܂��悤�ɂȂ�B�q����r�̓i�V���i���Y���̕�̂ƂȂ�q�������w�r��n��A���x�͂��́q�������w�r����̂ƂȂ�q�������Ɓr��n���Ă����B�����I�ɑ��݂���킯�ł��Ȃ��̂ɁA�l�����̂��߂ɂȂ疽��e(�Ȃ���)���Ă����Ƃ܂Ŏv���A�A���_�[�\�����킭�́A�u�z���̋����́v��n���Ă����̂ł���B
�q����r�̐����ɂ��ẮA�A���_�[�\���̗��j�I�ȕ��͂�����I�Ȃ̂́A���{��`�̔��B�Ƃ����A�����\���̃��F�N�g������ꂽ���Ƃɂ���B�������̂悤�ɁA�\�ܐ��I���A���[���b�p�ŁA�O�[�e���x���N����@����������A���܂Ŏ�Ŏʂ��Ă����������@�B�ň���ł���悤�ɂȂ����B�O�[�e���x���N����@�̔������l�ނ́q�������t�r�̗��j�̂Ȃ��ł����ɑ傫�ȈӖ������Ɏ��������͎��m�̎����ł���B�����A�A���_�[�\�����킭�A���Ƃ��A�O�[�e���x���N����@����������A�������@�B�ň���ł���悤�ɂȂ��Ă��A���̈�����ꂽ���������i�ƂȂ��ė��ʂ��Ȃ��ẮA����@�̔������Љ� |
138-139p
| �����A�u���Ȃ錾��v�������̐l�Ԃ̌��t�ł��������Ƃɋ�����u���A���_�[�\�����A�u���Ȃ錾��v�ɂ��āA����Ԃ��g���`�e��������B�u�r�����@�v1���{��ł́u��`�I�v�Ƃӂ����`�e���ł���B�uArcane�v�́umysterious=�_��I�v�ȂǂƂ������t�Ɠ��`��ł���A�����̐l�ɂ����킩��Ȃ��Ƃ����Ӗ������B��̓I�ɂ́A����班���̐l�Ƃ́A�A���_�[�\���ɂ�āA�u���l�v�u�G���[�g�v�u�����C���e���Q���`�@�v�ȂǂƂ���l�����ł���B�����ɂ����킩��Ȃ��Ƃ́A������܂������A�c��̑命���ɂ͂킩��Ȃ��Ƃ������Ƃł���B�u�r�ڂ����v�̌ꌹ�́A���e���Ȃ� |
153p
�@���e���ꂪ�D��āq�w��̌��t�r�ł��������̂�F������ƁA������܂��̂��Ƃ������Ă���B�̂��ɐ��E�𐧔e����悤�ɂȂ�ߑト�[���b�p�[���ꂪ�A�����Ɂq�w��̌��t�r�Ƃ��Ẵ��e����ɂ���đn���Ă��������Ƃ��������ł���B�����āA����́A�w�z���̋����́x�ɕ`����Ă���̂Ƃ͂܂������ʂ̃��[���b�p���}�Ɍ����Ă���Ƃ������Ƃɂق��Ȃ�Ȃ��B
�@���e���ꂪ�q���Ռ�r�Ƃ��đ劈�n�߂�̂́A�J�g���b�N����̗͂���܂�A�x�d�Ȃ鐹���ʂ��āA�C�X�����������ň��N�ȏ�ێ�����Ă����M���V���N�w�[�L���X�g�����ł͓r������ւ�����悤�ɂȂ����M���V���N�w�ɁA���[���b�p�̐l�X���ӂ����ѐG���悤�ɂȂ������납��ł���B
�@�܂��͎��R�Ȋw�ł���B�X�R���h�̓V�����ɖ��������o�����R�y���j�N�X�B���ꂪ�������n�����́A�u�R�y���j�N�X�I�]��v�Ƃ����\���ɂ���悤�ɁA�l�ނ̂����Ƃ��傫�Ȕ����̈�ł���B���̃R�y���j�N�X�́A���̃|�[�����h�ɐ��܂ꂽ�B���\�N��A�K�����I���A�]�������g���ăR�y���j�N�X�̒n�����̐��������m���邪�A�A�K�����I�́A�R�y���j�N�X�̌̋��|�[�����h���������ꂽ�A���̃C�^���A�ɐ��܂ꂽ�B�܂��A�K�����I��i�삵��������l�̃P�v���[�́A���̃h�C�c�ɐ��܂ꂽ�B����ɐ��\�N��A�j���[�g�����K�����I�ƃP�v���[�ɐ��w�I�ȏؖ���^���邪�A�j���[�g���͊C�������̃C�M���X�Ő��܂ꂽ�B�R�y���j�N�X�A�K�����I�A�P�v���[�A�j���[�g���Ƃ����A�ߑ�Ȋw���H���������Ƃ��d�v�ȑ��̂�́A�|�[�����h�A�C�^���A�A�h�C�c�A�C�M���X�ƁA��!���b�p�S�y��傫���Z�����삯�߂��铹�̂肾�����̂ł���B�����āA�����݂͂ȃ��e����ŏ������B�\�����I�㔼�Ɋ����j���[�g���ł����܂����e����ŏ����Ă����̂�.����B |
164-165p
��\���I�ɓ����Ă���̎�����`�ɐ��ȉe����^�����A�L�F���P�S�[���͑�\�I�ȗ�ł���B�f���}�[�N�l�̃L�F���P�S�[���́A�h�C�c��ŏ������Ƃ��ł����ł��낤�ɁA�w�[�Q���N�w�̔ᔻ���A�킴�킴�f���}�[�N��œW�J�����B���̂����ŁA���O�͍L���ǂ܂�邱�Ƃ͂Ȃ������B�q���������̌��t�r�ŏ����̂ɌŎ��������߁A����̏�������������Ƃ��̂̂��x�Ȃǂ����������w�I�ȐF������тт����̂ɂȂ����Ƃ͂����悤�B
�����A����͎����̏��������t���ʂ����āq�ǂ܂��ׂ����t�r���ǂ����A�����Ă��邠�����ɍL�����E�ɖ₢�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ������̂ł������B
�@�������A�ł���B |
181p
�@�䂦�ɁA�q�ǂ܂��ׂ����t�r��ǂ݂��̂������Ȃ����Ƃ��A���ɓI�ɂ́A�����̔ے�Ƃ����C�f�I���M�[�ɂȂ���̂ł���B�����̔ے�Ƃ����C�f�I���M�[�̂��������̎�͋ߑ㐼�m�̃��[�g�s�A��`�ɂ���A����́A���n���Y����^�A�����I���Y�����҂Ǝ�������҂Ƃ̍����Ȃ������Ƃ���|�s�����Y���A�Љ�̋K�͂���܂��������R�ȁq��́r�̕��ۉ��ȂǁA���܂��܂Ȍ`���Ƃ��āA���m�ł������̔j��������Ă����B
�����A�m�ɂ����Ă̕����̔j��́A���m�Ƃ͔�r�ɂȂ�Ȃ������܂������̂ƂȂ����B�����̕�����v���͋M�d�ȕ������̑�����n������i���ɏ�������A�Ǐ��l��݂��グ�ĐJ�߂��B�J���{�W�A�̃N���[���E���[�W���ɂ������Ă͓Ǐ��l�����Ƃ��Ƃ��s�E�����B���{�̐��\�N�̍��ꋳ����A������v����N���[���E���[�W���Ɣ�ׂ悤�Ƃ����킯�ł͂Ȃ��B���Ƃ��ƕ��w�D���̓��{�l�ł���B���ꋳ���ʂ��ėD�ꂽ���w���q�������ɓǂ܂���w�͂͐��������A�D�ꂽ���w�ɐe���l�������炿�A�ꎞ���͂��̐��̏t�Ƃ��蕶�w�͉h�����B��Ƃ����͎E�����ǂ��납�u�����l�v�̑�\�Ƃ��đ傫�Ȋ�����Ă���ꂽ�B��Ƃɂ���Ă͑A�܂����قǂ̑�����ɂ��Ȃ����B�����A
���{�̍��ꋳ��̗��z���A�q�ǂ܂��ׂ����t�r��ǂލ�������Ă�Ƃ���ɐݒ肵�Ȃ������[���Ȃ킿�A�������p������Ƃ���ɐݒ肵�Ȃ��������䂦�ɁA�����o��ɏ]���A�������������Ɂq�ǂ܂��ׂ����t�r���ǂ݂���Ȃ��Ȃ��Ă������̂ł���B
�q�ǂ܂��ׂ����t�r��ǂ݂��̂𗝑z�Ƃ��Ȃ�����̈Ӗ��������ċɌ��܂œ˂��i�߂�A����͂�͂蕶���̔ے�ƌ��킴������Ȃ��B
�@�����͍��Ƃ̂��̂ł��Ȃ���A���͎҂̂��̂ł��Ȃ��B�������l�Ԃ̂��̂ł���B
������A��������̍���ǂ��Ă��A���Ƃ����Ď��������́q�ǂ܂��ׂ����t�r���p�����Ă������Ƃ���̂ł���B�u���܂悦�郆�_���l�v�ɂ������ẮA�����S�ڂ��ꂽ���Ǝ��ɓ��ܕS�N�ɂ킽���Đ��E���𗬘Q���Ȃ���������鋳�T�����͕̂悤�ɕ����ēǂ݂��A���������̕������p�����Ă����B
�@�����̕�����v���͈�}�ƍق̂��Ƃł����������Ƃł���B�N���[���E���[�W���̋s�E�����N�ɂ킽��A���n�x�z�A����ɑ��������s�����A����ɂ̓��F�g�i���푈�̔g�y���ʂ̂����ł����������Ƃł���B�������A���{�͐��\�N�̂������A���a�Ɣɉh�ƌ��_�̎��R�����A�m�炸�m�炸�̂����Ɏ���̎�œ��{��́q�ǂ܂��ׂ����t�r��ǂ܂Ȃ��������ĂĂ������̂ł���B�q�������t�r�̖{�����ǂނ��Ƃɂ���̂�ے肵�A�����Ƃ������̂��q�ǂ܂��ׂ����t�r��ǂނ��Ƃɂ���̂�ے肵�A���ɂ͋��ȏ�������≨�O��ǂ��o�����Ƃ܂ł����̂ł���B�����āA�N�ɂł��ǂ߂� |
380-381p
�O�̏��͂��A�����ւ��[���B�Ȃɂ���A�����́A�u���{����p���l�v�ł������A���{�ȂǂƂ����ɓ��̓����ɂ��ẮA���̒m�����Ȃ��B���ꂾ���ł͂Ȃ��B�m�����Ȃ��ǂ��납�A���{�l�ɂƂ��Ă͂��ꂾ���̈Ӗ��������������ېV���O���ɂȂ��B���{�Ƃ��������ǂ������m�̐A���n�ɂȂ��Ă���̂ɂ������Ȃ��Ǝv������ł���̂ł���B
�ނ�͐u���B�u�n���[�E�p�[�N�X���͓��{�̑��ł����������?�v�u���{�̑��͏I�g���ł�������?�v�u���{�͂��܃��V�A�̗̓y����������?�v�B���̂悤�ȁk���{����p���l�v�̖��m�́A���{�����m�̐A���n�ƂȂ�̂�Ƃꂽ�̂��A�����ɗ�O�I���������������Ă���邵�A�܂��A�����ېV�̂��Ƃ��A����@�g�����{���Ɨ����ł����邩�ǂ����J�����Ă����̂ƁA�ĉ�����B |
436p
���{�ꂪ�S�т�Ƃ�1�p��̐��I�̒��Łx�������O�ɓǂނׂ��������{������B�w�C�U�x���E�o�[�h�̓��{�I�s�x�B�C�U�x���E�o�[�h�Ƃ����E���ȉp���������s�Ƃ��A�����ېV����\�N��̈ꔪ�����N(�����\��N)�A�܂����m�l�����ݐl�ꂽ����
�̂Ȃ��Ԗk��k�C���Ȃǂ��������Ƃ��̎v����͂ɂ������̂����A���s�L���n�܂� |
455p
������Ғ���
�l��
(���\��)�����O�u�����ېV���\�ɂ������{�Ǝ��̊����P�Ǖ����[���W�@�����ÓT�̉b�q�Ɂ@�w�ԁv�w�������_�x�Z�����A��Z�Z���N�B���̏��_��ǂ݁A�u�����v�ɂ��Ă̂������́@�^�₪������0�܂��A�u�����v���u�Õ�(�O�[�E�G��)�v�Ƃ�Ԃ̂�m�����B
(���\�O)�R�������w���{��̗��j�x��g�V���A��Z�Z�Z�N�B�����P�ǂŃJ�^�J�i�̐�߂�n�ʁ@���ǂ����o�I�ɕω����Ă��������ɂ��āA���̖{�ŏ��߂ċ�̓I�ɂ킩�����B
(���\�l)�i�c�x��u�����̏W�Ƃ��Ắw���t�W�x�v�A�n���I�E�V���l�E��ؓo���ҁw�n�����ꂽ�@�ÓT�x�V�j�ЁA�����N�B
(���\��)��ؔ͋v�w�����̓��{��[�|��̗��j�x��g���X�A��Z�Z�Z�N�B
(���\�Z)�������ъێR�^�j�Z���u�|��̎v�z�v�w���{�ߑ�v�z��n�x��g���X�A�����N�B
(���\��)�ێR�^�j�E��������w�|��Ɠ��{�̋ߑ�x��g�V���A���㔪�N�B
��
(���\��)�w���F�鍳�x���A�o�[�T�EM�E�N���[�Ƃ����C�M���X�l�������������w�����カ�ҁx�@(�wWeiker Than a Woman�x)�����Ƃɂ����Ƃ����̂́A�x�[�q�Ƃ��������҂ɂ���ē�Z�@�Z�Z�N�ɔ������ꂽ�B
�Z��
(���\��)Kevin Kelly,"Scan This Book"The New York Times Magazine,May 14.2006.
(����\)����ɂ́A��Z��O�N�A�C���^�[�l�b�g��ʂ��A�č��̍��ƈ��S�ۏ�ǂ��c��Ȍl�@���𐢊E��������W���Ă��邱�Ƃ��킩�������A�����ł͂���ɂ��G��Ȃ��B
|
|