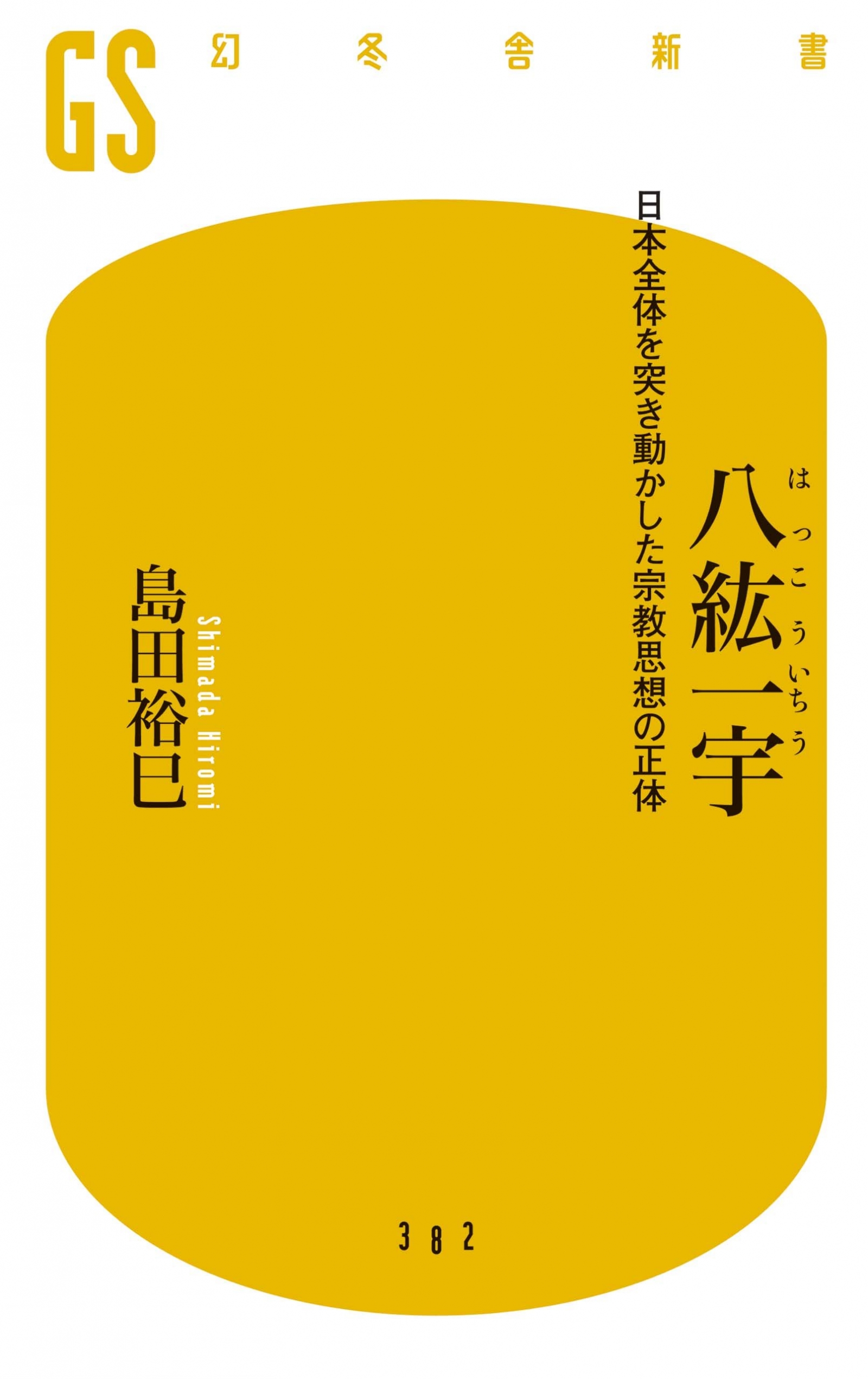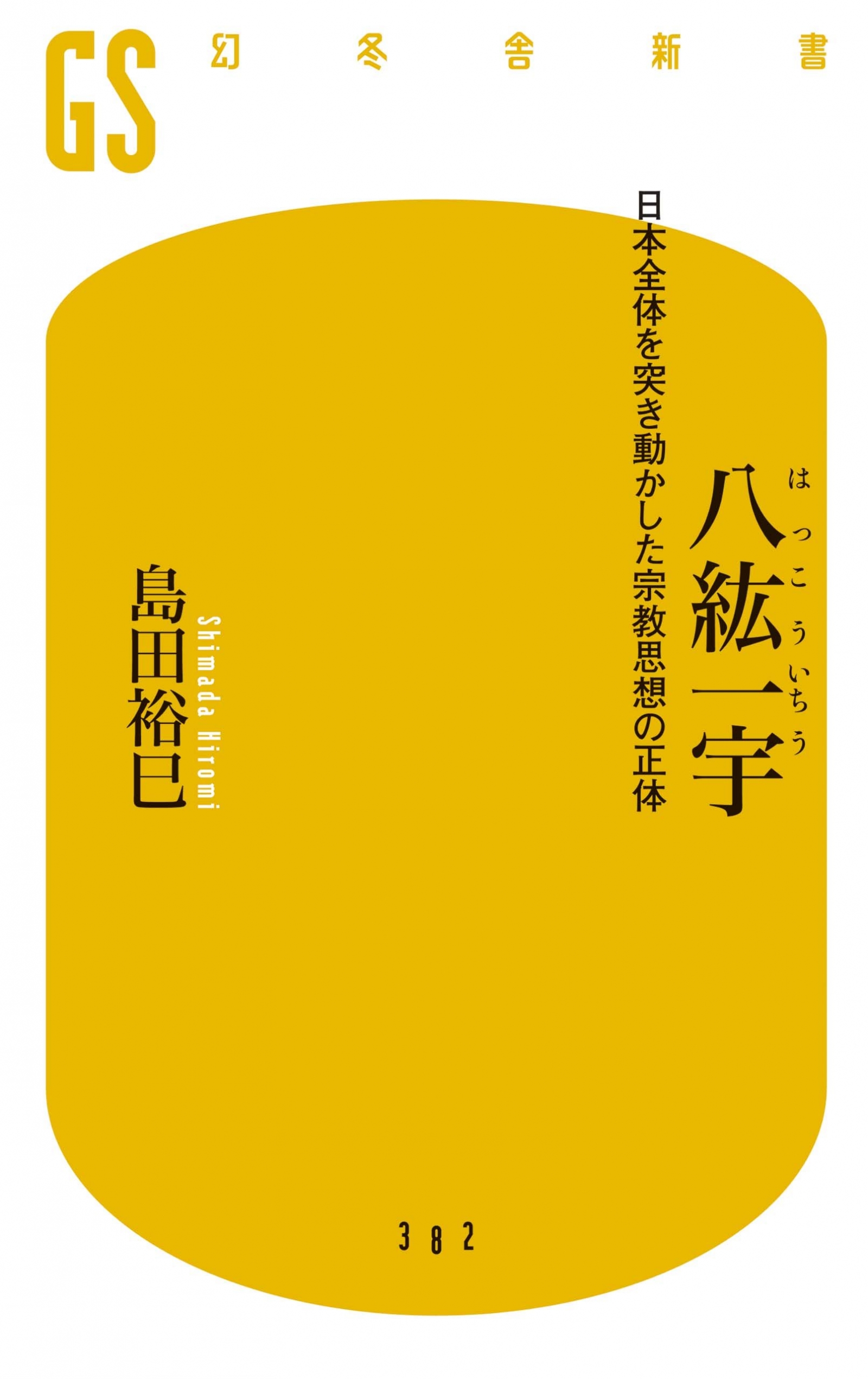�@�c���q�w�͔��h��F���u���`�I���E����v�ƈӖ��Â���
�@���h��F�̓������������a15�N�ɂ́A�哌�����h���̌��݂���W�Ƃ���7����11�Ɋt�c���肳�ꂽ�u��{�����v�j�v�`���́u���{���j�v�ɂ����āA�u�c���m�����n���h����F�g�X������(���悤����)�m�吸�_���L���E���a�m�m���������X���R�g���ȃe���{�g�V�v�Ƃ����`�ŁA���h��F�͍��Ƃ̕������������X���[�K���Ƃ��Č��I�ɔF�߂�ꂽ�̂������B
�@���E���Ƃ́A���߂č������Ă邱�Ƃ̈Ӗ��ł���A��̓I�ɂ͐_���V�c�̌����̂��Ƃ������Ă���B�_���V�c�́A�܂���h���炰�Ȃ���A���������a�ւނ����A�����ɁA�w���{���I�x�̕\�L���g���Ȃ�A�u���(�݂₱)�v��͂��߂��B�_���V�c�̑����炷��A����͍��ꂷ��̋ƂƂ������ƂɂȂ�B�����A�����̑ΏۂƂȂ��������炷��A����͐N������邱�Ƃ��Ӗ�����B���h��F�Ƃ������Ƃɂ́A��ɂ���������肪���܂Ƃ��Ă���̂ł���B
�@���h��F�Ƃ������Ƃ��ŏ��Ɏg�����̂́A���@��`�҂ŁA���Ǝ�`�I�ȏ@���c�̂ł��鍑�����g�D�����c���q�w�ł���B�c���́A�吳H(1922)�N�Ɋ��s���ꂽ�w���{���̂̌����x(�V�Ɩ���Њ��A��������}���ًߑ�f�W�^�����C�u�����[�Ō��J)�̖`���Ɏ��߂�ꂽ�u�錾�v�̂Ȃ��ŁA�u�V�c�͔V�������āw�V�떳���x�ƌ����A���c�͔V��`�ւāw���h��F�x�Ɛ邷�v�Ƃ����`�ŁA���h��F�Ɍ��y���Ă���B�V�c�͓V�Ƒ�_(���܂Ă炷�����݂���)�̂��ƂŁA���c���_���V�c�̂��Ƃł���B�����āA���̖{�̑�\�l�͂̃^�C�g���h��F�Ƃ��Ă���B�����A���̏͂�4�łقǂ̒Z�����̂ŁA���h��F���߂����āA�쒆�͏ڂ����E�_��W�ԁ[�Ă����̂Ă��Ȃ�,�@���̏͂œc���́A�u���`�I���E����v�Ɓu���N���I���E����v�Ƃ���ʂ�����ŁA���h��F�`�I���E����Ƃ��Ę_���Ă���B
�@���E�l�ނ��Ҍ��Ƃ��Đ��ꂷ��ڈ��Ƃ��Ē��F�𐢊E�I�ɐ�`����A������ЁX���w����R���āA�l�ނ𒉍F������g�������{�����̓V�E�ł���A���̌����͓��X����l�ވ�@�̐��ς��甭���Č��P�W������啶���ł���A����ōs(��)�萋���悤�Ƃ��Ӑ��E���ꂾ�A�̂ɔV���u���h��F�v�Ɛ錾����āA���F�̊g�[��\�z����Ă̌��_���A���E�͈�Ƃ��Ƃ��ӈӋ`�ɋA����B
�@���́A�Ɛb�A�b������N�ɑ��Ē����ł��邱�Ƃ��Ӗ�����I�ȓ����ϔO�ŁA�����ł͓V�c�ɑ��钉���z�肳��Ă���B�F�́A����ɑ��Ďd���邱�Ƃ��Ӗ����A���F�́A���{�l�̓����̂����Ƃ��d�v�Ȋ�ՂƂ���Ă����B��������c���́A���N���I�ł͂Ȃ��A���`�I�Ȑ��E����Ƃ����l�������o���Ă���킯�ł���B���̘_���́A���łɌ����w���h��F�̐��_�x�Ƌ��ʂ��Ă���B���{�ɂ͔��h��F�̐��_�ɏ]���āA���E�ꂷ��`�������邪�A����͒��F�Ƃ����������I�ȈӋ`�ɂ��Ƃ����̂ł��邩��A���N���I���E����ɂ͂�����Ȃ��Ƃ����̂ł���B�@�i�Q�W�`�Q�X�Łj
�@�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�@���{�����̊e�@�h�ɂ����āA�m���Ƒ��M�k�Ƃ̋����������Ƃ��߂��̂���y�^�@�̏ꍇ�ł���B��y�^�@�ł́A����ɕ��̐�ΐ�����������A�M�k�ł���ΒN���������邱�Ƃ��ł���O���̎��H�ɒ��S��������Ă��邽�߂ɁA�m���ɑ��ē��ʂȒn�ʂ͗^�����Ă��Ȃ��B����������y�^�@�̑m���͏o�Ƃł͂Ȃ��̂ł���B
�@����Ɏ����ŋ������߂��̂����@�@�̏ꍇ�ł���B�J�c�̓��@�́A�V��@�ɂ����ďo�Ɠ��x�����m���ł���A���U���̗�����т����B�������A���@�������Ƃ��S�𒍂����̂́A�@�،o�ɂ����߉ނ̐^���̋�����������Ă��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ��A�����ے肷�鑼�̐M���Љ�ɂ͂т���̂�j�~���邱�Ƃł������B
�@���������āA���@�͍ĎO�A�ނ̗��ꂩ��͌�������@�ł���u�ق��@(�ق��ڂ�)�v�̎����܂���א��҂ɋ��߂��B���@�́A�l�̋~�ςƂ������Ƃɂ͊S���������A�����̎Љ�̂������ς��邱�ƂɊ����̒��S���������B���̂��ߑ��̏@�h�Ƃ͈قȂ�A���@�@�̑m���́A�{���͓��@�̂悤�ɎЉ��ς��邱�Ƃɖz�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł���B�i�T�O�`�T�P�Łj
|
�c���q�w�́u�@�������v�Ɠ��@�́u�O���@���v
�@�q�w�����������l�����m�ɂ����̂��A�u�{�����@���ځv�ƌĂ��ޓƎ��̋��`�̑̌n�ɂ����Ă������B42�ɂȂ����q�w�́A����35(1902)�N��8������9���ɂ����āA���q�ɂ��������ւɂ�����A��C�ɂ���������������B�q�w�́A1�N�����āA������u�`���A���̍u�`�^�́A�w�{�����@���ڍu�`�^�x�S5���ɂ܂Ƃ߂�ꂽ�B
�@�����Œq�w�����������̂��A�u�@������(�ق������݂�������)�v�Ƃ����l�����ł������B���̖@�������Ƃ������Ƃ́A�q�w���Ǝ��Ɏg�������̂ŁA��ʂɂ́A�u��������(�����Ԃ݂悤����)�v�ƌĂ�邱�Ƃ������B�����Ƃ́A�����̖@�ł��鉤�@�Ǝ߉ނ̐��������@�������A���ꂪ��ɗZ������邱�Ƃ����������ł���B�q�w�̖@���������A�Ӗ�����Ƃ���͓����ł���B
�@�@�������������������A�Ƃ��ɂ��̍����́A���@�̈╶�A�u�O���@���v�ɋ��߂��Ă���B
���́u�O���@���v�́A�u�O���@�g����(�ڂ悤��)�v�Ƃ��Ă�A�O��4(1281)�N4��8���ɍb�㍑�g��(�݂̂�)�Ŏ��M���ꂽ�Ƃ���Ă���B���̂Ƃ����@��60�ŁA�S���Ȃ�̂͗��N��10��13���̂��Ƃł������B
�u�O���@���v�����M���ꂽ���_�ŁA���@�͂��łɕa�ɋꂵ��ł���A�܂Ƃ܂������_�I�ȕ��͂��������Ƃ��v���Ȃ��̂����A���e�I�ɂ��A�{���ɓ��@�̎�ɂȂ���̂Ȃ̂��ǂ����A���@�̋������w�Ԏ҂����̂������ł͐̂���c�_�ɂȂ��Ă����B
�@���@�́A�c��ȕ��͂��c���Ă��邪�A���̂Ȃ��ɂ́A�u�^�M�v�A���邢�́u�^�ցv�ƌĂ�A���@���M�̂��̂��c���Ă�����̂�����A�ʖ{�ł����c���Ă��Ȃ����̂�����B�u�O���@���v�́A�ʖ{�ł����c���Ă��炸�A���̎ʖ{���A15���I�͂��߂̂��̂������Ƃ��Â��B���̎��_�ł͂��łɁA���@���S���Ȃ��Ă���S���\�N���o���Ă����B�i�T�Q�`�T�R�Łj
|
�@���́A�{������d�ł���B���d�Ƃ����̂́A��ʓI�ɂ́A�m���A���邢�͓�m�ɑ��ĉ����������邽�߂̒d�̂��Ƃł���B�L���Ȃ��̂Ƃ��ẮA���厛�ɐ݂���ꂽ���d������B����́A�ޗǎ���̏I���ɓ����珵���ꂽ�Ӑ^(����)���������Ă���݂���ꂽ���̂ł���B����܂ŁA���{�ɂ͐����ɉ����������鎑�i�����u���t�v�����Ȃ������B�����炱���Ӑ^�������ꂽ�킯�����A�����ɁA�����t���Ƒ��ɕ{�ϐ������ɂ����d���݂����A�����ɑm���ɂȂ邽�߂ɂ́A�����������d�ʼn����������鐧�x���m�����ꂽ�B�i�T�S�`�T�T�Łj
|
�@�Ȃɂ��땑��́A���a�����̖��B���ɑn�݂��ꂽ������w������ł���B������w�́A���݂̑�w�ŁA���B���̍������i�閞�B�������@�����̍�����w�ł���A����Ɨ��̂��ꂽ�B�n���͏��a13(1938)�N5���ŁA���B��������20�N8���ɕ�����Ă���B���傪�����������Ԃ͒Z�����̂́A���v�Ŗ�1400�����ݐЂ����B
�w���F�̃g���c�L�[�x�́A���̌���ɁA���{�l�ƖÐl�̍����ł���E���{���g�Ƃ����N�����w���Ă���Ƃ��납��͂��܂�B�E���{���g�́A�c�����ɉƑ����s�E���ꂽ�B�����炭�͂��ꂪ�����Ȃ̂��낤�A�ߋ��̋L���������Ă��܂��Ă���B
�@����̖`���ɂ́A�E���{���g�̉Ƒ����s�E������ʂ��o�Ă���̂����A���́A�ނ͋s�E�����Ɛl�̊���o���Ă���B���̊�́A���V�A�̊v���ƁA���t�E�g���c�L�[�Ɏ��Ă���̂������B
�w���F�̃g���c�L�[�x�ɂ́A�E���{���g�₻�̕��e���͂��߂Ƃ���ˋ�̐l�����o�ꂷ�����ŁA�֓��R�Q�d���Ō�̎A�����p�@��֓��R���Q�d�Ō���̐ݗ���C�A�Ґ��M(���܂��̂�)�A�����{��`�҂̑吙�h(��������������)�Ȃǂ��E�Q���A����������A���B�f�拦��������Ƃ߂��Ô����F(���܂����܂��Ђ�)�A���C���̑n�n�҂Ő�O��2�x�e�������V�@���̑�{�̐M�҂ł���A����Ŏw�������A�Ő���(����������ւ�)�A�j���̗�l�Ƃ��Ė���y�����쓇�F�q(���킵�܂悵��)�A�����ĉ̎�ŏ��D�̗�����(�肱�����)(���͎R���i�q(��܂����悵��)�Ƃ��ĎQ�c�@�c�����Ƃ߂�)�ȂǁA�����[�����݂̐l�����������o�ꂷ��B
�@�������A����̂Ȃ��ŁA���|�I�ȑ��݊��������Ă���̂��Ό��Ύ��ł���B�Ό��́A����薞�B���ς̎�d�҂Ƃ��Ēm���Ă���B�Ό��́A������(��䂤���悤��)�������N�����āA���{�����B�ɂ����ČR���I�ɓW�J���邫�����������A�֓��R��C�Q�d�Ƃ��Ċ֓��R�����B�S�y���u���Ԃɐ������邱�Ƃɍv�������B����́A���́A���̐Ό��́u�A�W�A��w�v�\�z�����������ɂȂ��Ă����B�i�X�O�`�X�P�Łj
|
�@�Ό��̍�����Ƃ̂������́A���������͂邩�ɐ[�������B�Ƃ��ɐΌ��́A�������n�������c���q�w�̎O�j�ŁA���{���̊w���n�����������ݗY�Ɛ[���𗬂��Ă����B���{���̊w��͌��݂��������A�@�֎��ł���w���̕����x�̕���27�N5�����ł́A�u�͂��߂Ɂv�łӂꂽ�O�������q�c���̔��h��F�������āA�u���h��F���l����v�Ƃ������W��g��ł���B
�@�Ό��ƁA�q�w�����������@��`�Ƃ̊W������1���̎ʐ^���c����Ă���B
�@���a7(1932)�N2��16���A��V(���E�˗z)�ŁA���ؖ����̐����ƁA�R�l���������i(���悤����)�A�n��R�A���~�B�A����(������)���W�܂��āA���k�s���ψ����������B�����ɂ́A���{������A���������������Ό��̂ق��ɁA�{����(�ق悤������)�֓��R�i�ߊ��A�_���l�Y�卲�A�Бq��(������)��тȂǂ��o�Ȃ��Ă����B
�@���̂Ƃ��̋L�O�ʐ^���c����Ă���킯�����A�o�Ȏ҂����ԉE���ɂ́A�u�얳���@�@�،o�v
�̑�ڂ�发�������̂��f�����Ă����B����́A���@�ɓ����I�ȏ��̂ł���B2��16���́A���̓��@���a���������ł��������B�����p�ӂ����̂́A�ԈႢ�Ȃ��Ό��ł��낤�B���k�s���ψ���́A���B�̒�������̓Ɨ����������A���B�����������Ă������A���̎ʐ^�ɂ́A���̖��B���Ɠ��@��`�Ƃ̐[���W����������Ă���B�i�X�S�`�X�T�Łj
|
�{������
�@�����ɂ��ẮA��J�h��́w�ߑ���{�̓��@��`�^���x���ڂ����B�����́A�U�A�@�̈�h�ł��閭�����h�ɑ����Ă��āA���c�̋ߑ㉻���߂������B24��(����22�N)�̎Ⴓ�ŋ��w�����ɏA�C�������̂́A�@���̕ێ�h�ƑΗ����A2�N��ɂ͋��w�������ƁA����ɂ��̗��N�ɂ͑m�Ђ܂Ŕ��D�����B
�@�������A�����́A�u���{�@�؏@�O�ʏ��v������āA�����������̋��_�Ƃ���B�@�h�̓����ł��A�����������悤�Ƃ��铮�����N����A����27�N�ɂ͑m�Ђ����Ă���B����ȍ~�A�����́A���ԂƂƂ��Ɍ��������u���@����c�v����ՂɊ�����W�J����B���̓���c�ɂ́A�������h�̑m�������ł͂Ȃ��A��ʂ̒h�M�k���Q�����A�G���̔��s�A������̊J�ÂȂǂ��s�����A���̖ړI�́A�g�D�̖��O�������Ă���悤�ɁA���@�剺�̋��c�����A����ɂ͕����E�S�̂ꂷ�邱�Ƃɂ������B
�@�����͏@�����ĂɏA�C���邪�A�������h�́u���{�@�؏@�v�Ɖ��̂����B�����́A����38�N�ɁA���̌��{�@�؏@�̊ǒ���39�̎Ⴓ�ŏA�C���Ă���B�q�w���ґ����A�݉Ƃ̓��@��`�҂Ƃ��Ċ��������̂ɑ��āA�����́A��т��ďo�Ƃ̗��ꂩ��^����W�J�����B
�@�������A���@�@�̏ꍇ�ɂ́A��y�^�@�قǂł͂Ȃ��ɂ��Ă��A�o�Ƃƍ݉Ƃ̗���͐ڋ߂���
����B���ۓ����ƒq�w�́A���܂��܂ȏ�ʂŋ��͂��Ċ�����W�Ԃ��A���F�Ƃ�������W�ɂ������B���Ƃ��A����35�N4���ɂ́A�u���@���l�J�@��650�N�L�O���v�������J�Â��Ă���B
�@�Ό��́A�����́w���@���l�̊����x��ǂ����ł͂Ȃ��A���̎��̔N�A�吳9�N1���ɂ́A����t(�Ƃ�������)�ɂ����ނ��āA�����ɂ��u�Љ�����Ɠ��@��`�v�Ƃ����u���������Ă���B��_�^���ɂ��A�u�������N����吳���N�ɂ����Ė{���̍u���͑��@�h�̊w�������������ɍs���A�H��Ȃǂ̏���u�������āA���̏@���w���ɂ͓c���q�w�����]�����������������ł���v
(�w���ɂ�w�����ĊX���ցx��g�V��)�Ƃ����B��2�͂ŁA�q�w���ِ�̍˂Ɍb�܂�Ă������Ƃɂ��Ăӂꂽ���A�����͂���ȏ�̍˔\���������ƂɂȂ�B
�@�������A�������m�E�ɂ��������炩�A�Ό��͂���ȏ�A����t�̉^���ɂ͊S�������Ȃ������B2���ɂȂ�ƐΌ��́A�_�c�̌Ï��X�ŁA�����̎���ɂ��̓��@�W�̕��͂��W�߂Ċ��s���ꂽ�w���R�����Ɠ��@��l�x���A�����̐������@�̍��ƊςɊ������Ă���B���L�ɂ́A�u���̓��ۂ͕ʂƂ��ēO��I�Ȃ邱�Ɨ���(������)�͓V�˂̐l�Ȃ�v(2��8��)�ƁA�����̓��@�_�������]�����Ă����B
|
�@�O�l�̐l���Ƃ́A�����O���A�|���v��(���������Ђ�����)�A�o�萳���ł���B�����炭�A�����̐l�͂����̖��O�������Ƃ��Ȃ����낤�B
�@���̂Ȃ��ň�ԕ�����₷���̂��A�����O���ł���B�����́A���{�̑�\�I�ȃf�p�[�g�����g�X�g�A�A�ɐ��O�̑n�Ǝ҂ł���B�ɐ��O�́A����������19(1886)�N�A�����{�_�c�旷�Ē�2����4�Ԓn(���݂̐��c��O�_�c-����5��)�Ɉɐ����O�������X���J�������Ƃɂ͂��܂�B���a5(1930)�N�ɂ͊�����Јɐ��O�𖼏��悤�ɂȂ�A��8�N�ɂ͌��ݒn�̐V�h�ɓX���ڂ��Ă���B
�@���̏����̒q�w�Ƃ̊W�ɒ��ڂ����̂��A�l�ފw�҂̎R�����j�ł���B�R���́A�w�u�s�ҁv�̐��_�j�x(��g���X)�̂Ȃ��ŁA�q�w�̎O���q�Ƃ��āA�����A�Ό��A�����������A���̎O�l�̖��O���W�ŏI��邱�Ƃ���A�u�O�W�v�ƌĂ�ł���B
�@�q�w�́A����43�N�A�É��O�ۂ̏����ɍŏ��t�����āA�����Ɋ����̋��_���ڂ����A���̂Ƃ��A�����ɂ͏Z�����Ȃ��A�����ɕs�ւ������B���̂��ߏ����́A�Ō������ɂ��������@�̕~�n���Ɉꉮ�����āA�����q�w�̈�Ƃɒ����B�����̓@��́A���Ƃ��Ƃ͈ɓ����������Ă����̂ŁA�~�n�̍L����550���������B
�@����ɏ����́A�u�������݂��A�_�c���Ē��ɂ������ɐ��O�����X�ŁA�c���t�̍u��������J�Â��A�����̓��@�@�̐M�҂����܂��ĕ������B���Ȃ݂ɁA���O��������̐M�O���������A����̐����̌����������Â����v�Ƃ���(�y�����Y�w�n�Ǝҏ����O���x�ɐ��O)�B�i�P�P�U�`�P�P�V�Łj
|
�@���@�́A�w���������_�x�̂Ȃ��ŁA���{�����������@��Ȃ���A�C�O�̐��͂���U�߂���u�����N�N��v���N����ƌx�����A�̂��̖ÏP����\�������`�ɂȂ������A�k�̓C�M���X�ƃh�C�c��ÂɂȂ��炦�Ă����B�w�x�ߊv���O�j�x�̑�20�͂́A�u�p�Ƃ̌����P���v�Ƒ肳��Ă���A�����ł́A�u�������ē��ĊJ��Ɏ���Δ��l�̑Γ������R�Ǝx�߂̋��|�I���͂ɂ��ē��{�̖ŖS�͈�N���o�ł��B����r�S�x�߂̊v���ɂ����č�̌��鏊�Ȃ��A�����Â�ɉ��F���̌���҂��͂��邢�͉p�I���N�̈ېV�O�ɋA�ւ肠�邢�͂Ђɉp�ƒ�g�̌����P��������v�Ƃ����x�����������Ă����B�C�M���X�ƃh�C�c�̖����������Ă���̂́A�k���A���̗����ɒ�����C���h�V�i�ւ̐N�U�̈Ӑ}������Ɛ������Ă�������ł���B
�@�����������Ԃ܂��A�k�́A���Ă̐��͂ɑ��ĕ��͂őR���邱�Ƃ������i���Ă���B
���Ƃ��A�u�w�E���������Ȃށx���̂ɂ��炸��Έ������ނ�̎��R���a�Đ��`�̎��R�Ȃ锭����i��}�A���邠���͂��v�Ƃ�����ɂł���B
�@���̍ۂɁA�k�́A�u���v��퓬�I�ȏ@���Ƃ��ĂƂ炦�A������A�O�G�ɑ��ē��Ȏp����������L���X�g���ƑΔ䂳���Ă���B�k���g�̂��Ƃł́A�u���̔�����̂��鎞�A���𗦂�Ĕ����̎͂����������[�[�̗r�Q�Ƌ��ɘQ�X���肵�Ď�Ȃ�L���X�g���̂��Ƃ��A���߂ׂ̈̐ܕ������ӂ镧�̑��̓R�[�����ƌ������Ă�C�X���������܂��y���邲�Ƃ��v
���Ƃ����̂ł���B
�@�k�́A�w�x�ߊv���O�j�x�̍Ō�̕����ł́A�u�s�т̓I�S�f�C������ׂ��p�Y��q�˂đN���̃R�[������������v�Əq�ׁA�@�،o��N���̃R�[�����ƂƂ炦�Ă���B���̎���ɂ�(����ȍ~����������)�A�C�X�����������̐��������A�̓y���g�����邽�߂̐킢��簐i�������Ƃ���A�u�����A�R�[�������v�������t�Ƃ���퓬�I�ȏ@���ł���Ƃ����C���[�W�����z���Ă���A�k�͂���܂��Ă����B
�@����ɖk�́A���p�푈�Ƃ������`���Ƃ鐢�E��킪�A�v����U�����邱�ƂɂȂ�Ƃ��āA�푈���n�k�ɂ��Ƃ��āA�u�o���ɑ�n�k�Ēn�N�̕�F�̏o�����邱�Ƃ����ӁB��n�k��Ƃ͉߂��鐢�E���̂��Ƃ��A����A���鐢�E�v���̂��Ƃ�����ł���B�n�N��F�Ƃ͒n���w�ɖ����~��̌Q�Ƃ��ӂ��ƁA���Ȃ͂��ݖ�̉p�Y���w�K���̋`���̐l�̋`�ł���v�Əq�ׂĂ���B�����Ō�����n�N��F�Ƃ́A�@�،o�́u�]�n�N�o�i(���䂤���䂤����ق�)�v�ɏo�Ă�����̂ŁA�k�͂�����v���̐�m�ɂ��Ƃ��Ă���킯�ł���B(�P�T�S�`�P�T�T��)
|
�@�N���I�ȐM�ƌ����ƁA�\�͂ɂ���ĐM���L�߂邩�̂悤�Ȉ�ۂ��邪�A�q�w�́A�N���Ƃ������Ƃ̈Ӗ����L���g���Ă���A�u�����͂��ׂĐN���Ȃ�v�Ƃ܂Ō������Ă���B
�܂�A�����鑶�݂́A���̐������ێ������ɂ����āA���̑��݂�N������Ȃ��킯�ŁA���̓_�ŐN�������݂̖{���Ƃ��ĂƂ炦���Ă���킯���B���̏�ŁA�u�P�N���v�Ɓu���N���v����ʂ���A�u�@�،o�I�N���v�͑P�N���ł���Ƃ���Ă���̂ł���B
�@����ɒq�w�ɂ́A��2�͂ł��q�ׂ��悤�ɁA���@�́w�ϐS�{�����x�����ƂɁA�V�c���u�����v�Ƃ��ĂƂ炦�鎋�_���������B�q�w�́A�����푈���u�������ۂɁA�폟�F������邽�߂̍�������c��ł��邪�A���̍ۂɓǂ܂ꂽ�u��������`�v�ɂ����āA�����V�c���u���E����m�����v�Ǝ]���Ă���B
�@�������v�́A���������q�w�̖k�ɑ���e�����w�E������ŁA�����V�c�M���m�����ꂽ���ƂŁA�k�ɂ����āA���h��F�̍l�����Ɍ��т��Ƒ����Ɗς��m�肳��Ă������ƂƂ炦�Ă���B�������ɁA�w�x�ߊv���O�j�x�ɑ����w���{�����@�đ�j�x�̂Ȃ��ŁA�k�́A�u���{�����̍��Ɗς͍��Ƃ͗L�@�I�s���Ȃ���Ƒ��Ȃ�v�ł���Əq�ׂĂ���(�����w���@�����̎Љ�v�z�I�W�J�|�ߑ���{�̏@���I�C�f�I���M�[�x������w�o�ʼn�)�B
�@�������A�����p�������Ƃ́A�����́u���Ƃ̌����v�ɏo�Ă�����̂ł͂��邪�A�����ɂ����o�Ă��Ȃ��B�k�́w���{�����@�đ�j�x�̑S�̂�ʂ��āA���̂悤�ȍl�������q�ׂĂ����i�P�T�V�Łj
|
�@����܂ł��ӂ�Ă����悤�ɁA�@�،o�ɂ́u�s�ɐg���v�Ƃ������Ƃ��o�Ă���B����́A�M�̂��߂ɂ͎����̖����ڂ݂Ȃ��Ŏ̂Ă�Ƃ������Ƃ��Ӗ�����B���ہA���@�́A����̎咣���Ȃ��邱�ƂȂ��A���X�̖@��ɑ����Ă����B���̕s�ɐg���̍l�����́A����̎咣�Əd�Ȃ肠�����̂�����A�₪�Ĉ������������Ă����B
�@�������N����2�N�O�̏��a5�N8��29���ɏ㋞�����Ƃ��ɁA���́A�u���B�����(�̂낵)�������A����ɂ�Ďw���K���̊o���𑣂��ޓ��̎�ɂ�ĉ��������i�K��ɓ��ݏ��ŏ��͖ܘ_�ɂ߂ĕs�O��Ȃ��̂ɂ��܂ċ��邪�����đ��A��O�i�Ɠ]�J���čs���̂͋ɂ߂ėe�ՂȎ��ł���v�Ƃ����F���ɒB���Ă����B�����āA�u�悵�A����������̌��Ӓʂ莀�˂悢�̂��A�厀��Ԃ�!�v�ƁA�ÎE�Ƃ�����i�������(�w�����c������\���A������L�x)�B
�@�N���܂ɂȂ肳������A��͎����I�ɉ����������Ă����Ƃ����̂́A���ʂ��Ƃ��Đ����ƊÂ��悤�ɂ�������B���������˂A���ׂĂ͂��܂������Ƃ����l�������A���܂�Ɏ��Ȓ��S�I������B
�@�������A�����ɂ́A�����c�����ɑ����A�܁E��������N����A����͂���ɓ�E��Z�����ւƔ��W���Ă������̂�����A���̍l�����Ƃ���ɂ��Ƃ͐i��ł������Ƃ�������B
�@����ɁA������A�����c�ɉ�����Ă����ʂ̃O���[�v���������B���ꂪ�A�����鍑��w�Ƌ��s�鍑��w�̒�吶�����ł������B�R�̏��Z�������G���[�g�ł��������A�ނ���G���[�g�ł���A�����썑���֏W�܂��Ă����l�Ԃ����Ƃ͎Љ�K�w���܂������قȂ��Ă����B
�@�����́A�_�Ƃ̏o�g�ŁA�������w�Z�����Ƃ��Ă��炸�A�E�l�̌��K���Ȃǂɂ����Ȃ�Ȃ������B�H�����_�Ƃ̏o�g�ŁA��q�S���w�Z�𑲋Ƃ��Ă�����̂́A�ڂ̕a�C�ŏA�E���ł��Ȃ������B�ނ�́A�����ăG���[�g�Ƃ͌����Ȃ��l�Ԃ����������B
�@��吶�̒��S�ɂ������̂́A��㐭�E�̍����ƂȂ�A���̑����̎w����Ƃ��Ȃ�l���`���������B
�@�l���́A�������̏o�g�ŁA�n���̎����ɐi�w���邪�A�����ł�͂茌���c�ɉ����r�ܐ��ژY�ƒm�荇���A���Ԃ����āA�u�h�V��v�Ƃ����A���{���_�̔��g�Ȃǂ�ړI�Ƃ����C�{�c�̂���������B�i�P�V�W�`�P�V�X�Łj
|
�@���������A�H���������u�_��I�ÎE�v�������Ȃ���̂Ȃ̂��́A���ꂾ���ł͔��R�Ƃ��Ȃ��B
�����A�c���ÎE���邱�Ƃɂ���āA���Ȃ̑��݂m�Ɉӎ������A����ɔ����đ��҂𑼎҂Ƃ��ĔF�������̂��Ƃ���A�����ɂ͕H���̎��Ȏ����̉ߒ������������ƂɂȂ�B
�@���@�̋����̂Ȃ��ł́A�@�،o�̒��j�ɂ́A�V��q �@���������A�H���������u�_��I�ÎE�v�������Ȃ���̂Ȃ̂��́A���ꂾ���ł͔��R�Ƃ��Ȃ��B
�����A�c���ÎE���邱�Ƃɂ���āA���Ȃ̑��݂m�Ɉӎ������A����ɔ����đ��҂𑼎҂Ƃ��ĔF�������̂��Ƃ���A�����ɂ͕H���̎��Ȏ����̉ߒ������������ƂɂȂ�B
�@���@�̋����̂Ȃ��ł́A�@�،o�̒��j�ɂ́A�V��q �@���������A�H���������u�_��I�ÎE�v�������Ȃ���̂Ȃ̂��́A���ꂾ���ł͔��R�Ƃ��Ȃ��B
�����A�c���ÎE���邱�Ƃɂ���āA���Ȃ̑��݂m�Ɉӎ������A����ɔ����đ��҂𑼎҂Ƃ��ĔF�������̂��Ƃ���A�����ɂ͕H���̎��Ȏ����̉ߒ������������ƂɂȂ�B
�@���@�̋����̂Ȃ��ł́A�@�،o�̒��j�ɂ́A�V��q�����q�ׂ��u��O�O��v��u�\�E��(����������)�v
�̍l����������Ƃ��ꂽ�B��O�O��́A�������̈�O�̂Ȃ��ɎO���琢�E�����̂܂܊܂܂�Ă���Ƃ������̂ŁA�\�E����A���ꂼ��̐��E�ɂ͒n���E�����F�E�܂ł��ׂĂ̐��E��������Ă���Ƃ����l�����ł���B���邢�́A�H���́A�ÎE�̏u�ԂɁA���̓��@�����������E��̌������̂�������Ȃ��B
�@�@�،o��ǂݑ�ڂ�������Ƃ����s�ׂ́A��������H����҂��x���Ƃ������n�ɓ����Ă����B
�H���́A�ÎE��ʂ��Ă���������Ԃ��o�����Ă������B�ʂ����Ă��ꂪ�A���̈ÎE�҂ɋN���邱�ƂȂ̂��ǂ����͕�����Ȃ����A����ɂ���ĈÎE�Ƃ����s�ׂɂ͏@���I�ȈӖ����^����ꂽ���ƂɂȂ�B
�@�����c�ƌĂꂽ���𒆐S�Ƃ����e�����X�g�̃l�b�g���[�N�́A�����c�����ɂ���ĉ�̂���A���s�Ƃ���Ȃǂ͍��ɂȂ���邱�ƂɂȂ�B�������A���łɏq�ׂ��悤�ɁA�Y���̂��y��������ɁA���͂ɂ���ĊF�o�����Ă���A�ނ�͑����m�푈���O�̓��{�Љ�ɗ����߂��Ă������B
�@�l�����A���E�̍����Ƃ��Đ��Ɋ������Ƃɂ��Ă͂��łɂӂꂽ���A�����A�u�썑�c�v�Ƃ����c�̂��������Ċ����𑱂����B�������A�ƊE���_�ЂƂ����o�ŎЂ����Ȃ���A�E�������𑱂����B�H���ɂȂ�ƁA�����ܘN�Ɖ������A��錧�c��c���ƂȂ��Č��c��c���܂łƂ߂��B�e�����X�g�́A���̓��{�Љ�Ɏ����ꂽ�̂ł���(�{�͂ɂ��ẮA�����x�u�w�����c�����x�q���Y�t�H�r�A�x�^���w���c�łƓ��{�t�@�V�Y���^���x�q��g���X�r���Q�l�ɂ���)�B���q�ׂ��u��O�O��v��u�\�E��(����������)�v
�̍l����������Ƃ��ꂽ�B��O�O��́A�������̈�O�̂Ȃ��ɎO���琢�E�����̂܂܊܂܂�Ă���Ƃ������̂ŁA�\�E����A���ꂼ��̐��E�ɂ͒n���E�����F�E�܂ł��ׂĂ̐��E��������Ă���Ƃ����l�����ł���B���邢�́A�H���́A�ÎE�̏u�ԂɁA���̓��@�����������E��̌������̂�������Ȃ��B
�@�@�،o��ǂݑ�ڂ�������Ƃ����s�ׂ́A��������H����҂��x���Ƃ������n�ɓ����Ă����B
�H���́A�ÎE��ʂ��Ă���������Ԃ��o�����Ă������B�ʂ����Ă��ꂪ�A���̈ÎE�҂ɋN���邱�ƂȂ̂��ǂ����͕�����Ȃ����A����ɂ���ĈÎE�Ƃ����s�ׂɂ͏@���I�ȈӖ����^����ꂽ���ƂɂȂ�B
�@�����c�ƌĂꂽ���𒆐S�Ƃ����e�����X�g�̃l�b�g���[�N�́A�����c�����ɂ���ĉ�̂���A���s�Ƃ���Ȃǂ͍��ɂȂ���邱�ƂɂȂ�B�������A���łɏq�ׂ��悤�ɁA�Y���̂��y��������ɁA���͂ɂ���ĊF�o�����Ă���A�ނ�͑����m�푈���O�̓��{�Љ�ɗ����߂��Ă������B
�@�l�����A���E�̍����Ƃ��Đ��Ɋ������Ƃɂ��Ă͂��łɂӂꂽ���A�����A�u�썑�c�v�Ƃ����c�̂��������Ċ����𑱂����B�������A�ƊE���_�ЂƂ����o�ŎЂ����Ȃ���A�E�������𑱂����B�H���ɂȂ�ƁA�����ܘN�Ɖ������A��錧�c��c���ƂȂ��Č��c��c���܂łƂ߂��B�e�����X�g�́A���̓��{�Љ�Ɏ����ꂽ�̂ł���(�{�͂ɂ��ẮA�����x�u�w�����c�����x�q���Y�t�H�r�A�x�^���w���c�łƓ��{�t�@�V�Y���^���x�q��g���X�r���Q�l�ɂ���)�B�����q�ׂ��u��O�O��v��u�\�E��(����������)�v
�̍l����������Ƃ��ꂽ�B��O�O��́A�������̈�O�̂Ȃ��ɎO���琢�E�����̂܂܊܂܂�Ă���Ƃ������̂ŁA�\�E����A���ꂼ��̐��E�ɂ͒n���E�����F�E�܂ł��ׂĂ̐��E��������Ă���Ƃ����l�����ł���B���邢�́A�H���́A�ÎE�̏u�ԂɁA���̓��@�����������E��̌������̂�������Ȃ��B
�@�@�،o��ǂݑ�ڂ�������Ƃ����s�ׂ́A��������H����҂��x���Ƃ������n�ɓ����Ă����B
�H���́A�ÎE��ʂ��Ă���������Ԃ��o�����Ă������B�ʂ����Ă��ꂪ�A���̈ÎE�҂ɋN���邱�ƂȂ̂��ǂ����͕�����Ȃ����A����ɂ���ĈÎE�Ƃ����s�ׂɂ͏@���I�ȈӖ����^����ꂽ���ƂɂȂ�B
�@�����c�ƌĂꂽ���𒆐S�Ƃ����e�����X�g�̃l�b�g���[�N�́A�����c�����ɂ���ĉ�̂���A���s�Ƃ���Ȃǂ͍��ɂȂ���邱�ƂɂȂ�B�������A���łɏq�ׂ��悤�ɁA�Y���̂��y��������ɁA���͂ɂ���ĊF�o�����Ă���A�ނ�͑����m�푈���O�̓��{�Љ�ɗ����߂��Ă������B
�@�l�����A���E�̍����Ƃ��Đ��Ɋ������Ƃɂ��Ă͂��łɂӂꂽ���A�����A�u�썑�c�v�Ƃ����c�̂��������Ċ����𑱂����B�������A�ƊE���_�ЂƂ����o�ŎЂ����Ȃ���A�E�������𑱂����B�H���ɂȂ�ƁA�����ܘN�Ɖ������A��錧�c��c���ƂȂ��Č��c��c���܂łƂ߂��B�e�����X�g�́A���̓��{�Љ�Ɏ����ꂽ�̂ł���(�{�͂ɂ��ẮA�����x�u�w�����c�����x�q���Y�t�H�r�A�x�^���w���c�łƓ��{�t�@�V�Y���^���x�q��g���X�r���Q�l�ɂ���)�B�i�P�W�Q�`�P�W�R�Łj
|
�@����܂ł��ӂ�Ă����悤�ɁA�@�،o�ɂ́u�s�ɐg���v�Ƃ������Ƃ��o�Ă���B����́A�M�̂��߂ɂ͎����̖����ڂ݂Ȃ��Ŏ̂Ă�Ƃ������Ƃ��Ӗ�����B���ہA���@�́A����̎咣���Ȃ��邱�ƂȂ��A���X�̖@��ɑ����Ă����B���̕s�ɐg���̍l�����́A����̎咣�Əd�Ȃ肠�����̂�����A�₪�Ĉ������������Ă����B
�@�������N����2�N�O�̏��a5�N8��29���ɏ㋞�����Ƃ��ɁA���́A�u���B�����(�̂낵)�������A����ɂ�Ďw���K���̊o���𑣂��ޓ��̎�ɂ�ĉ��������i�K��ɓ��ݏ��ŏ��͖ܘ_�ɂ߂ĕs�O��Ȃ��̂ɂ��܂ċ��邪�����đ��A��O�i�Ɠ]�J���čs���̂͋ɂ߂ėe�ՂȎ��ł���v�Ƃ����F���ɒB���Ă����B�����āA�u�悵�A����������̌��Ӓʂ莀�˂悢�̂��A�厀��Ԃ�!�v�ƁA�ÎE�Ƃ�����i�������(�w�����c������\���A������L�x)�B
�@�N���܂ɂȂ肳������A��͎����I�ɉ����������Ă����Ƃ����̂́A���ʂ��Ƃ��Đ����ƊÂ��悤�ɂ�������B���������˂A���ׂĂ͂��܂������Ƃ����l�������A���܂�Ɏ��Ȓ��S�I������B
�@�������A�����ɂ́A�����c�����ɑ����A�܁E��������N����A����͂���ɓ�E��Z�����ւƔ��W���Ă������̂�����A���̍l�����Ƃ���ɂ��Ƃ͐i��ł������Ƃ�������B
�@����ɁA������A�����c�ɉ�����Ă����ʂ̃O���[�v���������B���ꂪ�A�����鍑��w�Ƌ��s�鍑��w�̒�吶�����ł������B�R�̏��Z�������G���[�g�ł��������A�ނ���G���[�g�ł���A�����썑���֏W�܂��Ă����l�Ԃ����Ƃ͎Љ�K�w���܂������قȂ��Ă����B
�@�����́A�_�Ƃ̏o�g�ŁA�������w�Z�����Ƃ��Ă��炸�A�E�l�̌��K���Ȃǂɂ����Ȃ�Ȃ������B�H�����_�Ƃ̏o�g�ŁA��q�S���w�Z�𑲋Ƃ��Ă�����̂́A�ڂ̕a�C�ŏA�E���ł��Ȃ������B�ނ�́A�����ăG���[�g�Ƃ͌����Ȃ��l�Ԃ����������B
�@��吶�̒��S�ɂ������̂́A��㐭�E�̍����ƂȂ�A���̑����̎w����Ƃ��Ȃ�l���`���������B
�@�l���́A�������̏o�g�ŁA�n���̎����ɐi�w���邪�A�����ł�͂茌���c�ɉ����r�ܐ��ژY�ƒm�荇���A���Ԃ����āA�u�h�V��v�Ƃ����A���{���_�̔��g�Ȃǂ�ړI�Ƃ����C�{�c�̂���������B�i�P�W�U�`�P�W�V�Łj
|