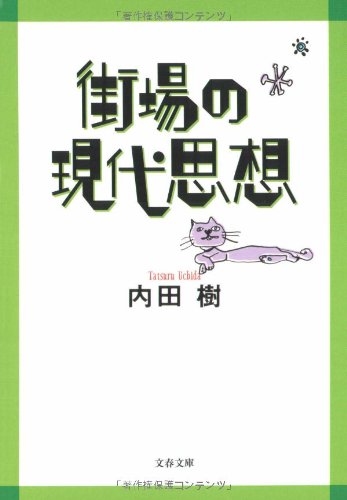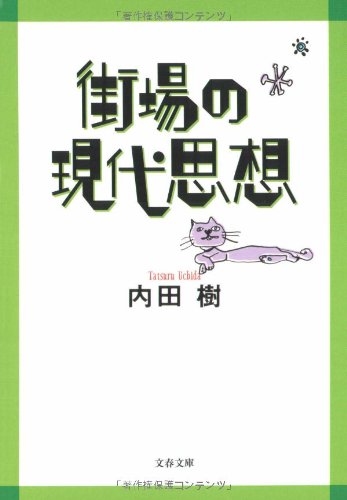「文化資本」という槻念を使って社会理論を構築したのが、フランスの社会学者ピエール・ブルデューである。
どうしてフランスで「文化資本」ということばが社会理論の道具として有用であったかというと、そこにはそれなりの歴史的事情がある。
それはフランスが「階層社会」だからである。
「階層」(couche)と「階級」(classe)は似ているようだが、微妙に違う。
「階級」というのはマルクス主義の概念であり、「階級意識」の主体的獲得と同時に歴史的に登場する。主体の側の積極的参与がない限り、「階級」というものは存在しない。
「私は階級社会に生きており、私のものの考え方や感じ方やふるまい方は、階級的に規定されている」ということに「気がついた」人間の目にだけ「階級」は見え、そういうふうな考え方をしない人間の目には見えない。ただ「ビンボー」であれば、「プロレタリア的階級意識」を持てるというものではないのである。
だから、社会の最下層にあって、現に苛烈に収奪されていながら、ナポレオン三世のブルジョワ独裁を熱狂的に支持した貧民たちは「ルンペン・プロレタリアート」と呼ばれてマルクスの罵倒を浴びることになったのである。
「階級」は「階級的自覚に目覚めたもの」が主体的に構築してゆくものである。
それに対して「階層」というのは、本人がどう思おうと、ご本人の自己決定や努力とはかかわりなしに、リアルかつクールに「もう、すでに、そこに」存在する。
ある人間がどの「階層」に所属するのかということは、本人によっては決定することができない。気がついたら「そこにいた」のであり、個人的努力ではめったなことでは「そこから抜け出せない」のが「階層」である。
フランスは「階級」社会ではないが、「階層」社会である。そして、階層と階層の間には乗り越えることのできない「壁」がある。その「壁」は社会的地位や資産や権力や情報や学歴など、多様な要素によって構成されているが、ある階層に属する人間と別の階層に属する人間を決定的に隔てているのは「文化資本」(capital culturel)の格差である。 |