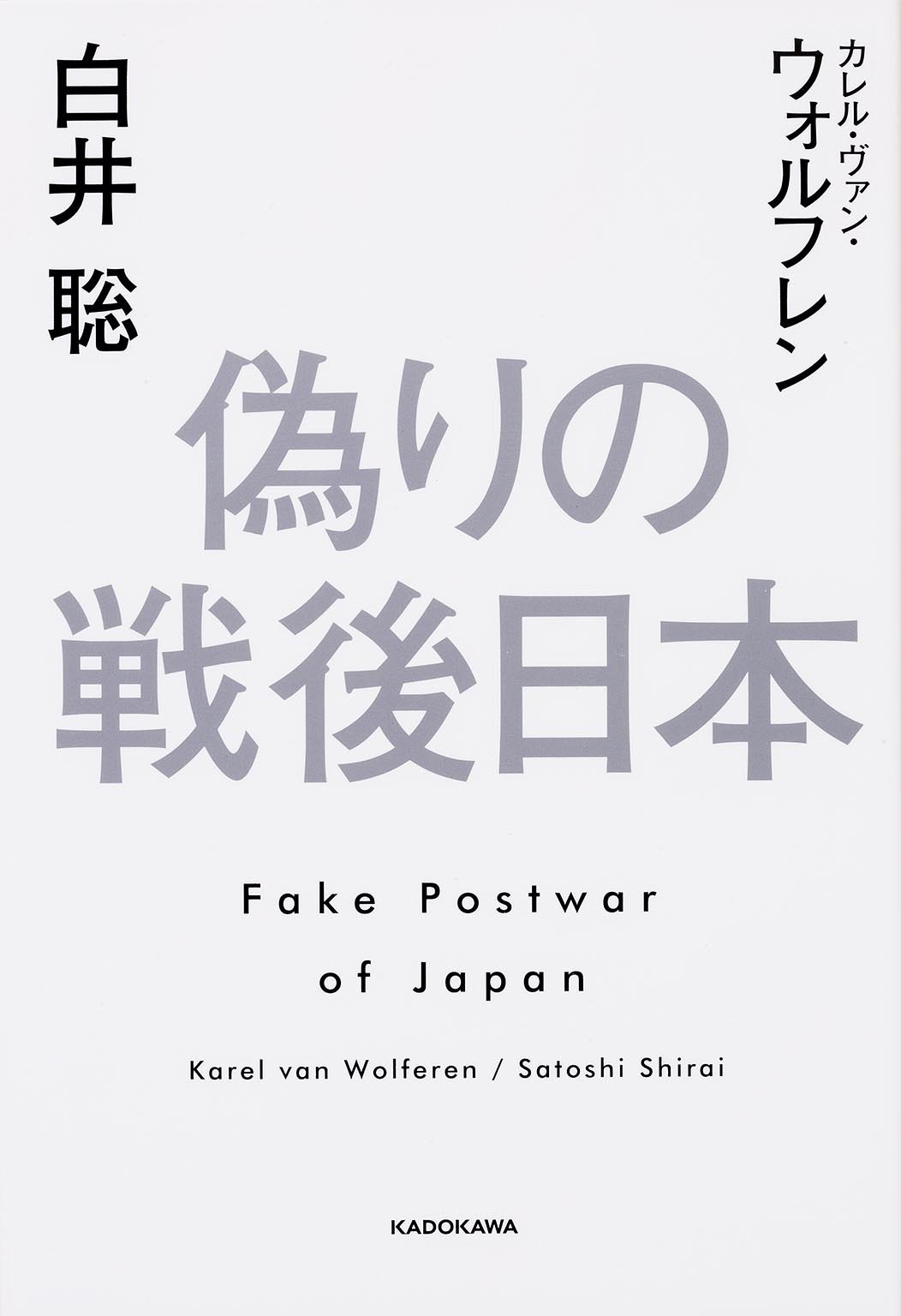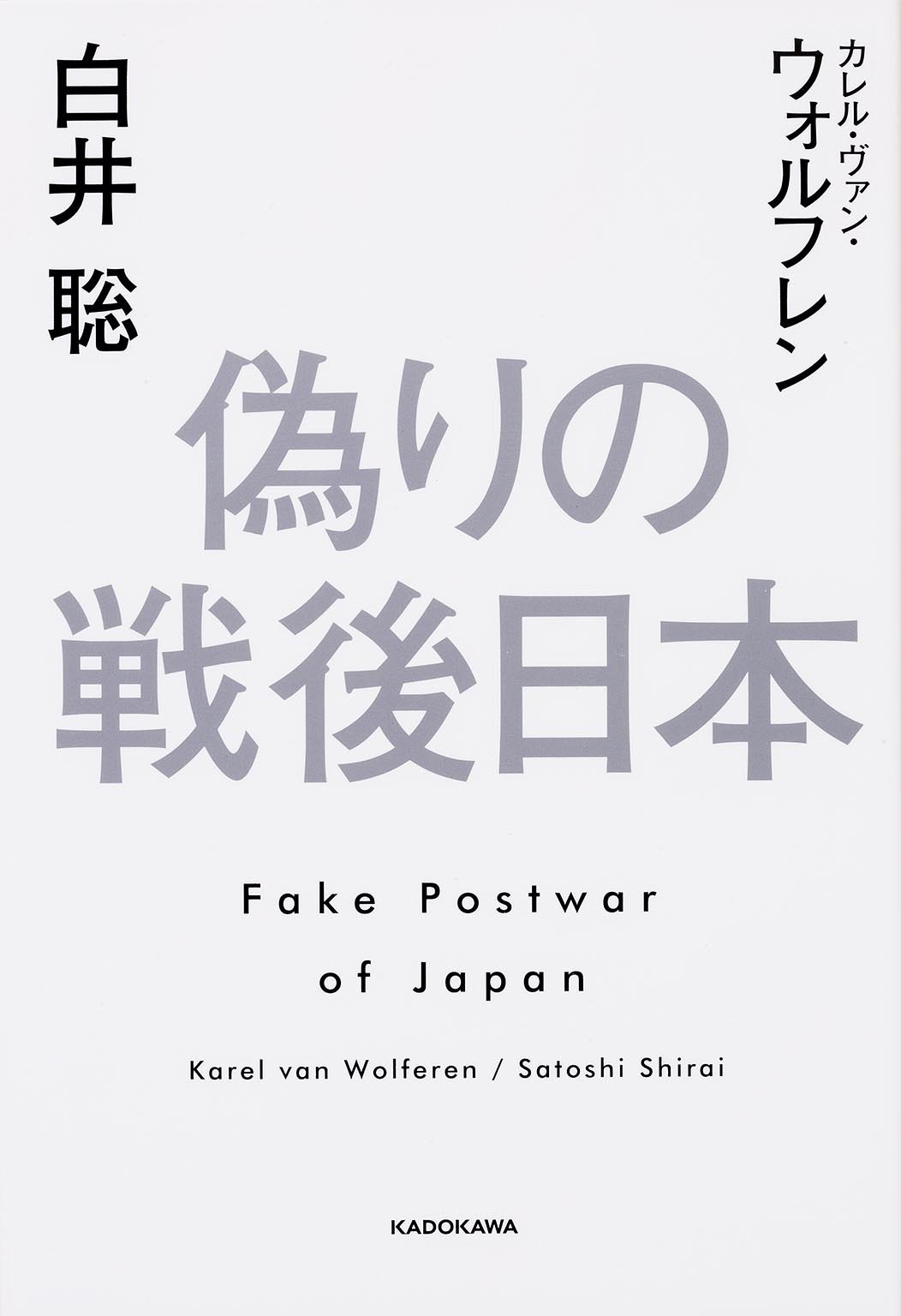2015年11月21日(土)
白井聡、カレル・ヴァン・ウォルフレン『偽りの戦後日本』読了。
ブログ参照;http://kohkaz.cocolog-nifty.com/monoyomi/2015/11/post-8673.html
ていました、橋本さんにはすでに首相経験があって、当初は小泉さんより有利と見られていた。しかし、党員を対象とした予備選で小泉さんが圧勝し、その勢いで総裁になります。小泉さんが仕掛けた広告宣伝戦略が効果を発揮したのです。彼は希代のショーマンですからね。新聞やテレビも「改革の旗手」として持ち上げた。日経新聞を始め、読売、さらには朝日までも小泉さんに肩入れしていた。あのとき橋本さんが勝っていれば、今ごろは自民党など存在していなかったかもしれない。
白井 小泉さんの政治は、「劇場型」などとも評されましたが、その大きな問題は反知性主義を大々的に持ち込んだことです。後に発覚してスキャンダルになりましたが、郵政解散総選挙のときに、選挙戦略を請け負った広告会社が「B層」、すなわち「本当のところよくわからないが小泉さんのキャラクターに惹かれて郵政民営化に賛成する層」、もっと露骨に言えば、オツムが悪く軽率なので騙されやすい層をターゲットにしようと提案していた。この戦略は見事に当たったわけですが、自民党はこれ以来明確にシニシズムに依拠するようになった。今の安倍政権の政治手法はこの延長線上にあります。その政策的実質が腐敗したものとなるのは必然的でしょう。
ウォルフレン 小泉さんがやったことは、それまでの官僚主義を市場主義に置き換えただけのことです。看板の政策だった「郵政民営化」がその象徴と言えます。しかし郵便局が民営化されたことで、日本人が幸せになったのでしょうか。それどころか、むしろ不幸な人が日本中で増えてしまった。構造改革路線によって、地方の商店街などは大打撃を受けました。また、非正規雇用が増えていくのも、小泉さんが導入した「改革」の結果です。
小泉さんのブレーンを務めたのが、経済学者の浜田宏一です。彼は現在の安倍政権にも深く関与していて、「アベノミクス」の生みの親とまで言われている。浜田氏はアメリカのイェール大学で教鞭(きようべん)を執っていたバリバリの新自由主義者ですからね。
白井 問題は、このようなふざけた茶番を国民が受け入れてきたことです。
特に小泉政権時代には、熱狂的に支持されていた。自分たちの利害がどのような仕組みで成り立っており、何が自分にとって損になるのか、得になるのか、合理的に考えることができない国民になってしまったからこそ、小泉かウォルフレン 新自由主義とは、政府の介入を最小限に留め、何でも市場に任せようという考え方です。そのために何よりも「効率」が優先される。また、企業にとっては、短期的な視点で利益を生むことも求められる。日本には全く馴染(なじ)まないものだと思います。
日本が経済成長を続けていた1980年代、東京を訪れた欧米のビジネスマンは「日本はなんて効率の悪い国なんだ」とよく嘆いていました。「こんな国がよく経済成長を遂げているな」と驚きもした。政府が管理して金融機関を破綻させないようにする「護送船団方式」や、企業グループ問での「ケイレツ」取引などもまかり通っていました。いずれも欧米人の目には、極めて非効率なやり方です。
私は彼らに対し、「日本では『効率』よりも、目標を達成するための『効果』が重要とみなされるんだ。実際に効果は上がっていて、経済成長という結果も出ているだろ」と反論したものです。少しくらい効率が悪かろうと、ゴールにたどり着けば成功とされる。そんな思考で日本は成功を掴(つか)んできたのです。
しかし、やがて日本も新自由主義の影響を受けるようになりました。「効率」ばかりを重視すれば、クオリティ(質)に問題が生じてしまいます。それでもよしとされるようになった。中身の質がどうであれ、とにかく効率を重視する。そのためには「見た目」が重要です。見た目さえ整っていれば、実体が伴っていなくても構わない。つまり、現実が「見た目」に置き換えられてしまった。PR(パブリック・リレーションズ巨広報活動)を駆使すれば、「見た目」を繕うことも簡単です。そうしてPR重視の考えが広がってしまい、日本の良さのみならず、本来持っている強さまでも失われていきました。
白井 新自由主義化は世界資本主義の趨勢です。効率が効果に取って代わることで、本質的な意味で生産性の基礎となる社会の体力が奪われて行きます。 |
140-143p
ウォルフレン 確かにそうですね。
白井 今回の選挙では、「基地がなくても自分たちは発展できる、むしろ基地などない方がいい」という声が上回った。政府の方針がどうであれ、選挙を通じて地元がきちんと自分たちの意思を表明するという・ことが実現されました。こうしたことが政治対立のプロトタイプとして、日本全体に広がっていくことを僕は期待しています。
ウォルフレン 沖縄では「基地」という大きなテーマがありました。それと同様、本土にもテーマはある。「原発」などその典型だと思います。本土でも、沖縄で起きたようなことを現実のものにしていくことは決して不可能ではない。
引退すると正論を吐く政治家と財界人
白井 先ほどウォルフレンさんから、「日本には愛国者はいないのか」というお話がありました。それで思い浮かぶのが、プロ野球の広島力ープに復帰した黒田博樹投手です。黒田投手のことはご存じですか。
ウォルフレン 私はスポーツには関心がないもので、事情は全くわかりません(笑)。
白井 黒田投手は昨年まで大リーグのニューヨーク・ヤンキースで活躍していました。年齢は今年で40歳ですが、それでも引き続きアメリカでプレーしていれば1年で20億円近く稼げたと言われています。にもかかわらず、敢(あ)えて古巣の広島力ープというチームに戻ってきた。カープは日本のプロ野球でも資金力に乏しい球団の一つです。それでもがんばって黒田投手には年俸4億円を出すとのことですが、大リーグでプレーした場合と比べればずっと安い。つまり、黒田投手は。カネ"ではない何かが存在することを示すために日本へと戻る道を選んだ。彼の決断は英雄的です。
わざわざ黒田投手の話を持ち出したのは、「愛国者」と言われて他にすぐ思いつく人がいなかったからです。政治家もそうですし、財界にしても同じです。
大企業の経営者たちには、「愛国者」ぶっている人が時々います。「日本経 |
196-197p
きているのです。現状は1962年のミサイル危機のレベルには達していないとはいえ、冷戦終結後で最悪の状況にあることは間違いありません。その原因はロシア側ではなく、アメリカ側にあるのです。そこにはアメリカや西ヨーロッパ諸国において、歴史が歪曲されて伝わったことも強く影響しています。歴史の解釈がひどい政策を招いてしまう何よりの証と言えるでしょう。
ウクライナ情勢がロシアとの戦争に発展しないよう、ヨーロッパにおいて遅ればせながら中心的な役割を演じてきたのがメルケル首相です。メルケル首相は訪日時、安倍首相とも会談していますが、彼女を通じて安倍首相がウクライナ情勢の深刻さを理解したことを祈るばかりです。
日本の報道を見る限り、ウクライナ情勢の実態は正確に伝わっていないように感じます。その象徴が、ウクライナ南部のクリミア半島を訪問した鳩山由起夫・元首相に対する日本のメディアの反応です。メディアはロシアがクリミアを武力によって編入したと批判しています。クリミァの人たちが民主的な住民投票を実施した結果、ロシアへの帰属を望んだという事実については報じようとはしない。そうしたメディアの姿勢もあって、鳩山氏は日本政府から激しい非難を受け、一部の評論家たちの嘲りの対象とすらなっています。しかし鳩山氏が取った行動は、日本のベテラン政治家として極めて正当なものなのです。そのことを是非、読者の皆さんには理解していただきたい。
歴史が持つ意味は、口本にとって、過去になかったほど重要になっています。日本はロシア、中国、アメリカという大国に挟まれるかたちで存在しています。それぞれの国との間で日本は、ある意味、歪んだ関係を築いてしまっている。日本が敗戦を喫する以前に起きた出来事、そうした出来事について戦後、日本政府が下した解釈による結果です。
最近も、歴史に関する理解がいかに重要であるかを思い知らされる出来事がありました。ジャーナリストの後藤健二さんらがシリアで「ISIS(イスラム国)」に惨殺された後の日本政府の対応です。安倍首相はイスラム国と戦う姿勢を明確に示しました。しかし後藤さんたちは、いったい何の犠牲になったのか。シリアにおける政治的混乱とイスラム国の狂信的な戦闘員たちをつくりだしたのは、他でもなく日本の最大の同盟国であり、かつ日本を守ってくれているはずの国なのです。
その事実について、いったいどれほどの日本人が理解しているのでしょうか。
安倍首相が信じているような「対テロ戦争」など、現実には全く不可能です。今世紀に入ってからの「歴史」を振り返るだけでも、そのことは明らかになっている。「対テロ戦争」など虚構に過ぎません。テーブルについて和平交渉すらできないような相手との間で、戦争をすることなどできるはずもないのです。
この対談を通じ、白井さんと私は歴史の持つ重要性について語り合いました。その思いが本を手に取ってくださった皆さんに伝わっていることを願ってやみません。私の次の作品で、皆さんと再 |
220-221p 「あとがき」より
偽りの戦後日本
白井聡/著 カレル・ヴァン・ウォルフレン/著
出版社名 KADOKAWA
ISBN 978-4-04-653342-5
発売日 2015年04月
販売価格 : 1,600円 (税込:1,728円) |
- 1945年の「敗戦」を認められない日本人は、戦後日本という欺瞞の構造をいつまで放置し続けるのか――。原発、基地問題から安倍政権の本質まで、独立なき「永続敗戦」の現実を直視する日欧の論客が語りあう。
- 目次
-
第1章 日本はふたたび戦争に踏み出すのか(40年前への逆戻り
「大政翼賛会」化した日本の政界 ほか)
第2章 敗戦国の空虚な70年(「敗戦」を認められない日本人
二度目の「敗戦」が必要なのか ほか)
第3章 右傾化する日本人(政治に「神話」を持ち込む安倍政権
存在感を増す「反米保守」 ほか)
第4章 新自由主義が支配する世界(小泉政権が日本に残した反知性主義
「ポチョムキン村」化する日本 ほか)
第5章 終わらない「敗戦」を乗り越えるために(脱原発には二度目の悲劇が必要なのか
ドイツとイタリアにできて日本にできない脱原発 ほか)
|
|