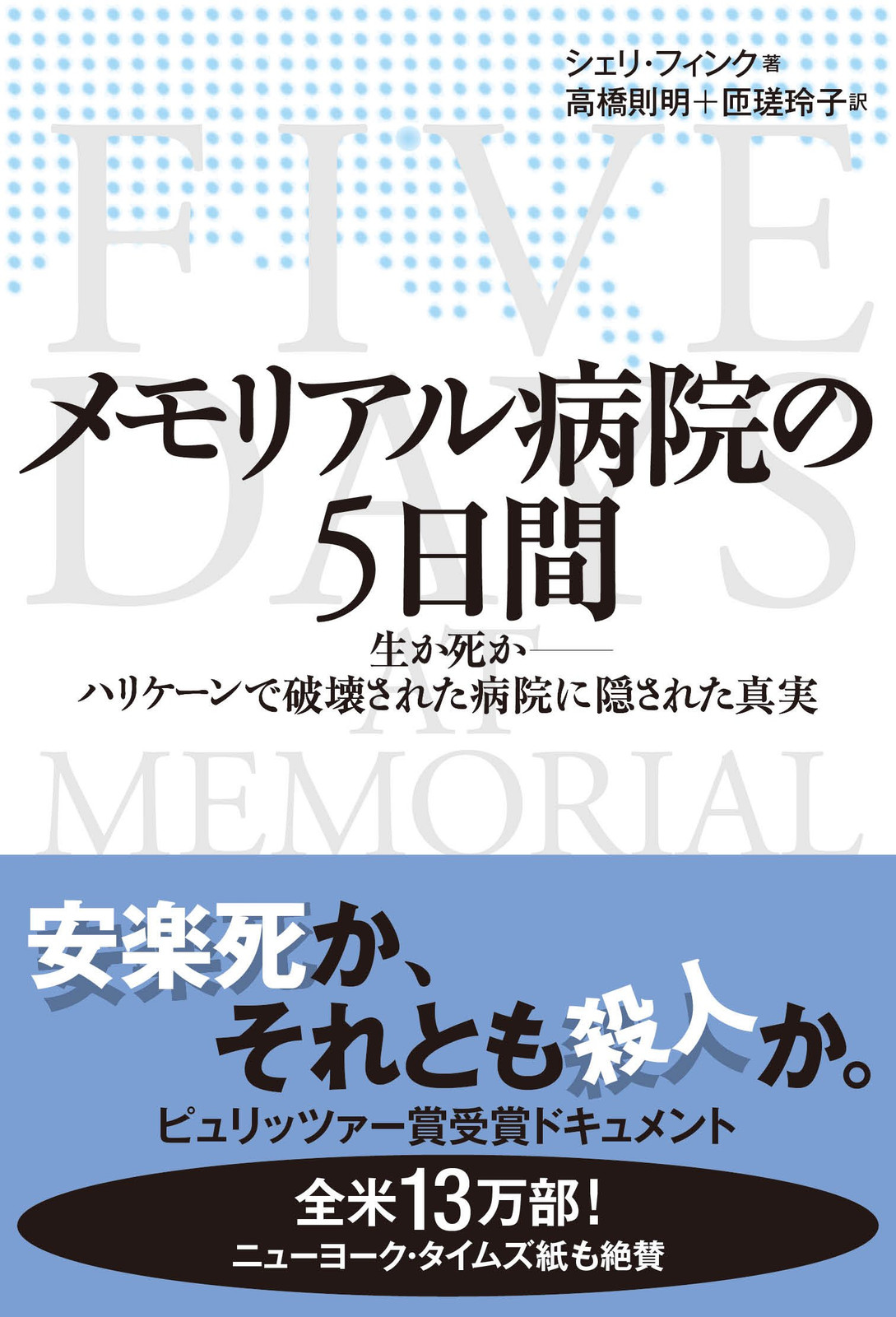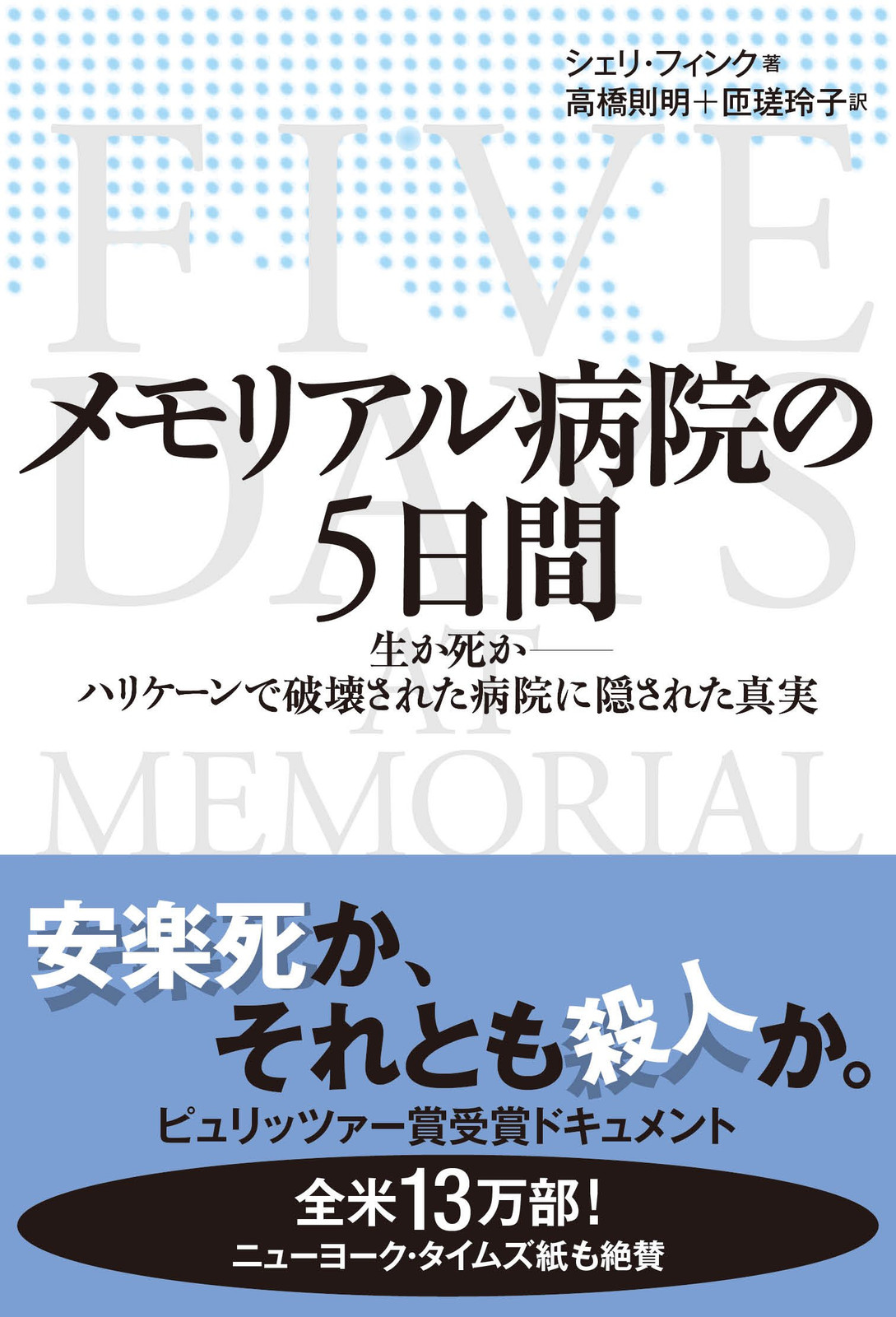2015年10月18日(日)
ブログ参照;http://kohkaz.cocolog-nifty.com/monoyomi/2015/10/post-85ae.html
この地域最大の救急車サービス会社であるアケイディアン・アンビェランス社の配車センターには、危機感を抱いた病院や介護ホーム、一般家庭から患者を搬送してくれという要請が殺到していた。ところが、派遣した約25台の救急車の多くは、州間高速道路の渋滞にはまってしまった。そこで、時間節約のために搬送者を市外ではなく、スーパードームに運ぶ救急車も出てきた。
セントバーナード郡にある大規模病院のシャルメット医療センターでは、第1陣の重症患者を乗せて出発した救急車は二度と戻ってこなかった。ニューオリンズにある別の病院では重症患者を9名、州西部に移動させたかったが、緊急に高価なヘリをチャーターできなければ、手遅れになる可能性があった。道路は大渋滞で、脆弱な病人を乗せた救急車が目的地に着くのに丸1日かかることもありえたのだ。ある介護ホームでは、ハリケーン・シlズンに先駆けてニューオリンズの旅行会社に1400ドルを支払い、緊急時に入居者を7台の大型バスでミシシッピ州まで運ばせる手はずを整えていた。
ところが27日土曜日の夜、その会社から、手配できるのは運転手なしのわずか2台であり、契約を履行できないという連絡があったという。 |
(52〜53頁)
「人の生き死にを決める権利は、きみにはない」。ボルツはいつもそう応酬した。同僚の何人かは、ボルツが考えるところの「ラム流哲学」の信奉者だった。1984年、財政赤字がふくらみ、医療費が膨張していた時代、コロラド州知事リチャード・ラムは高価な最新医療を駆使して、年齢や予後に関係なく延命することを批判した。ラムはその論拠として、コロラド医療専門弁護士協会の会議で、シカゴ大学の有名な生命倫理学者、レオン・R・カス博士が寄せたアンチエイジング研究に関する批評を引用した。「我々には(ムダな延命治療を受けずに)死ぬ義務がある」とラムは言った。「我々(高齢者)は、機械や人工心臓といったもの一切合切を抱えて立ち去るべきだ。そうすることで、次の世代に合理的な生活を築いてもらうのだ」
このラムの言葉は、デンバー・ポスト紙の記者がめざとくとりあげたことで、全国で物議を醸した。
1960年代、70年代に救急力iトが登場し、集中治療医学が進歩したことで、病院は病人を延命す |
69頁
そこにはまた、死をどう定義するかという、考える人を不安な気持ちにさせる深遠な問題があった。
延命治療を始める時期、またはやめる時期はいつなら許されるのか、もっと言えばいつなら正しいのか。ラム州知事のコメントが新聞に掲載されてからの数週間、一般のアメリカ人はこうした問題を直視せざるをえなくなった。
そして、すぐに目をそらした。 |
71頁
使われていた言葉だ。その後、ナポレオン軍の医師だったドミニク・ジャン・ラーレーが戦場で負傷兵の選別に適用した。やがて、災害や事故で治療リソースを超える負傷者が出たときにも使われるようになった。驚いたことに、ベストの選別方法として広く認められているものはまだない。
トリアージと医療手当ての割り当てを見ると、その社会の権力者が人の命をどのように見ているかがわかる。第二次世界大戦中のイギリス軍は、貴重なペニシリンの投与をパイロットと爆撃機の乗員とに制限した。腎臓病のための透析が普及する前のアメリカでは、ひそかに一部の病院が、コミュニティの「最大幸福」を促進するために、患者の年齢、性別、配偶者の有無、教育水準、職業、将来性を考慮して治療方針を決めていた。ライフ誌の記者シャナ・アレクサンダーが、1962年11月号でこのやり方を暴くと、世間の注目が集まり、抗議の声があがった。識者たちはシアトルの病院が、「体制に従わない者」を排除していたことを批判した。「アメリカにはそうした人々が国を作ってきた歴史がある。太平洋岸北西部には、腎臓病のヘンリー・デイヴィッド・ソローが生きる場所はないようだ」
そのためアメリヵでは、必要な市民には国の負担で透析が受けられる制度が立法化された。一方、南アフリカなどの国では、公立病院において透析の需要が供給を大きく上まわった場合には、医師たちが週に一度の会合で、誰を生かし、誰を死なせるかを決めている。その際にはさまざまなことが問題となる。たとえば、患者の職業や親の地位、薬物乱用歴など「社会的価値のものさし」を重視することは倫理的に正しいのか? 患者にその決定を知らせて、抗弁の機会を与えるべきか? 長年、白人を優遇する決定をしてきた南アフリカで、そのプロセス自体を公平なものに正すことは可能なのだろうか? 結局、南アフリカでは患者からの意見を多くとりいれることで、より標準的な割り当てシステムを作った。加えて、低収入の市民に透析を普及させる活動と、腎臓病予防の活動も効果をあげて、患者の選別プロセスはより透明なものになったのだった。
カトリーナ襲来時のアメリカでは、少なくとも9種類のトリアージ法が認知されていた。だが、主な方法について、その実効性があるかどうか、つまり、目的を達成できているかどうかが調べられたことはほとんどない。というのも、非常時には死亡も含めて、結果を調査することがむずかしいし、結果を知りたくない者もいるし、さらには、調査しても金銭的利得がないからだ。9つのトリアージ法のほとんどが、軽いケガの患者を待たせて、重症患者の治療を優先する。
重症患者の優先という考えは、前述したナポレオン軍のドミニク・ジャン・ラーレー医師が起源となっている。1806年10月、現ドイツのイエナで、ナポレオン軍とプロイセン軍が戦ったときのラーレーの回想録にその考えは登場する。「負傷程度が軽い者は、重症の同胞が手当てを受けるのを待つことになる。重症者は、その階級や武勲に関係なく、優先的に治療されるべきだ」。そこには、フ |
174〜175頁
ランス革命でうたわれた平等の理念が受け継がれていた。
その後、1846年にイギリスの海軍医ジョン・ウィルソンが、別のトリアージ法を考えだした。
手術が成功する見込みの低い患者は、手術をしないことにしたのだ。2005年にいくつかのトリアージ法がこの考えを組みいれ、手元にある医療リソースで助かる見込みがない負傷者については、手当てをしないか、立ちのかせることを医療従事者に求めた。これは交戦地帯での爆弾の爆発など、一度に大量の負傷者が出て、手当てが追いつかないか、リソースが足りない状況を想定している。
重症患者をあとまわしにすることにはリスクがある。この先、患者の状態がどうなるのかを予測することはむずかしいし、その判断にはバイアスが働きやすいからだ。トリアージに関するごく小規模な研究では、ベテラン医師たちが患者の分類をしたところ、判定結果に大きなぼらつきが出たのだった。同じ患者でも生存可能性を高いと見積もる医師もいれば、低いと見る医師もいた。さらに、利用できるリソースが増えることもあり、患者の条件は変化しうるのだ。そのため再トリアージは重要なのだが、ひとたび分類がなされたあとは忘れられやすい。
分類ミスにより助かる命を失う悲劇を避けるために、一部の専門家は、生存可能性が低いと見積もられ、手当てをしないか、立ちのかせるかをする患者を、早急に手当ての必要な患者と、待たせておくことのできる患者とのあいだに入れることを提唱している。
ボーたちはトリアージのやり方についてほとんど学んでいなかったし、特定の手順に従ったわけでもなかった。ボーにしてみれば、それは胸を締めつけられるつらい作業だった。重症患者について、避難の優先度を最初から最後に変えたのは、医師たちが全員は救えないと思っていたことの結果だ、とボーは思った。 |
176〜177頁
| この日、ジョージ・W・ブッシュ大統領が、テキサス州で過ごしていた休暇を切りあげて、大統領専用機のエアフォースワンでホワイトハウスに戻る途中、空からニューオリンズを視察した。エアフォースワンはメモリアルのヘリパッドからも携帯電話で写真が撮れたほど低空を飛んだ。だがのちに、視察のあいだ、救助ヘリの飛行が制限されたために、救助活動を遅らせたという批判が出た。 |
187〜188頁
これら3つの病院とスタッフの対応が対照的だったのが、公立チャリティ病院だった。浸水し、電気と水道が止まり、コンピュータも電話もエレベーターも使えなくなった。ヘリパッドはなく、支援してくれる親会社もないし、救助はメモリアルよりも1日遅い9月2日になった。メモリアルの約2倍の患者を抱え、そのうち精神疾患の患者が100人以上もいて、スタッフ1人当たりの患者数はメモリアルよりも多かったにもかかわらず、チャリティ病院ではわずか3人しか死者が出なかった。スタッフが逃げださずに、患者のケアを続けたからにほかならない。
周囲の環境はメモリアルよりも悪かったかもしれない。近くのビルの屋上には銃を持った人間がいて、避難の障害になっていると言われていた。病院に水を運ぼうとした一団は銃を持つ男たちに襲われ、物資を奪われたという。多くの精神疾患の患者を抱え、小便は階段の踊り場で済ませた。避難すべき時間までに避難が終えられなかったうえに、軍によって人工呼吸器を必要とする患者が新たに運びこまれたのだ。 |
417頁
メモリアル病院の5日間 生か死か−ハリケーンで破壊された病院に隠された真実
-
- 出版社名KADOKAWA
-
- ISBN 978-4-04-731653-9
-
- 発売日 2015年05月
-
-
- 価格 販売価格 : 2,500円 (税込:2,700円)
-
|
- 安楽死化?それとも殺人か?医師たちによって行われた命のランク付け。ピューリッツァー賞作家が描くナラティブ・ジャーナリズム。
- 目次
- 第1部 死の選択(1926年、1927年の嵐
カトリーナ襲来前夜
カトリーナ襲来とメモリアル病院
停電と洪水
電源喪失とトリアージ
猛暑と命がけの避難
蘇生禁止患者と安楽死)
第2部 審判(不審死と告発
逮捕と大陪審)
|
著者紹介
シェリ・フィンク
Sheri Fink
アメリカ人ジャーナリスト。健康や医療、科学分野のテーマを得意とする。彼女のレポートはこれまでに、ピュリッツァー賞、アメリカ雑誌編集者協会のナショナル・マガジン・アワード、海外記者クラブのローウェル・トーマス・アワードをはじめとするジャーナリズムに関する多くの賞に輝いている。スタンフォード大学及び大学院で神経科学のPh,D.、 M,D.を取得。大学院修了後は、災害や紛争地域に影ける難民救済ワーカーとして活動した。彼女の処女作『War
Hospital』は、ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争中、スレブレニツァで虐殺がヵこなわれたときに、セルビア人勢力に包囲された町にいた医療従事者たちの姿を描い充ノンフィクション。本書はノンフィクション2作目になる。
訳者紹介
高橋則明
翻訳家。1960年生まれ。立教大学法学部卒。
主な訳書に、クリス・アンダーソン『フリー』、ネイサン・ウルフ『パンデミック新時代』、ペドロ・G・フェレィラ『パーフェクト・セオリー』(以上、NHKl出版)、ジョン・ロビンズ『100歳まで元気に生きる!』(アスペクト)などがある。
匝瑳玲子
翻訳家。青山学院大学文学部卒。主宏訳書に、ジョー・R・ランズデール『ダークライン』(早川書房)、ロバート・フェザー『死海文書の謎を解く』(講談社)、ロバート・K・ウィットマン『FBI美術捜査官一奪われた名画を追え』(柏書房、文芸社、共訳)などがある。 |
|