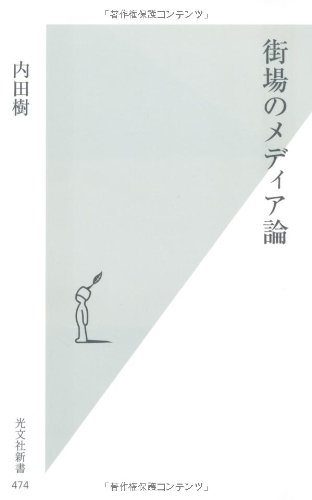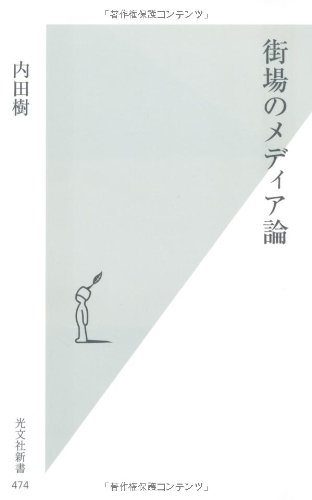後退するメディア
第一が「マスメディアの凋落(ちようらく)」。日本のメディア業界は、新聞も、図書出版も、テレビも、音楽産業も、きわめてきびしい後退局面に入っております。ビジネスモデルが一変してしまった。どういうふうに一変したのかについては、これからじっくり見てゆきたいと思いますけれど、とにかくもう業界的には「先がない」。気の毒ですけれど。
みなさんの中には、これからメディア業界に就職して、そこでのキャリア形成を構想されている方も多いわけですから、その方たちには最初から冷水をかけるようで、ほんとうに申し訳ないんですけれど、どうぞご勘弁ください。でも、いったいどうして、こんなことになってしまったのか。これはぜひ解明しなければならないと思います。
第二の論点は、もし、マスメディアが没落してゆくのだとしたら、いったいそれに代わって、どのようなメディアモデルが登場してくるのか、というものです。「マス」メディアに代わるのは「パーソナル」メディアではなくて、その中間の「ミドル」メディアだろうという意見があります。面白い考え方だなと僕も思います。この「ミドルメディア」とはいった |
34-35p.
| メディアの「危機耐性」とは、端的に言えば、政治的弾圧や軍部やテロリストの恫喝(どうかつ)に屈しないということです。その抵抗力は最終的には「メディアには担わなければならない固有 |
45p.
少し前に、ある国立大学の看護学部に講演で招かれたことがありました。講演の前に、ナースの方たちと少しおしゃべりをしました。そのときに、ナースセンターに貼ってあった「『患者さま』と呼びましょう」というポスターに気づきました。「これ、なんですか?」と訊いたら、看護学部長が苦笑して、そういうお達しが厚労省のほうからあったのだと教えてくれました。
僕はそれを聞いて、これはまずいだろうと思いました。これは医療の根幹部分を損なう措置なんじゃないかと思って率直にそう言いました。その場にいたおふたりとも頷いて、興味深い話をしてくれました。
「患者さま」という呼称を採用するようになってから、病院の中でいくつか際立った変化が起きたそうです。一つは、入院患者が院内規則を守らなくなったこと(飲酒喫煙とか無断外出とか)、一つはナースに暴言を吐くようになったこと、一つは入院費を払わずに退院する患者が出てきたこと。以上三点が「患者さま」導入の「成果」ですと、笑っていました。
当然だろうと僕は思いました。というのは、「患者さま」という呼称はあきらかに医療を商取引モデルで考える人間が思いついたものだからです。 |
77p.
メディアの定型性は二種の信憑によってかたちつくられているというのが僕の仮説です。
これからその話をします。
第一は、メディアというのは「世論」を語るものだという信憑。第二は、メディアはビジネスだという信憑。この二つの信憑がメディアの土台を掘り崩したと僕は思っています。
たぶん、ほとんどのメディア業界人はそう聞いてびっくりするでしょう。メディアは世論を形成し、世論を代表し、それによってビジネスとして成立している、そういうものではないのか、と。僕はそれが違うだろうと思います。世論とビジネスがメディアを滅ぼした。それが僕の意見です。かなりわかりにくい話だと思いますので、ゆっくりその理路を申し上げます。 |
99p.
現代人は「社会の諸関係はすべて商取引をモデルに構築されている」と考えています。一方に売り手がいて、他方に買い手がいる。それが市場を形成し、そこで商品やサービスと貨幣が取り交わされる。そういうスキームに即してすべての社会関係が考想されている。
たしかに、資本主義経済体制の中に僕たちは生きているわけですから、ほとんどの社会関係がマーケットにおける取引を基礎にして理解されるのは当然と言えば当然のことです。けれども、社会制度の中には商取引の比喩では論じることのできないものもあるということは忘れないほうがいい。さしあたり、「市場経済が始まるより前から存在したもの」は商取引のスキームにはなじまない。
「社会的共通資本」という概念があります。経済学者の宇沢弘文(うざわひろふみ)先生が使い出された言葉ですけれど、人間が共同的に生きてゆく上で不可欠のものを指します。自然環境(大気、水、森林、河川、湖沼、海洋、沿岸湿地帯、土壌など)、社会的インフラストラクチャー(道路、交通機関、上下水道、電力・ガスなど)、制度資本(教育、医療、金融、司法、行政などの |
107p.
ジョーゼフ・ピュリッツァーとウィリアム・バーストという今に名を残す二大新聞王は、一九世紀末『ニューヨーク・ワールド』と『ニューヨーク・モーニング・ジャーナル』で激しい部数競争を展開していました。そして、ちょうどそのときに起きたキューバ独立運動について虚実とりまぜた扇情的な報道を行い、アメリカの軍事的コミットメントを正当化するための世論形成に大きな役割を果たしました。「イエロー・ジャーナリズム」というのはこのときの二紙の部数拡大主義を指して用いられた言葉です。メディアによる「煽り」はアメリカ政府の領土的野心を満たし、ふたりのビジネスマンに巨富をもたらしました。その成功体験が近代ジャーナリズムには刻印されている。
むろん、日本のメディアも日比谷焼き討ち事件を使嗾(しそう)した新聞報道や、先の大戦中の翼賛報道などについての反省をおりおりには口にします。でも、社会不安や戦争が「部数を伸ばす」最大の要因であるという事実は否定しない。そして、「部数を伸ばしたい」という欲望が「社会不安や排外主義を煽ってまで部数を伸ばすようなことはしてはならない」という「政治的に正しい」倫理的自制によって抑圧された場合、それは社会制度の急激な、予測不能の変化への抑えがたい欲求という症状となって回帰ない。僕はそう思います。
社会制度の劇的変化が起こると、「これから何が起こるかわからない」という不安が生まれます。「何が起きているのか知りたい」という情報へのニーズはメディアにたしかな商業的利益をもたらす。そういう図式がすべてのメディア人の無意識のうちには深く刻印されている。それが無意識のものである以上、メディアが「変化を求める」ことは誰にも止められません。変化のないところにさえ変化を作り出そうとする。変化しなくてもよいものを変化 |
112-113p.
まだ5年で10年の半分だが、マスメディアはまったく変わっていない。
本書では特に既存マスメディア(新聞、テレビ、出版社)に対して、たいへんきびしい言葉を書き連ねました。これも蓋を開けてみたら、まるでお門違いであって、十年後もあいかわらずテレビではどの局も同じようなバラエティ番組を放送し、新聞は毒にも薬にもならない社説を掲げ、インスタント自己啓発本がベストセラーリストに並んでいる……というようなことになった場合には、ほんとうにお詫びの申し上げようもありません。その場合はわが不明を恥じつつ、この本が「未来予測はたいへんにむずかしい」という汎用性の高い真理を学ぶための「生きた教訓」としてひさしく読み継がれるというかたちで責任を全うしたいと考えております。
二〇一〇年六月 内田樹 |
210-211p.
街場のメディア論
光文社新書 474
|
|
|
著者/訳者
|
内田樹/著
|
|
出版社名
|
光文社
|
|
発行年月
|
2010年08月
|
|
サイズ
|
213P 18cm
|
|
販売価格
|
740円 (税込799円)
|
|
本の内容
テレビ視聴率の低下、新聞部数の激減、出版の不調?、未曾有の危機の原因はどこにあるのか?「贈与と返礼」の人類学的地平からメディアの社会的存在意義を探り、危機の本質を見極める。内田樹が贈る、マニュアルのない未来を生き抜くすべての人に必要な「知」のレッスン。神戸女学院大学の人気講義を書籍化。
目次
第1講 キャリアは他人のためのもの
第2講 マスメディアの嘘と演技
第3講 メディアと「クレイマー」
第4講 「正義」の暴走
第5講 メディアと「変えないほうがよいもの」
第6講 読者はどこにいるのか
第7講 贈与経済と読書
第8講 わけのわからない未来へ
ISBN
978-4-334-03577-8
著者情報
内田 樹
1950年東京都生まれ。東京大学文学部仏文科卒業。東京都立大学大学院人文科学研究科博士課程中退。現在、神戸女学院大学文学部教授。専門はフランス現代思想、映画論、武道論。2007年『私家版・ユダヤ文化論』(文春新書)で第6回小林秀雄賞を、『日本辺境論』(新潮新書)で新書大賞2010を受賞
|