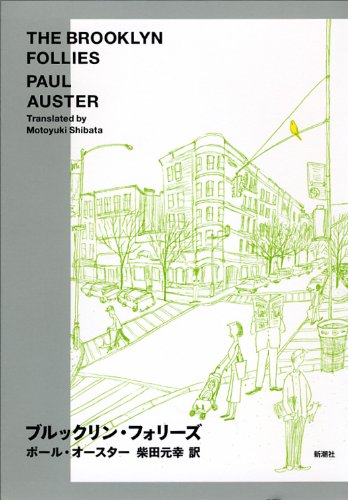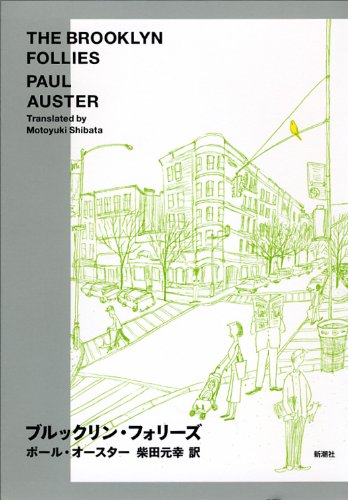内容紹介
幸せは思いがけないところから転がり込んでくる──傷ついた犬のように、私は生まれた場所へと這い戻ってきた──一人で静かに人生を振り返ろうと思ってい
たネイサンは、ブルックリンならではの自由で気ままな人々と再会し、とんでもない冒険に巻き込まれてゆく。9・11直前までの日々。オースターならでは
の、ブルックリンの賛歌、家族の再生の物語。感動の新作長編。
内容(「BOOK」データベースより)
傷ついた犬のように、私は生まれた場所へと這い戻ってきた―ブルックリンの、幸福の物語。静かに人生を振り返ろうと故郷に戻ってきたネイサンが巻き込まれる思いがけない冒険。暖かく、ウィットに富んだ、再生の物語。
著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
オースター,ポール
1947年、ニュージャージー州ニューアーク生まれ。若いうちから作家を志し、1970年代から詩、戯曲、評論の執筆、フランス文学の翻訳などに携わる。
1985年から86年にかけて刊行された「ニューヨーク三部作」で一躍脚光を浴び、以来、無類のストーリーテラーとして現代アメリカを代表する作家であり
つづけている。フランス、ドイツ、日本などでは、本国アメリカ以上に評価の高い世界的人気作家である。ブルックリン在住
柴田/元幸
1954年生まれ。東京大学教授、翻訳家。ポール・オースター、リチャード・パワーズ、スティーヴ・エリクソン、レベッカ・ブラウン、スティーヴン・ミル
ハウザー、バリー・ユアグロー、トマス・ピンチョンなどアメリカ現代文学の翻訳多数。自著『生半可な學者』で講談社エッセイ賞、『アメリカン・ナルシス』
でサントリー学芸賞を受賞
|