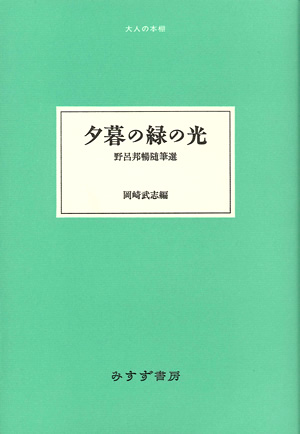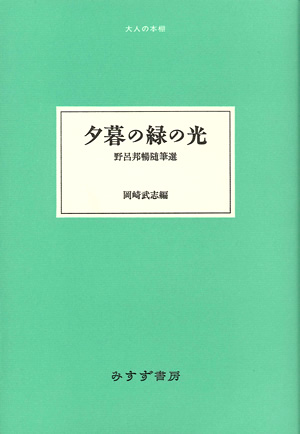|
夕暮の緑の光――野呂邦暢随筆選 《大人の本棚》 [単行本]
野呂 邦暢 (著), 岡崎 武志 (編集)
価格: ¥ 2,808
単行本: 240ページ
出版社: みすず書房 (2010/4/24)
言語: 日本語
ISBN-10: 4622080818
ISBN-13: 978-4622080817
発売日: 2010/4/24
商品パッケージの寸法: 19.4 x 13 x 1.8 cm
内容紹介
「一番大事なことから書く。
それは、野呂邦暢が小説の名手であるとともに、
随筆の名手でもあったということだ。
……ちょっとした身辺雑記を書く場合でも、
ことばを選ぶ厳しさと端正なたたずまいを感じさせる文体に揺るぎはなかった。
ある意味では、寛いでいたからこそ、
生来の作家としての資質がはっきり出たとも言えるのである」
(岡崎武志「解説」)
1980年5月7日に42歳の若さで急逝した諫早の作家野呂邦暢。
故郷の水と緑と光を愛し、
詩情溢れる、静かな激しさを秘めた文章を紡ぎ続けた。
この稀有な作家の魅力を一望する随筆57編を収録。
内容(「BOOK」データベースより)
端正な文体に秘めた人生への熱い思い。行間からほとばしる故郷九州の光と風。42歳で急逝、没後30年を経て再評価高まる作家の濃密な文業をここに贈る。
著者について
(のろ・くにのぶ)
1937年長崎市生まれ。長崎県立諫早高校卒。1965年、「ある男の故郷」が第21回文學界新人賞佳作入選。翌年発表した「壁の絵」が芥川賞候補となる。1973年、第一創作集『十一月 水晶』刊行。1974年、自衛隊体験をベースにした「草のつるぎ」で第70回芥川賞受賞。1976年、「諫早菖蒲日記」発表。1980年5月7日、42歳で急逝。著作に、短編集『海辺の広い庭』『鳥たちの河口』(1973)『一滴の夏』(1976)『ふたりの女』(1977)『猟銃』(1978)、中・長編『愛についてのデッサン』(1979)『落城記』『丘の火』(1980)、随筆集『王国そして地図』(1977)『古い革張椅子』(1979)『小さな町にて』(1982)、評論に『失われた兵士たち―戦争文学試論』(1977)、他多数。
著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
野呂邦暢
1937年長崎市生まれ。長崎県立諌早高校卒。1965年、「ある男の故郷」が第21回文學界新人賞佳作入選。翌年発表した「壁の絵」が芥川賞候補となる。1973年、第一創作集『十一月水晶』刊行。1974年、自衛隊体験をベースにした「草のつるぎ」で第70回芥川賞受賞。1976年、「諌早菖蒲日記」発表。1980年5月7日、42歳で急逝
岡崎/武志
1957年大阪生まれ。立命館大学卒。ライター、書評家
《大人の本棚》
野呂邦暢
夕暮の緑の光
野呂邦暢随筆選
岡崎武志編
2010年5月7日 第1刷発行
2010年8月5日 第4刷発行
発行所株式会社 みすず書房
〒113-0033東京都文京区本郷5丁目32-21 電話03-3814-Ol31(営業) 03-3815-9181(編集)
http;〃www.msz.co.jp
本文組版 キャップス
本文印刷所 平文社
扉・表紙・カバー印刷所 栗田印刷
製本所 誠製本
著者略歴(のろ・くにのぶ)
1937年長崎市生まれ,長崎県立諌早高校卒,1965年,「ある男の故郷」が第21回文學界新人賞佳作入選,翌年塘表した「壁の絵」が芥川賞候補となる.1973年,第一創作集『十一月 水晶」刊行.1974年,自衛隊体験をベースにした「草のつるぎ」で第70回芥川賞受賞.1976年,「諌早菖蒲日記」
発表、1980年5月7日.42歳で急逝、著作に,短編集『海辺の広い庭」「鳥たちの河口』(1973)「一滴の夏』(1976)「ふたりの女」(1977)『猟銃』〔19781,中・長編「愛についてのデッサン」(1979)『落城記」『丘の火封(1980),随筆集「王国そして地図』(197の丁古い革張椅子」(1979)『小さな町にて』(1982),評論に『失われた兵士たちー戦争文学試論』 (1977)、 他多数,
編者略歴(おかざき・たけし〉
1957年大阪生まれ.立命館大学卒.ライター,書評家.
主な著作に「文庫本雑学ノート』(1998)「気まぐれ古省店紀行』(2006)「読書の腕前」(2007}「新・文學入門』(山本善行との共署、2008)『雑談王 岡崎武志バラエティブック』(2008)「あなたより貧乏な人」(2009}他多数.
|