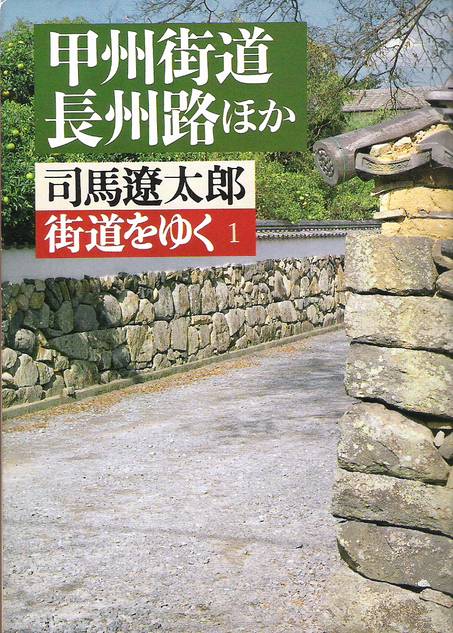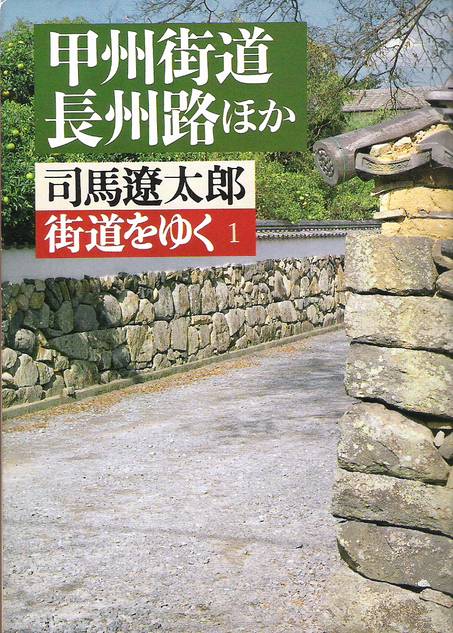|
「崇神王朝は、征服王朝である」
という戦後の諸説は、きわめて考え方として自然である。われわれは戦前、その崇神帝で代表される日本古代国家の朝鮮における植民地が「任那」であったというぐあいに教えられたが、そうであるにしてもモトは逆であろう。崇神帝で象徴される勢力が「任那」からやってきたと考えるほうが、自然であるかもしれない。が、その議論については武蔵のこの項とはさしあたって関係がない。
ともあれ、その任那が六世紀のはじめに衰弱し、ついにB本の大和王朝と同盟関係にあった百済に一部を割譲し、さらに新羅に他のすべてをとられてしまったことだけはたしかである。くだって七世紀の後半、朝鮮半島の情勢変化とともに百済の国運があぶなくなった。この、
「朝鮮半島の情勢変化」
というのが、武蔵の国にひびくのである。
それより前、北朝鮮に高句麗という強大な勢力が興って、その兵は完全な騎馬民族国家であった。その版図は満州の]部をもふくめていたから、もともと満州で遊牧していた連中が南下した勢力であり、人種は固有満州人であったであろう。高句麗は南下して百済を圧倒した。百済は倭をたのんでこれと軍事同盟を結ばざるをえない。
さらに百済は東隣の新羅とはげしく抗争しつづけ、ついに倭の大和政権からの援軍を乞うにいたった。
|