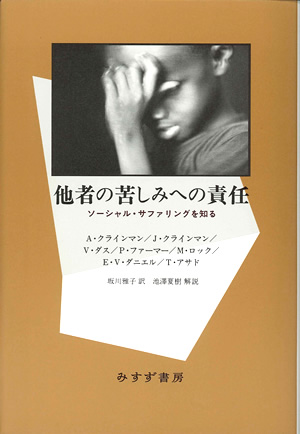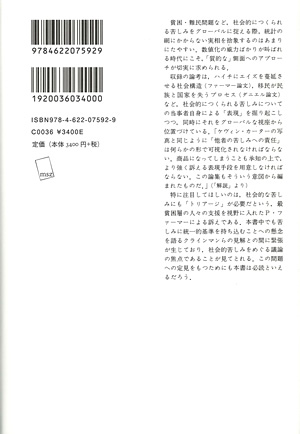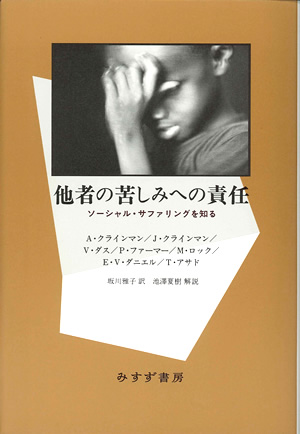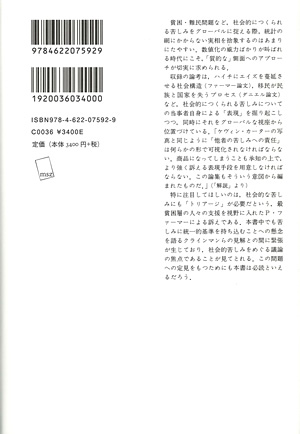|
アサドは、「世界人権宣言」の根底にある理念には文化や歴史による制約ーそれが宣言の普遍的妥当性を阻害するかどうかはさておきーがあること、また、国民全体に大量の苦痛と苦しみを与えることになる戦争等については何も言わないで、残酷で非人間的だと見なされる刑罰のみを禁止しようとすることには、根本的な偽善があることを、強く主張する。その偽善性は、「文明社会の正義と人間性の基準」を、苦しみを軽減し生をより耐えやすいものにする手段としてよりも、むしろ、新しい種類の規律をもたらすものとして、被植民者たちに押しつける植民地主義の根底にもある。植民地主義において、苦しみは社会の「進歩」のために役立つはずのものであった。自由主義的社会契約においては、痛みやトラウマをもたらす行為は、国益のために法的に是認されうるし、現実に是認されている。国益は、社会的価値の頂点として、自由主義的近代性を特徴づけるものである。アサドは、ほとんどあらゆる社会で、ある種の社会的な苦しみを持続させている為政者の政策を理解するためには、それぞれの社会の政治プロセス、その社会が目指すもの、その政策間に生じる矛盾を、一つ一つ検討すべきだと考えている。彼はまた、個人同士の私的な関係を「取り締まる」ことに対して自由主義の考え方がもつ意味を考察する。そして、そこにも相反する価値観と実践の偽善性が見られることを、彼は示す。したがって、拷問と社会的な苦しみが存在するのは、近代性の欠如のためではなく、近代的な行政組織の、国益を守るための理念や技術や戦術のためである。しかし、その近代化政策が、文化的な抑圧に対する現.地人の「防衛」を、利己的なものとして問題視するために、われわれは、保守と変化の象徴的・政治的計画に悲劇と同時にアイロニーを見いだすのである。(ⅹⅵ)
|