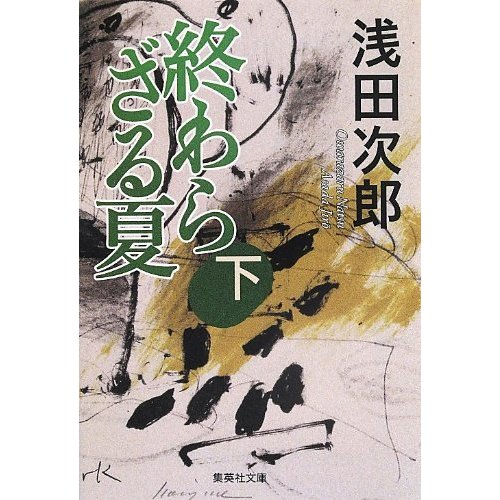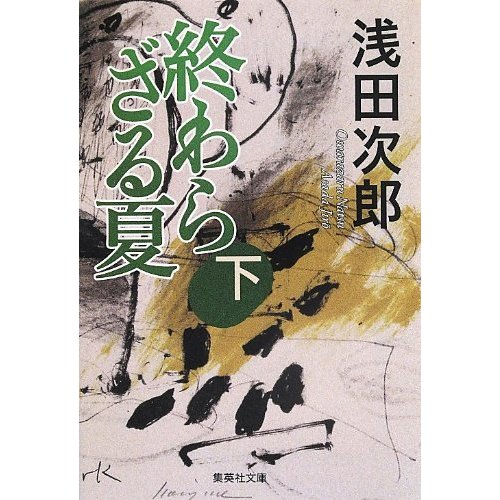���e�Љ�
1945�N8��15���A�ʉ�������Ɂq�m��ꂴ��킢�r���A�������k�̌Ǔ��Ŏn�܂����\�\�B���ꂼ��̏ꏊ�ŁA����ŁA�����ւ̊�]�����߂�l�X��`����c�Łu�푈�ƕ��a�v�B��64���o�ŕ�����܍�B(���/��v���q)
���e�i�uBOOK�v�f�[�^�x�[�X���j
1945�N8��15���A�ʉ������B�����͂��ꂼ��̎v��������Ȃ���A���{�̖������~����m��B�����̓��E��瓇�ł́A�ʖ�v���ł���Љ��炪�A�I�����
�ɂ���ė���ł��낤�ČR�̌R�g��҂��Ă����B�����A���Ɏc���ꂽ���{�R���ڂɂ����̂́A��������j�����ď㗤���Ă���\�A�R�̎p�������B�\������
�k�̌Ǔ��ŁA�Ăюn�܂����u�푈�v�̐^���Ƃ́B�푈���w�̐V���Ȃ�������A���X�̊����B
���҂ɂ���
��c ���Y (������ ���낤)
1951�N�����s�o�g�B1995�N�w�n���S�ɏ���āx�ŋg��p�����w�V�l�܁A1997�N�w�S�����x �Œ��؏܁A2000�N�w�p���`�m�`�x�Ŏēc�B�O�Y�܁A2006�N�w���������܂��x�Œ������_���|�܂Ǝi�n�ɑ��Y�܁A2008�N�w�����̓��x�ŋg��p�����w �܂��A���ꂼ���܁B�ߊ��Ɂw�܁A�������B�x�w�n�b�s�[�E���^�C�A�����g�x���B���{�y���N���u�ꖱ�����B
���җ��� (�uBOOK���ҏЉ���v���)
��c/���Y
1951�N�����s���܂�B95�N�w�n���S�ɏ���āx�ŋg��p�����w�V�l�܁A97�N�w�S�����x�Œ��؏܁A2000�N�w�p���`�m�`�x�Ŏēc�B�O�Y�܁A06�N
�w���������܂��x�Œ������_���|�܂Ǝi�n�ɑ��Y�܁A08�N�w�����̓��x�ŋg��p�����w�܁A10�N�w�I��炴��āx�Ŗ����o�ŕ����܂��A���ꂼ����
|