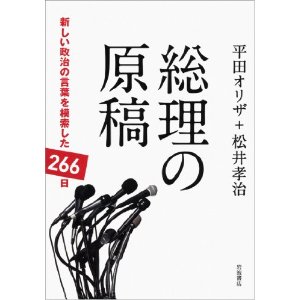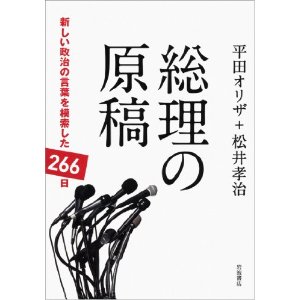2013年6月19日(水)
『総理の原稿』読了。
目次を見るとわかるように、三分の一が著者自慢の演説原稿で占められており、自画自賛の感が強い。
自信家の松井孝治クンは今後、どういう道に進むのだろうか。
電通の佐藤尚之
ツイッターの利用 42頁
安田正篤 ブレーン 34頁
2011年1月1日、総理のツイッター開始
佐々木かをり
鷲田清一 大阪大学総長 哲学カフェ 46、56頁
ガンジーの七つの大罪
| その際総理から、インドでガンジー廟に献花をしたんだけれども、そこにあった「七つの大罪」を使えないかな、という提案があった。「理念なき政治」「労働なき富」「良心なき快楽」「人格なき教育」「道徳なき商業」「人間性なき科学」「犠牲なき宗教」。その一週間前に、総理がお母様からの献金も含めて記者会見でおっしやっているわけですから、「労働なき富」はつらいなというのが第一印象だったが、もともと科学とか文化についてきちんと取り上げたいと思っていたし、所信表明演説で述べた「人間のための経済」ともつながる。労働の大切さ、資本主義のモラルというテーマも考えていた。総理の意向を聞いて、平田さんと「これは、はまりますよね」と。総理があえて自分の政治と金の問題を意識されて、それも含めて提示したいということなら、それは一つの考えかもしれない。「七つの大罪」を軸にして、どういうコンセプトの演説にするか、年末年始、官邸の自分の部屋で長い時間ポーッと考えた。 |
(67-68頁)
自画自賛
|
松井 官僚時代にかかわったスピーチでいうと、一九九六年の九月二日に日本記者クラブで橋本首相が行われた橋本行革演説は私が書きましたが、これは自由に書けました。省庁再編、国家機能の再整理と省庁数半減、官邸機能の抜本的強化、政策評価制度の導入など、後々の橋本行革のアジェンダをそこで出した。従来なら秘書官が書くんですが、その時の総理秘書官が、私が通産省の一年生の時の上司で、彼にインパクトのあるものを書いてくれと頼まれた。本質的な話ですけれども、総理というのは、その不用意な発言で大変なしっぺ返しを受けるリスクもあるわけですが、きちんと用意して、あとのシナリオも含めて詰めて発言するつもりがあれば、閣議決
|
(90頁)
平田 鳩山さんに最初にお会いした時から言ってきたことですけれども、二一世紀というのはどういう世紀かということを考えると、近代国家の枠組みが、決して解体はされないけれど、相当輪郭はぼやけるだろうと思うんですね。現在議論されているTPPなんかまさに象徴的なんだけれども、一四〇年前に日本が血の滲むような努力をして得た関税自主権を放棄するんですから、これはものすごいことですよ。「東アジア共同体」、TPP、温室効果ガス二五%削減でも何でも、程度の差はあれ国家の主権の一部を譲っていく行為です。EU各国は、通貨発行権という近代国家主権の基本的な部分を譲り渡した。このように、今後はどうしても、近代国家を支えてきた国家主権の】部を、国際社会に譲り渡さざるを得ない局面が否応なくでてくる。
そういうふうになっていく時に当然、外交と内政というのは、常に、多くの場合矛盾する。外交に力点を置くと、小村寿太郎からしてそうですけれども、優れた政治家ほど焼き打ちに遭ったりするわけです。焼き打ちにあわなくても、選挙で落ちる。だから、国家主権の一部を国際社会に譲り渡していく過程で、国民にその意義をきちんと説明していくのが、これからの政治家の大きな仕事で、そこにはたぶん「新しい言葉」が必要だろうと思った。
それからこれは鈴木寛さんなんかも言ってきたことですが、「熟議」ということ。きちんと議論をしよう、と。それは別に政治家だけのことではない、もう、イデオロギーにとらわれずに 例えば、外国人参政権問題なんていうのは僕と松井さんでは意見が違うわけです。安全保障のことについても全然違う。しかし全部のことが一致しなければ一緒に行動できないなんてことは、大体人間としてあり得ないはずなんです。だから本来は、半分以上の議案は党議拘束をかけなくてもいい。僕は、少なくとも参議院は党議拘束をかけないほうがいいと思う。外国人参政権に賛成しているから左翼だとか、夫婦別姓に賛成しているから何だとか、あいつはああいう党派だみたいなレッテル貼りをまずやめるところから、たぶん熟議というのは始まる。ほとんどのイシューは個々のものですから、様々な価値観が集まって、政治家なら政治家一人の世界観というものが形成されているはずで、特定のイデオロギーが先に立つということではないはずだ。政治家自身も、いままでは党の言葉に従って喋ればよかったけれど、政治家個々人にもうちょっと「新しい言葉」を持ってもらいたい。鳩山内閣というのはその象徴的なことができるのではないかなと思ったし、できた部分もあったと思う。私は、その「点に興味があって協力をしてきたのだと思います。ただ、それが続かなかったことがいちばん残念です。総理が国民とダイレクトに対話する仕組みを、やはり、作りたかった。
松井 さっき平田さんがおっしゃったけれど、「新しい公共」で、国とか地方が独占していた、官が独占する公共政策領域を見直すという必要は一部分あります。しかし私自身は、それで官や国家がなくなるかというと、全くそんなことはないと思う。これまで内弁慶になって地域のことに口出しばかりしていて、本当に国がやらなければならないことをやっていない。そこは平田さんと意見が違うところかもしれないけれど、たとえば外交・安全保障などの国特有分野に特化するためにも、国はもっと内政的に、本来地域社会とか個人とか企業とかが担っていたような公共の分野を地方の官や民に移譲すべきで、その空いた領域でもっと国家戦略を描くべき。現在のような時代だからこそ、私は国家意識がより重要になっていると考えるし、中央政府がやるべき仕事の大きな役割はそちらに振り向けられるべきだと思う。領土問題も断固たる対応を取るべきです。安全保障、外交戦略であったり、国家的な人材育成や研究開発、そこが空き家になっていて、どちらかというと、民間や地方自治体など中央から見て弱い立場の人たちに対して指導・監督・ |
(95-97頁)
目次
はじめに 平田オリザ…1
対談政治のコミュニケーションデザイン 平田オリザ 松井孝治…9
政権交代 「国民のさらなる勝利に向けて」 11
「基本方針」から所信表明演説へ 17
国会演説はどうやってつくられるか 24
身体性のある言葉 37
ソーシャルメディアを使う 42
ツイッターの教訓 48
「リアル鳩カフェ」 53
記者会見はオープンに 61
施政方針演説 66
官邸機能に足りないもの 76
国際交流会議演説「アジアの未来」 86
最後の演説 90
政治とコミュニケーションデザイン 94
あとがき 松井孝治…105
資料 121
「国民のさらなる勝利に向けて」 122
「基本方針」 126
「第一七三回国会における鳩山内閣総理大臣所信表明演説」 133
「第一七四回国会における鳩山内閣総理大臣施政方針演説」 150
「第一六回国際交流会議「アジアの宋来」鳩山内閣総理大臣スピーチ」 169
装丁=後藤葉子 |
|
総理の原稿 新しい政治の言葉を模索した266日
[平田オリザ/著 松井孝治/著]
岩波書店
2011年04月
1,890円
|
内容紹介
この国では人々と政治との距離が遠い。それを埋める言葉を求めて、鳩山首相演説の作成やソーシャルメディアによる情報発信に携わった二人が、政権交代の試行錯誤を踏まえつつ、これからの政治的コミュニケーションについて語る。
|
著者紹介
平田オリザ
1962年生まれ・劇作家・演出家。2009年鳩山内閣において内閣官房参与に就任・劇団「青年団」を主宰.199S年『東京ノート』で第39回岸田國士戯曲賞受賞。現在,大阪大学教授.著書『話し言葉の日本語』(井上ひさし氏との共著
2002年,小学館),『演劇のことば』(2004年,岩波書店)。
松井孝治
1960年生まれ.参議院議員(民主党所属)、鳩山内閣の官房副長官を務める.1983年通商産業省入省.1994年首相官邸に出向,内閣官房内閣副参事官.1996年通産省大臣官房総務課長補佐を経て行政改革会議調査員.同省退官後2001年参議院選挙にて京都選挙区より初当選.著書『この国のかたちを変える』(2007年,PHP研究所). |
|